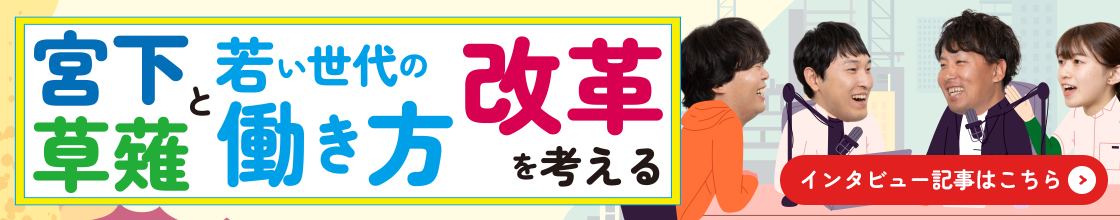管工事はおもに配管工事に携わる仕事で、新築の建築物やリフォームなど、今後も高い需要が見込まれます。管工事の国家資格である管工事施工管理技士には1級と2級があり、試験の難易度や業務領域、年収などが異なることをご存知でしょうか?
今回は、管工事施工管理技士の資格と試験の概要、1級と2級のさまざまな違いについて解説していきます。
●施工管理の求人情報を探す
> 建築施工管理 > 土木施工管理 > 電気施工管理 > 空調衛生施工管理
■管工事施工管理技士とはどんな資格?
管工事施工管理技士資格の基礎知識と、今年からスタートする試験の変更点について紹介します。
◇管工事施工管理技士資格の概要
管工事施工管理技士は、施工管理技士という国家資格の一つで、配管など管工事のスペシャリストとして認められる資格です。
管工事とは、ガスや給排水、空調、ダクトなどの管を設置するための工事を指します。生活に欠かせないインフラを整備するため、今後も高い需要が見込まれる仕事といえるでしょう。
管工事施工管理技士を取得すると、工事現場の施工管理に携われるようになります。作業員から責任者へのキャリアアップに役立つため、取得するメリットが大きい資格です。
◇2021年から施工管理技士試験が変わる
2021年より、施工管理技士試験の新制度がスタートします。新制度では、学科試験が第1次検定、実地試験が第2次検定と名称が変更になる予定です。
施工管理技士の国家試験は、学科試験に合格後、さらに実地試験に合格する必要があります。新制度では第1次検定の合格の有効期限が「無期限」になるうえに、第1次検定に合格すると「技士補」の資格が与えられます。
技士補とは、施工管理技士(監理技術者)を補佐するための資格です。2級施工管理技士などの主任技術者の資格に加え、1級技士補の資格があると監理技術者の補佐を勤められます。
補佐を配置すると、監理者は「特例監理技術者」として2つの現場の兼任が可能になるため、技術者不足をカバーする効果が期待できます。また、1級の第2次検定に不合格になったとしても、1級技士補の資格が与えられることで、試験のモチベーションも維持しやすくなるでしょう。
■管工事施工管理技士1級と2級のさまざまな違い

管工事施工管理技士1級と2級では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
受験資格や試験の合格率、業務領域などの観点から、両者の違いを比較してみましょう。
◇管工事施工管理技士1級・2級の受検資格の違い
1級、2級管工事施工管理技士の受検資格は次のとおりです。
・1級管工事施工管理技術検定(1次検定)の受検資格
| 学歴 | 実務経験年数 | ||
| 指定学科 | 指定学科以外 卒業後 |
||
| 大学卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| 短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | |
| 高等学校・中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | |
| その他の者 | 15年以上 | ||
| 技能検定合格者 | 10年以上 | ||
| 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後8年以上の実務経験 (その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上実務経験の後、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む) |
||
| 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 | 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後8年以上 | 卒業後9年6ヶ月以上 (業務能力開発促進法による2級配管技能検定合格者、給水装置工事主任技術者に限る) |
| その他の者 | 13年以上 | ||
| 2級合格者 | |||
※より詳細な説明は以下のサイトにてご確認ください。
参考)https://www.jctc.jp/exam/kankouji-1
一般社団法人全国建設研修センター
・1級管工事施工管理技術検定(2次検定)の受検資格
●1級管工事施工管理技術検定・第1次検定の合格者(1次検定において2級合格者として受検した者を除く)
●1次検定において2級合格者として受検した者については、以下のサイトにてご確認ください。
参考)https://www.jctc.jp/exam/kankouji-1
一般社団法人全国建設研修センター
・2級管工事施工管理技術検定(1次検定)の受検資格
●受検年度の末日における年齢が17歳以上の者(令和3年度の場合、平成17年4月1日以前に生まれた者)
・2級管工事施工管理技術検定(2次検定)の受検資格
●第1次検定免除者
●2級管工事施工管理技術検定・第1次検定の合格者で、次のいずれかに該当する者
| 学歴 | 実務経験年数 | ||
| 指定学科卒業 | 指定学科以外卒業 | ||
| 大学卒業者 専門学校卒業者(高度専門士に限る) |
卒業後1年以上 | 卒業後1年6ヶ月以上 | |
| 短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 | |
| 高等学校・中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
| その他 | 8年以上 | ||
| 技能検定合格者 | 4年以上 | ||
参考)https://www.jctc.jp/exam/kankouji-2
一般社団法人全国建設研修センター
・指定学科と第1次検定免除者について
指定学科とは、施工管理技士の業種に関する学科のことです。機械工学または建築学、土木工学、都市工学、電気工学、電気通信工学などが挙げられます。
また、1級・2級管工事施工管理技士の第1次検定(学科試験)の合格者、技術士の有資格者などの要件を満たすと、第1次検定が免除になります。
より詳細な説明は以下のサイトにてご確認ください。
https://www.jctc.jp/exam/kankouji-2
一般社団法人全国建設研修センター
◇管工事施工管理技士1級・2級試験の違い
施工管理技士試験の試験基準は、新旧で以下のように変更されました。
| 新制度の試験基準 | |||
| 旧制度 | 学科試験専門分野…法規、施工管理法などの一般的な知識を有する | ||
| 実地試験専門分野…法規、施工管理法などの高度な応用能力を有する | |||
| 新制度 | 第1次検定…施工技術の基礎となる知識と能力を有するかどうかを判定 | ||
| 第2次検定…施工技術の実務経験に基づいた技術管理、指導監督に関わる知識と能力を有するかどうかを判定 | |||
このように、新制度の試験では、知識に加えて実践的な能力が問われます。
また、2級管工事施工管理技士に合格すると、実務経験を問わず「1級が受検できる」ようになりました。つまり、2級に合格したらすぐに1級を受検できるため、旧制度よりも早く1級を取得できることになります。1級の試験問題は2級の知識が前提になっているため、2級受検直後の知識が定着している段階のほうが合格率も高くなるでしょう。
次に、令和元年度の管工事施工管理技士試験における、1級、2級の合格率を紹介します。
<1級管工事施工管理技士の合格率>
・学科試験…52.1%
・実地試験…52.7%
<2級管工事施工管理技士の合格率>
・学科試験…69.3%
・実地試験…44.1%
2級の学科試験の合格率は比較的高いといえますが、1級と大きな差はないようです。2級合格者が1級を受検できる新制度の施行により、今後の合格率に変化が見られるかもしれません。
◇管工事施工管理技士1級・2級の業務領域の違い
管工事施工管理技士を取得すると、工事現場の工程や品質、安全などの管理を行なう施工管理や職人の指導監督に従事できます。1級、2級を問わず、仕事内容は基本的に変わりません。
1級と2級における業務領域の大きな違いは、資格によってなれる技術者の種類が変わることです。1級は特定建設業または一般建設業における専任技術者、主任技術者、監理技術者と認められます。監理技術者は規模を問わず、さまざまな建設現場に従事できます。
一方、2級は一般建設業の専任技術者、主任技術者になることが可能です。技士補として監理技術者の補佐を務められるのは1級に限られるため、2級のみを取得している場合は仕事の規模に制限があります。
◇管工事施工管理技士1級・2級の年収の違い
年収の点では、管工事施工管理技士1級のほうが高い傾向にあります。
1級は大規模な工事に携われる監理技術者になれること、公共工事の経営事項審査で1級の有資格者の評価が高くなることが要因でしょう。1級の年収は400万円~750万円、2級は300万円~600万円が目安とされ、年収の差が数字から見てとれます。
管工事に限らず、施工管理技士の有資格者は2級よりも1級の年収が高い傾向にあるようです。仕事内容に大きな差はないため、1級の取得に挑戦した方が得策といえるでしょう。
■まとめ
管工事施工管理技士は、ガスや給排水、空調などの管工事のスペシャリストと認められる国家資格です。施工管理技士試験の新制度により、1級の第1次検定合格者には1級技士補の資格が、2級の合格者には実務経験を問わず1級の受験資格が与えられるようになりました。
仕事内容や合格率には大きな差がない一方、監理技術者の対象外になる2級は業務領域に限度があります。待遇面では1級の年収が高い傾向があるため、2級を取得している方が1級の受験に挑戦するメリットは大きいでしょう。
管工事施工管理技士試験に疑問点がある方や、転職でお悩みの方は、現キャリのキャリアアドバイザーにぜひご相談ください。

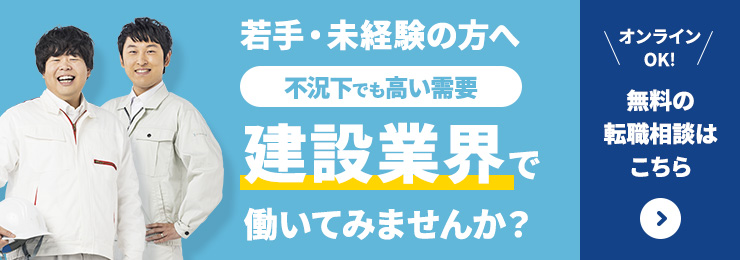




_180x98.jpg)