電気工事施工管理技士とは、電気工事現場における施工計画作成や工程管理、品質管理、原価管理、安全管理などを担うための知識や技術力を認定する国家資格です。
極めて専門性が高い資格であるため、「1級と2級の違いは?取得すると何ができる?」「資格の取り方は?難易度は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで本記事では、これから電気工事業界で活躍したい方や、資格取得を目指す方に向けて、電気工事施工管理技士の基礎知識や試験情報について分かりやすく解説します。
電気工事施工管理技士の業務内容や、1級・2級の違い、取得難易度、具体的な取り方なども網羅的にまとめました。
電気工事業界でキャリアアップを目指している方や、これから資格取得を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- ✓ 電気工事施工管理技士の仕事内容と活躍フィールド
- ✓ 1級・2級の違い(役割・現場規模・経審加点など)
- ✓ 試験内容・受検資格・学習の進め方の要点
電気工事施工管理技士とは?
電気工事施工管理技士とは、建物の新築や増築に伴う電気設備工事を管理するために必要な国家資格です。
この資格を取得することで、電気設備工事において「工程管理・原価管理・品質管理・安全管理」といった4大管理に加え、施工計画の作成や電気工事の監理業務を担当できるようになります。
ここでは、電気工事施工管理技士の主な勤務先や年収についても詳しく解説していきます。
電気工事施工管理技士の勤務先
電気工事施工管理技士の勤務先には、建設会社や電気設備工事会社、電力会社などが挙げられます。
新築や改修工事を担う建設現場だけでなく、電気工事の保守管理を行う企業でも、電気工事施工管理技士の資格が求められるケースもあります。
主な工事内容は、建築物の構内電気設備工事や屋内外の照明電気工事、引込線工事などです。
電気工事施工管理技士は、これらの現場において監理技術者や主任技術者として配置され、施工管理業務を担います。
電気工事施工管理技士の平均年収
厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「jobtag」によると、電気技術者の平均年収は約688万円です。
国税庁が公表した令和5年分の民間給与実態統計調査によれば、全職種の平均年収は約460万円となっており、電気工事施工管理技士は220万円ほど高い水準に位置しています。
このため、電気工事施工管理技士は高収入を目指せる職種といえるでしょう。
ただし、企業規模や経験年数、資格の有無、勤務地域によって年収には差があります。掲載されている年収データはあくまで目安とし、転職活動や就職先選びの際には、個別に条件を確認するようにしましょう。
一般に、2級電気工事施工管理技士よりも1級電気工事施工管理技士の方が担当する現場の規模が大きく、業務の幅も広いため、より高収入が期待できます。
出典:電気技術者|職業情報提供サイトjobtag 国土交通省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査|国土交通省
電気工事施工管理技士における1級と2級の違い
電気工事施工管理技士には、1級と2級の区分があり、担当できる工事規模や業務範囲、経営事項審査(経審)における評価基準にも違いがあります。
どちらも電気工事に欠かせない存在ですが、役割や責任の範囲には明確な違いがあるため、事前に理解を深めておきましょう。
監理技術者資格の違い
1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士の大きな違いは、監理技術者に認定されるかどうかにあります。
| 項目 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 監理技術者への認定 | 認められる | 認められない |
| 主任技術者への認定 | 認められる | 認められる |
| 担当できる現場規模 | 大規模現場まで対応可能 | 小規模~中規模中心 |
1級を取得すると、監理技術者および主任技術者として認められます。監理技術者とは、元請の特定建設業者が総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を締結する際に、現場に配置が義務付けられている技術者のことです。
一方、2級電気工事施工管理技士は主任技術者にはなれるものの、監理技術者としては認められません。主任技術者は、請負金額や発注形態にかかわらず、施工現場の技術管理を担う役割を果たします。このように、1級と2級では、担う現場規模や責任範囲に明確な違いが生じます。
業務領域の違い
1級電気工事施工管理技士は、監理技術者として認められるため、公共工事をはじめとする大規模な工事にも対応できます。一方、2級電気工事施工管理技士は、担当できる工事規模が限られ、小規模から中規模の工事を中心に従事します。
| 項目 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 担当できる工事規模 | 大規模工事を含む | 小規模〜中規模工事中心 |
| 活躍の場 | 公共工事や大型施設工事など | 中小規模の民間工事など |
| キャリアパス | 大規模現場管理・監理技術者へステップアップ可能 | 実務経験を積んで1級取得を目指す流れが一般的 |
大規模な建設現場で活躍したい場合は、まず2級を取得し、実務経験を積んだうえで1級取得を目指す流れが一般的です。
経営事項審査の加点の違い
電気工事施工管理技士には、1級と2級で経営事項審査(経審)における加点内容にも明確な違いがあります。
| 項目 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 技術力評価の基本加点 | 5点 | 2点 |
| 監理技術者証+講習受講による追加加点 | 1点(合計最大6点) | なし |
| 第一次検定(技士補)合格による加点 | 4点(要主任技術者資格併有) | なし |
| 最大加点差 | 最大4点差 | ー |
1級電気工事施工管理技士の場合、経営事項審査の技術力評価において1人あたり5点が加算されます。監理技術者証の取得と、監理技術者講習の受講を終えていれば、追加で1点が加算され、最大で6点となります。
一方、2級電気工事施工管理技士の加点は1人あたり2点に留まるため、1級と2級では、最大で4点もの差が生じるのです。
また、1級電気工事施工管理技士は、第一次検定(学科試験)に合格した段階でも「1級電気工事施工管理技士補」として4点加算の対象になります。この場合、主任技術者となる資格(2級電気工事施工管理技士など)を併せ持っていることが条件です。
公共工事への入札を目指す企業にとって、経営事項審査の技術点は非常に重要な評価項目です。そのため、2級よりも1級の資格を保有している方が、企業内での評価も高まる傾向にあります。
出典:経営事項審査申請の手引き(資料編)
出典:経営事項審査の審査基準の改正について
第一次検定合格後の違い
1級電気工事施工管理技士の第一次検定(学科試験)に合格すると、「1級電気工事施工管理技士補」として認定されます。
1級電気工事施工管理技士補は、監理技術者の補佐業務に携わることが可能です。
一方、2級電気工事施工管理技士の場合も、第一次検定に合格すれば「2級電気工事施工管理技士補」となりますが、新たに担当できる業務はありません。
| 項目 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 第一次検定合格後の資格 | 1級電気工事施工管理技士補 | 2級電気工事施工管理技士補 |
| 取得後の業務範囲 | 監理技術者の補佐業務に従事可能 | 新たに担当できる業務は特になし |
なお、2級電気工事施工管理技士補の資格だけでは、主任技術者として現場に配置されることはできません。
主任技術者として業務を担当するには、別途2級電気工事施工管理技士の資格を取得する必要があります。
このように、電気工事施工管理技士の1級と2級では、第一次検定合格後に可能となる業務範囲にも明確な違いがあります。
1級・2級電気工事施工管理技士の試験概要
ここでは、1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士の試験における検定の試験科目や受検資格、合格基準点や合格率・難易度について解説します。
受検するときに必要な情報を把握し、効率的に試験勉強のスケジュールを立てるために役立てましょう。
1級電気工事施工管理技士の試験科目
1級電気工事施工管理技士の検定科目について、第一次検定と第二次検定に分けて解説します。
どの分野の対策が必要か、事前に確認しておきましょう。
第一次検定の試験科目
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 電気工学 | 電気理論・電気機器・電気系統・電気応用 |
| 電気設備 | 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備・電車線・その他の設備 |
| 関連分野 | 機械設備関係・土木関係・建築関係 |
| 設計・契約関係 | 設計・契約関係 |
| 施工管理法 | 応用能力問題・施工計画・工程管理・品質管理・安全管理・工事施工 |
| 法規 | 建設業法・電気事業法等・建築基準法等・消防法・労働安全衛生法・労働基準法 |
出典:1級電気施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
1級電気工事施工管理技士の第一次試験は、四肢択一式または五肢択一式の選択形式で出題されます。
さらに、全体の出題の中には必須問題と選択問題があります。
全89問の出題の中から必須問題21問に加え、選択問題の中から39問を選んで解答し、合計60問に回答する形式です。合格基準は60%以上であるため、36問以上の正解で合格となります。
第二次検定の試験科目
| 試験科目 | 出題傾向 |
|---|---|
| 施工経験記述 | 指定された現場条件に基づき、「工程管理」「品質管理」「安全管理」における予想される問題点と、その対策・留意点を記述する問題 |
| 施工管理 | 「品質管理」または「安全管理」に関する用語の中から任意に2つを選び、それぞれの意味や留意点を記述する問題 |
| 計算問題 | 送配電を中心とした電気設備に関する計算問題 電気理論・電気機器・発変電・送配電の基本定理など |
| 電気設備 | 各種電気設備に関する技術的内容を論述する問題 |
| 法規 | 建設業法・監理技術者・元請負人の義務・施工体制台帳・電気事業法・電気工事士 |
出典:1級電気施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
第二次検定は、記述式と五肢択一式の混合形式で実施されます。出題数は全5問で、すべて必須問題です。全体で正答率60%以上を取得する必要があります。
1級電気工事施工管理技士の受検資格
1級電気工事施工管理技士の受検資格は、第一次検定と第二次検定でそれぞれ異なります。 令和6年度から、電気工事施工管理技士を含む施工管理技術検定の受検資格が改正され、要件が一部緩和されました。 令和6年度から令和10年度までは経過措置期間として、「新受検資格」と「旧受検資格」のいずれでも受検が可能です。
ここでは、1級電気工事施工管理技士の第一次検定および第二次検定における新しい受検資格について解説します。受検資格を確認する際の参考にしてください。
第一次検定の受検資格
1級電気工事施工管理技士の第一次検定を受けるには、試験実施年度の4月1日時点で満19歳以上であることが必要です。
たとえば、令和7年度に受検する場合は、平成19年4月1日以前に生まれていることが条件となります。
第二次検定の受検資格
1級電気工事施工管理技士の第二次検定の受検資格は、1級第一次検定合格者や2級第二次検定合格者、第一種電気工事士試験合格者(または免状交付者)など、5つの区分に分かれています。
それぞれに必要な実務経験年数が定められているため、以下の表で確認しましょう。
| 区分 | 必要実務経験 |
|---|---|
| 【区分1】 1級第一次検定合格者 |
・1級電気工事第一次検定合格後、実務経験5年以上 ・1級電気工事第一次検定合格後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・1級電気工事第一次検定合格後、監理技術者補佐としての実務経験1年以上 |
| 【区分2】 1級第一次検定および2級第二次検定合格者 |
・2級電気工事第二次検定合格後、実務経験5年以上 ・2級電気工事第二次検定合格後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
| 【区分3】 1級第一次検定受検予定および2級第二次検定合格者 |
・2級電気工事第二次検定合格後(※4)、実務経験5年以上 ・2級電気工事第二次検定合格後(※4)、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
| 【区分4】 1級第一次検定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者 |
・第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上 ・第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
| 【区分5】 1級第一次検定受検予定、および第一種電気工事士試験合格または免状交付者 |
・第一種電気工事士試験合格または免状交付後、実務経験5年以上 ・第一種電気工事士試験合格または免状交付後、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
出典:令和7年度1級 電気工事施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業振興基金
実務経験の詳細について詳しく知りたい方は、一般財団法人 建設業振興基金のWebサイトから「受検の手引き」をご覧ください。
1級電気工事施工管理技士の合格基準点
1級電気工事施工管理技士の合格基準点は、以下の通りです。
- 第一次検定 全体で得点が60%以上かつ施工管理法の得点が50%
- 第二次検定 得点が60%以上
出典:令和7年度1級電気工事施工管理技術検定第一次検定・第二次検定受検の手引 総合版(旧受検資格用)|一般財団法人 建設業振興基金
第一次検定・第二次検定ともに、不合格となった場合は、不合格通知書によって成績が通知されます。
通知内容は全体の得点結果のみであり、設問ごとの得点や詳細な評価内容は開示されません。
第一次検定では、合格基準に満たない場合に正解数(例:「〇〇問正解」)が通知されます。第二次検定では得点率に応じて「A・B・C」の3段階で評価され、不合格者のみ通知されます。なお、合格者への成績通知はありません。
1級電気工事施工管理技士の合格率・難易度
1級電気工事施工管理技士の第一次検定および第二次検定の直近3年間の合格率は以下の通りです。
| 実施年 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 36.7% | 49.6% |
| 令和5年度 | 40.6% | 53.0% |
| 令和4年度 | 38.3% | 59.0% |
出典:1級電気工事施工管理技士受験者数・合格率動向|KGKC建設技術教育センター
第一次検定の合格率は概ね35〜40%、第二次検定では50〜60%程度となっています。 難易度は極端に高いわけではないものの、知識問題に加えて計算問題や記述問題にも対応する必要があるため、計画的な対策が求められます。
2級電気工事施工管理技士の試験科目
2級電気工事施工管理技士の試験科目について、第一次検定と第二次検定に分けて解説します。どの分野の対策が必要になるか、事前に確認しておきましょう。
第一次検定の受検資格
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 電気工学 | 電気理論・電気機器・電気系統・電気応用 |
| 電気設備 | 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備・電気通信関係・電車線・その他の設備 |
| 関連分野 | 機械設備関係・土木関係・建築関係 |
| 設計・契約 | 設計・契約関係 |
| 施工管理法 | 能力問題・施工計画・工程管理・品質管理・安全管理・工事施工 |
| 法規 | 建設業法・電気事業法等・建築基準法等・消防法・労働安全衛生法・労働基準法・その他関連法規 |
出典:1級電気施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
第一次検定の試験は、四肢択一式または五肢択一式で出題されます。出題数は全部で62問あり、そのうち必須問題が9問、選択問題が53問です。
この中から、必須問題9問と選択問題31問の、合計40問を選んで解答します。
第二次検定の受検資格
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 施工経験記述 | 指定された現場条件に基づき、工程管理または安全管理の問題点と対策・留意点を記述する問題 |
| 施工管理 | 安全管理または品質管理に関する用語の説明 高圧受電設備の単線結線図に関する記述問題 |
| 計算問題 | 電気設備に関する四肢択一形式の計算問題 |
| 電気設備 | 各種電気設備に関する用語の技術的内容を簡潔に論述する問題 |
| 法規 | 建設業法が中心の法文中の空欄に語句や数値を入れる四肢択一式の問題 電気工事士法・労働安全衛生法・労働基準法・建築基準法 |
出典:2級電気施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
第二次検定は、記述式または四肢択一式の形式で出題されます。
問題数は全5問で、すべての問題に解答する必要があります。択一と記述を組み合わせた形式です。
2級電気工事施工管理技士の受検資格・合格率
2級電気工事施工管理技士の受検資格は、1級電気工事施工管理技士と同様に、第一次検定と第二次検定で異なります。また、令和6年度から施工管理技術検定の受検資格が改正され、要件が一部緩和されました。
令和6年度から令和10年度までは、経過措置期間として「新受検資格」と「旧受検資格」のいずれでも受検が可能です。
ここでは、令和7年度に受検する場合の2級電気工事施工管理技士の第一次検定と第二次検定における新受検資格について解説します。
第一次検定の受検資格
2級電気工事施工管理技士の第一次検定を受検するには、試験が行われる年度内に満17歳以上となることが条件とされています。
たとえば、令和7年度に受検する場合は、平成21年4月1日以前に生まれている方が対象です。
第二次検定の受検資格
2級電気工事施工管理技士の第二次検定の受検資格は、保有資格や実務経験に応じて3つの区分に分かれます。区分ごとの要件は以下の通りです。
| 区分 | 必要実務経験 |
|---|---|
| 【区分1】 | 2級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格後、実務経験3年以上 |
| 【区分2】 | 1級電気工事施工管理技術検定第一次検定合格後、実務経験1年以上 |
| 【区分3】 | 電気工事士試験または電気主任技術者試験の合格後または免状交付後、実務経験1年以上 ※別途、2級または1級電気工事施工管理技術検定第一次検定の合格が必要 |
出典:令和7年度2級 電気工事施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業振興基金
実務経験の詳細について詳しく知りたい方は、一般財団法人 建設業振興基金のWebサイトから「受検の手引き」をご覧ください。
2級電気工事施工管理技士の合格基準点
2級施工管理技士の合格基準点を確認しておきましょう。
2級電気工事施工管理技士の合格基準点 第一次検定 得点が60%以上 第二次検定 得点が60%以上 不合格者には不合格通知書にて成績が通知されますが、内容は全体の結果のみで、設問ごとの得点は開示されません。
第一次検定では正解数が通知され、第二次検定では「A・B・C」の評定で評価されます。
なお、検定の実施機関は成績に関する問い合わせには対応しておらず、合格者への成績の通知は行われません。
出典:令和7年度【前期】2級電気工事施工管理技術検定第一次検定のみ受検申請専用受検の手引|一般財団法人 建設業振興基金
出典:令和6年度2級電気工事施工管理技術検定第二次検定のみ申請用受検の手引|一般財団法人 建設業振興基金
2級電気工事施工管理技士の合格率・難易度
2級電気工事施工管理技士の、第一次検定と第二次検定の3年間の合格率を把握しておきましょう。
| 実施年 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 47.5% | 51.4% |
| 令和5年度 | 43.8% | 43.0% |
| 令和4年度 | 55.6% | 61.8% |
出典:2級電気工事施工管理技士受験者数・合格率動向|KGKC建設技術教育センター
2級電気工事施工管理技士の合格率は、第一次検定で45〜55%程度、第二次検定は40〜60%程度です。
極端に合格率が低いわけではありませんが、幅広い範囲から出題されるため、計画的に学習を進めていくことが大切です。
電気工事施工管理技士の主な仕事内容
ここでは、電気工事施工管理技士が担う6つの主な業務内容について解説します。
電気工事施工管理技士の業務内容を理解しておくことで、資格取得後のキャリアイメージを具体的に描けるようになるでしょう。
1. 工程管理
電気工事施工管理技士は、電気工事全体を統括する役割を担い、主に管理業務を担当します。
なかでも工程管理は、工事を円滑に進めるために欠かせない業務のひとつです。
具体的には、工程の進行管理、作業員や重機の手配、下請け業者や工事資材の発注・管理、工事工程表や電気施工図の作成、作業員への情報共有などを行います。
また、施工開始前の準備を整え、工事が始まった後は、工程表どおりに進んでいるかを随時チェックしながら進捗を管理していきます。
2. 品質管理
品質管理は、電気工事施工管理技士にとって欠かせない重要な業務の一つです。品質管理とは、電気設備のデザイン、強度、寸法、材質、機能などが設計図や仕様書、法令基準に適合しているかを工程ごとに確認し、必要に応じて品質試験を実施することを指します。
品質試験を通じて、電気設備における問題点や不備を早期に発見し、適切な対応を図ることが目的です。前工程での品質不良は、後続作業の遅延やトラブルを招く原因となるため、品質管理は長期的な設備維持や工期順守の観点からも非常に重要といえます。
具体的な業務としては、設計図や仕様書に定められた基準を満たしていることを証明するために、工程ごとに写真を撮影し、記録を残す作業が挙げられます。
3. 安全管理
安全管理とは、作業員が安全に作業を遂行できる環境を整備し、労働災害を未然に防ぐ取り組みのことです。電気工事施工管理技士にとって、極めて重要な業務の一つといえます。
たとえば、作業時に使用する脚立の点検、必要に応じた補助者の配置指示、夏場の熱中症対策、感電防止策の徹底などが含まれます。
これらの施策を適切に講じることで、現場の安全性を高め、工事を円滑に進行できます。
4. 原価管理
原価管理とは、建設現場における人件費や材料費などの費用を適切に算出し、あらかじめ設定された予算内で工事を完了させるための業務です。
電気工事施工管理技士は、電気工事の見積作成をはじめ、現場で発生する各種経費を予算と進捗状況を踏まえて把握し、随時、予算との差異を確認します。
予算からの乖離が発生した場合は、原因を分析し、計画や工程の見直しを行い、適正な利益を確保することも重要な役割です。
5. デスクワーク
デスクワークも、電気工事施工管理技士にとって重要な業務の一つです。電気工事施工管理技士の仕事は、現場対応だけでなく、各種書類作成や事務手続き、施主との交渉・プレゼンテーションなどの業務も含まれます。
具体的には、積算による見積書作成、発注業務、工事担当者との連絡・調整、役所への各種申請書類の作成・提出などが挙げられます。
プロジェクト初期には施主との交渉に加え、プレゼンテーションを行う機会もあり、現場管理と事務処理の両面で幅広い対応力が必要です。
6. 情報共有などの打ち合わせ業務
関係者との情報共有や打ち合わせも、電気工事施工管理技士にとって欠かせない業務です。 建設現場において電気工事を円滑に進めるためには、発注者、設計者、作業員などさまざまな関係者との密な連携が必要となります。 発注者との打ち合わせはもちろん、作業員に対しても単なる指示・伝達にとどまらず、適切にコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことが重要です。
適切な連携体制が整えば、工事の品質向上と安定した進捗管理にもつながるでしょう。
電気工事施工管理技士になると何ができる?
1級または2級電気工事施工管理技士を取得すると、主に次の7種類の電気工事における施工管理業務を担うことができます。
- 照明設備工事
- 送配電線工事
- 発電設備工事
- 構内電気設備工事
- 信号設備工事
- 非常用電源設備工事
- 電車線工事
これらの工事は、一般住宅における電気設備工事を担当する場合もあれば、大規模な商業施設やオフィスビルにおける電気設備の施工管理を担うこともあります。
さらに、信号設備工事や電車線工事といった、社会インフラを支える工事にも携わることができます。
これらは鉄道電気設備専門の工事会社が行うケースが多いですが、関連企業に勤務している場合、電気工事施工管理技士がこうしたプロジェクトにも関わることも可能です。
電気工事施工管理技士の取り方
電気工事施工管理技士を取得するには、まず第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)に合格する必要があります。
受検資格は学歴や実務経験によって異なりますが、令和6年度以降は要件が一部緩和されたことによって受検しやすくなりました。
試験は電気工学・施工管理法・法規など幅広い分野から出題されるため、早めに学習計画を立てて、過去問題を繰り返し行う必要があります。 第一次検定に合格すると「電気工事施工管理技士補」として認定され、現場で実務経験を積みながら第二次検定を目指すことができます。
電気工事施工管理技士の効果的な勉強方法
電気工事施工管理技士の試験に合格するためには、出題範囲を把握したうえで、計画的に学習を進めることが重要です。
まずは公式テキストや過去問題集を用いて、出題傾向と頻出分野を確認しましょう。 第一次検定では四肢択一式・五肢択一式が中心となるため、インプットと同時に問題演習を繰り返し、知識を定着させることがポイントです。
第二次検定では記述式問題もあるため、論述力や計算問題への対応力も鍛える必要があります。 効率的に試験対策をしたい方は、市販の参考書のほか、通信講座や資格特化のスクールを活用するのもおすすめです。
働きながら受験する方は、仕事と学習の両立を図るために、隙間時間を活用し、毎日の学習習慣を継続することが大切だと言えるでしょう。
電気工事施工管理技士を取得するメリット
電気工事施工管理技士を取得する最大のメリットは、努力次第で「キャリアアップ」と「年収アップ」の両方を実現しやすくなることだと言えます。
1級電気工事施工管理技士を取得すれば、監理技術者として大規模工事に携われるため、企業内での評価やポジションが高まり、収入水準も上がりやすくなります。
また、公共工事を受注する際に求められる技術者要件を満たすため、転職市場でも大きな強みとなるでしょう。
さらに、資格取得によって専門性が証明され、社内昇進や独立開業といった選択肢も広がります。
電気工事業界で安定したキャリアを築きたい方にとって、取得する価値の高い資格と言えます。
まとめ
電気工事施工管理技士は、1級・2級ともに需要が高く、キャリアアップや年収アップにつながる国家資格です。
1級と2級で担当可能な工事の規模や役割が異なります。特に、1級電気工事施工管理技士を取得すると、監理技術者として大規模な現場で活躍でき、企業からの評価も高くなるため、年収アップやキャリアアップが期待できるでしょう。
まずは2級電気工事施工管理技士を取得し、実務経験を積みながら1級電気工事施工管理技士の取得に向けて勉強を進めていくことをおすすめします。
資格取得に向けて実務経験を積みたい方や、希望条件に合う転職先を探している方は、建設業界専門の転職エージェント「ベスキャリ建設」にご相談ください。
ベスキャリ建設では、建設業界に精通したキャリアアドバイザーが一人ひとりの現状や目標をヒアリングし、経験やスキルを最大限に活かせる職場をご提案いたします。
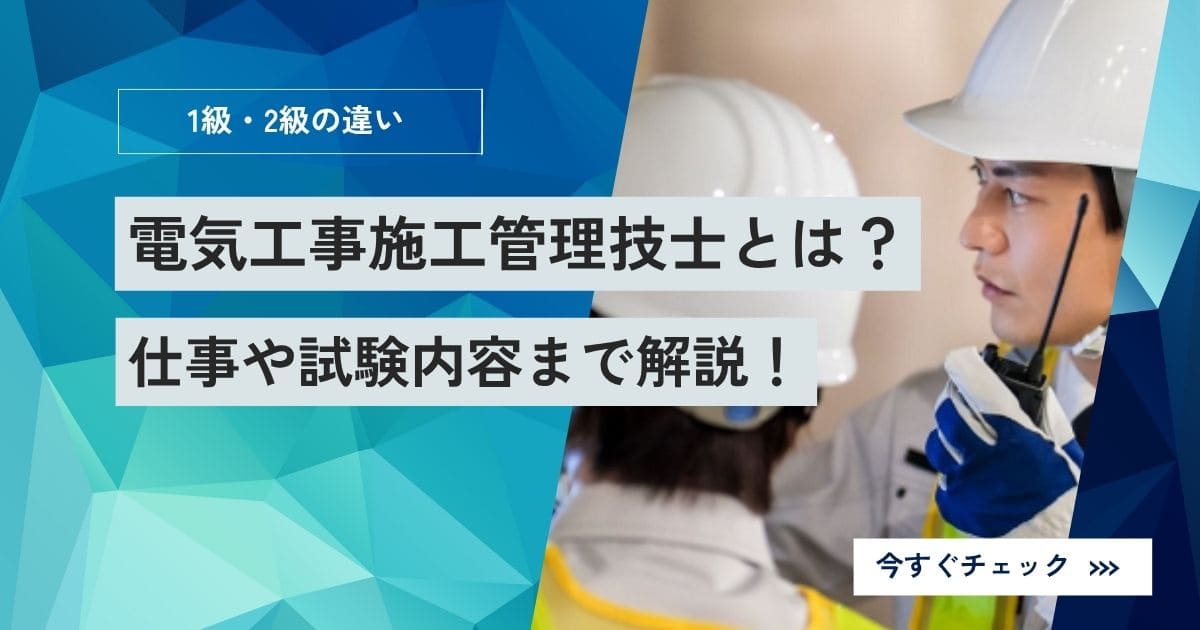
_180x98.png)
_180x98.png)
_180x98.png)
 (1)_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


