建設業界には、キャリアアップや転職などの場面において有利に働く資格が多数あります。
建築士や施工管理技士のほか、電気工事士や宅地建物取引士など、建築系以外の資格も現場や企業で高く評価されています。
しかし、資格の数が多く「どの資格を取ればいいのか迷っている」「自分の職種に合った資格を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建設業界でキャリアを積みたい方に向けて、職種別におすすめの資格を17種ご紹介します。今後のキャリア形成に向けて資格取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
【合格率】建設業界の資格難易度ランキングTOP5
建築・電気分野の資格は難易度に大きな差があります。中でも電験一種や一級建築士などは合格率が非常に低く、取得には高い専門性と継続的な学習が求められます。
以下に、建設業界の代表的な国家資格・民間資格の合格率ランキング(上位5つ)をまとめました。
| 順位 | 資格名 | 合格率 |
|---|---|---|
| 1位 | 第一種電気主任技術者(電験一種) | 6%前後 |
| 2位 | 第二種電気主任技術者(電験二種) | 8%前後 |
| 3位 | 一級建築士 | 9.5%前後 |
| 4位 | 第三種電気主任技術者(電験三種) | 10.5%前後 |
| 5位 | 建築CAD検定試験准1級 | 11%前後 |
※合格率や難易度は公式発表や過去データを参考にしていますが、年度ごとに変動があるため、目安としてご活用ください。
合格率の低さは、その資格が持つ専門性や業務独占性の高さを示しています。
【建築系】建設業界で役立つ資格
建設業界の中でも、建築分野に関する資格は多岐にわたり、建築士や建築施工管理技士は、設計や現場管理を担ううえで欠かせない国家資格として広く知られています。
ここでは、建築分野で働く方に向けて、現場や設計業務に役立つおすすめの資格を紹介します。
建築士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級、2級、木造 |
| 主な業務内容 | 建築物の設計・工事監理など |
| 受験資格 | 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校などで指定科目を修めて卒業した者(所定の実務経験が必要) 建築設備士(1級の受験には所定の実務経験が必要) 7年以上の実務経験がある者(2級または木造のみ) |
| 試験内容 | 学科試験(四肢択一式)、設計製図の試験 |
出典:建築士試験パンフ|国土交通省
出典:一級建築士試験 出題科目、出題数等|公益財団法人 建築技術教育普及センター
建築士は、建築物の設計や工事監理などの業務を担える国家資格です。建物の規模や種類により、1級や2級、木造の3種類に分かれています。
建築士の受験資格は、大学や短期大学などで指定科目を修めて卒業した方や、所定の実務経験がある場合などです。試験は四肢択一式の学科試験と、設計製図の試験が出題されます。
建築に関する科目のある学科・コースなどを卒業するのが、建築士資格を受験する最短ルートです。
建築設備士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | 建築設備の設計や工事監理など |
| 受験資格 | 大学・短期大学・高等学校などで建築・機械・電気に関する課程を修めて卒業した者 一級建築士などの資格取得者 建築設備の実務経験を有する者 上記それぞれに応じて所定の実務経験年数が必要 |
| 試験内容 | 学科試験、設計製図 |
出典:建築設備士(制度全般)|公益財団法人 建築技術教育普及センター
建築設備士は、空調や換気、電気などの建築設備について設計や工事監理などを行える国家資格です。建築士に対して、建築設備に関する設計や工事監理のアドバイスを行います。
受験資格は、大学などで建築や機械、電気などの課程を修めた場合や一級建築士の資格を取得している場合などが該当します。
受験するには、所定の実務経験が求められるため、働きながら資格取得を目指すのが一般的です。 建築設計や工事において建築設備士の配置は義務ではありませんが、建築設備の高度化・複雑化が進んでおり、需要の高い資格です。
構造設計1級建築士・設備設計1級建築士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 構造設計1級建築士、設備設計1級建築士 |
| 主な業務内容 | 構造設計、設備設計 |
| 受験資格 | 一級建築士として5年以上の構造設計業務に従事した後、登録講習機関の行う講習の課程を修了した者 |
| 試験内容 | 学科試験(四肢択一式、記述式) |
出典:構造設計一級建築士|公益財団法人 建築技術教育普及センター
出典:令和6年度構造設計一級建築士講習 受講要領|公益財団法人 建築技術教育普及センター
構造設計1級建築士・設備設計1級建築士は、構造設計・設備設計の高度なスキルを持つ専門家として認められた者に与えられる国家資格です。
一定以上の規模の建築物は、構造設計1級建築士・設備設計1級建築士が設計に関与することが義務づけられています。 構造設計1級建築士・設備設計1級建築士の受験資格は、1級建築士として構造設計に5年以上の業務経験がある者です。
登録講習機関の実施する講習を受けて、修了考査に合格することで、構造設計1級建築士・設備設計1級建築士を取得できます。
受験資格や修了考査の難易度は高く、容易に取得できる資格ではありません。独占業務であるため、建設業界での需要が高い資格です。
建築施工管理技士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 建設工事の施工管理 |
| 受験資格 | 1級:試験実施年度に満19歳以上となる者 2級:試験実施年度に満17歳以上となる者 |
| 試験内容 | 学科試験(マークシート方式・記述式) |
出典:1級 建築施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業振興基金
出典:2級 建築施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業振興基金
出典:受検の手引|一般財団法人 建設業振興基金
建築施工管理技士は、建設工事の施工管理を担う技術者に与えられる国家資格です。1級と2級の2つの等級があります。試験は一次検定と二次検定があり、いずれも学科試験です。
受験資格は年齢制限のみであるため、学生から社会人まで幅広い年齢層の人が受験しています。 建築施工管理技士は、特定建設業や一般建設業の営業所に設置が義務づけられている各種技術者を務められるのが特徴です。
大規模工事の主任技術者や監理技術者になるには、1級建築施工管理技士の資格を取得していなければなりません。 一方で、中小規模の工事現場で主任技術者になれるのが、2級建築施工管理技士です。
現場への設置が義務づけられる各種技術者に就くことができる資格のため、建築施工管理技士は継続的に高い需要があります。 将来性の高い資格で、今後も安定したキャリアを築ける資格といえるでしょう。
【土木系】建設業界で役立つ資格
道路や橋、河川、トンネルなどのインフラ整備を支える土木分野では、土木施工管理技士や測量士といった資格が、現場の管理や設計業務を行ううえで重要な役割を担います。
ここでは、土木分野で活躍したい方に向けて、建設業界で役立つ土木系の資格を紹介します。
土木施工管理技士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 土木工事の施工管理 |
| 受験資格 | 1級:受験年度中における年齢が満19歳以上の者 2級:受験年度中における年齢が満17歳以上の者 |
| 試験内容 | 学科試験(マークシート方式、記述式) |
出典:1級土木施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:2級土木施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:1級土木施工管理技士 出題傾向|建設技術教育センター
土木施工管理技士は、土木工事の施工管理を行う技術者に与えられる国家資格です。 土木施工管理技士の資格を取得すると、営業所や現場に配置することを義務づけられている「監理技術者」や「主任技術者」を務めることができます。
1級は特定建設業の専任技術者・監理技術者、2級は一般建設業の専任技術者・主任技術者になることが可能です。 土木施工管理技士の受験資格は年齢制限のみで、学生でも受験できます。
試験はマークシート方式と記述式の学科試験で実施されます。 各種技術者になれる土木施工管理技士は、一定規模の営業所や建設現場で設置が必須な建設業界において、重要な資格と位置づけられています。需要の高い資格で、土木施工管理技士の資格取得者は転職市場でも引く手あまたです。
測量士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 測量士、測量士補 |
| 主な業務内容 | 土地の位置・形状の測量 |
| 受験資格 | 学歴、年齢、実務経験に関係なく受験可能 |
| 試験内容 | 学科試験(択一式、記述式) |
出典:試験及び登録に関するQ&A|国土交通省 国土地理院
出典:令和7年 測量士・測量士補試験 受験案内|国土交通省
国土地理院 測量士は土地の位置・形状の測量を行うのに必要な専門的な知識・スキルを有することを証明する国家資格です。 学歴や年齢、実務経験に関係なく誰でも受験できます。
択一式・記述式による学科試験が行われ、測量に関する幅広い分野の知識から出題されるのが特徴です。
測量士の試験に合格して登録すれば、専門家として測量作業に従事できます。土地の測量業務は測量士にのみ認められた独占業務のため、測量士の需要は高いです。
舗装施工管理技術者
| 資格の種類 | 民間資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 舗装工事の現場の管理・指導 |
| 受験資格 | 大学、短期大学、高等専門学校などの指定学科を卒業した者 土木施工管理技術検定や建設機械施工技術検定に合格した者 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 上記それぞれに応じて舗装施工管理の実務経験の必要年数の要件を満たす必要がある |
| 試験内容 | 学科試験(択一式、記述式) |
出典:1 級・2 級舗装施工管理技術者 資格試験のご案内|一般財団法人 日本道路建設業協会
舗装施工管理技術者(ほそうせこうかんりぎじゅつしゃ)は、舗装工事の専門的な知識を持ち、舗装工事の管理・指導ができる能力を認定する民間資格です。
1級と2級に分かれており、試験に合格して登録申請をすれば、舗装施工管理技術者を称することができます。 舗装工事は一般的な土木工事とは異なる独自の知識や施工経験が求められる分野です。
日本は全国的にインフラ設備の老朽化が進んでいて、修繕や再整備の必要性が高まっています。舗装工事の専門家として、舗装施工管理技術者はこれから需要の高い存在になるでしょう。
技術士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 技術士、技術士補 |
| 主な業務内容 | 科学技術に関する専門スキルを必要とする事項についての計画、設計、分析、指導など |
| 受験資格 | 年齢、学歴、実務経験による制限なし 第二次試験の受験のために所定の業務経験が必要 |
| 試験内容 | 学科試験(筆記試験、口頭試験) |
技術士は、特定の技術部門について高度な知識と応用能力を持つ技術者に与えられる国家資格です。
技術士は全部で12の技術部門があり、建設や上下水道、衛生工学など建設業界に関係する分野も含まれています。 技術士試験の受験には年齢や学歴、実務経験による制限はありません。
ただし、第一次試験を受験した後で所定の業務経験が求められます。 技術士の中でも建設部門は建設業界で需要が高いです。技術士の建設部門に合格すれば、官公庁への就職や建設コンサルタント、技術士としての独立などキャリアの幅が広がります。
RCCM
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 技術士、技術士補 |
| 主な業務内容 | 科学技術に関する専門スキルを必要とする事項についての計画、設計、分析、指導など |
| 受験資格 | 年齢、学歴、実務経験による制限なし 第二次試験の受験のために所定の業務経験が必要 |
| 試験内容 | 学科試験(筆記試験、口頭試験) |
RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)は土木工事で建設コンサルタント業務に携わる技術者が認定される民間資格です。RCCMの有資格者は土木工事の現場で、監理技術者や照査技術者として建設コンサルタント業務に携わることが期待されています。
所定の実務経験を有する者が受験でき、CBT形式による学科試験に合格しなければなりません。活動場所は主に建設コンサルタント会社やゼネコンなどです。
資格を取得すれば、建設コンサルタントとしてのスキルをアピールできるため、昇給・昇進や転職で有利に働きます。
地質調査技士
| 資格の種類 | 民間資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | ボーリング調査、地質計測、地質試験など |
| 受験資格 | 地質調査を目的とした調査業務および現場管理業務などで所定の実務経験を有する者 |
| 試験時期・頻度 | 年1回/例年7月頃 |
全国地質調査業協会連合 地質調査技士はボーリング調査や地質計測、地質試験などに従事できる専門性や技術を証明する民間資格です。
地質調査業務や現場管理業務などで所定の実務経験を有する者が受験できます。 試験は筆記試験と口頭試験で、地質調査やボーリング調査に関する専門的な知識を問われる内容です。
試験時期は例年7月頃となり、年に1回の頻度で試験が実施されます。 日本は自然災害が多いため、地盤調査を含む地質調査の重要性は高いです。地質調査の専門家として地質調査技士の需要は高く、取得すれば昇給や転職などで有利に働きます。
コンクリート診断士
| 資格の種類 | 民間資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | コンクリートや鋼材などの診断における計画や調査、評価、それらの管理・指導 |
| 受験資格 | 所定の資格または学歴を有して、コンクリート診断士講習を受講した者 |
| 試験内容 | 学科試験(四肢択一式、記述式) |
出典:コンクリート診断士試験のご案内|公益社団法人 日本コンクリート工学会
コンクリート診断士は、コンクリート構造物の維持や修繕のために診断や点検、評価などを行う専門家に与えられる民間資格です。所定の資格または学歴を有し、コンクリート診断士講習を受講した者が受験できます。
コンクリート診断士を取得すれば、建物の管理・調査や建設コンサルタント、ゼネコン、コンクリート製品製造などの企業で活躍できるでしょう。
コンクリート構造物の老朽化は全国的に進んでおり、コンクリートの診断や修繕などの需要は高まっています。企業だけではなく公的機関でも認められる資格で、活躍の場は幅広いといえます。
【電気系】建設業界で役立つ資格
建築物に電力を安全かつ効率的に供給するためには、電気設備の設計や施工、保守を担う専門人材が欠かせません。
そのため、電気系の資格は建設現場や設備工事の分野で高く評価され、需要も安定しています。
中でも、電気工事士や電気工事施工管理技士は、現場での実務に直結しやすく、取得することで業務の幅が広がるだけでなく、昇進や独立にもつながります。
ここでは、電気工事に関する資格について解説するので、電気工事業界への転職やキャリアアップを目指す方に必見です。
電気工事士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 第一種・第二種 |
| 主な業務内容 | 電気設備などの工事 |
| 受験資格 | 学歴や年齢、職歴を問わず誰でも受験できる |
| 試験内容 | 学科試験(四肢択一方式)、技能試験(配線図に従って施工する) |
出典:第一種電気工事士試験について|一般財団法人 電気技術者試験センター
出典:第二種電気工事士試験について|一般財団法人 電気技術者試験センター
電気工事士は、電気工事の高度な知識や技能を持った専門技術者に与えられる国家資格です。屋内配線設備や電気設備の設置などの工事は、電気工事士が従事しなければなりません。 電気工事士は第一種と第二種に分かれており、扱える電気設備の電圧に違いがあります。
第一種電気工事士の資格があれば、高電圧の電気設備の工事にも対応可能です。 電気工事士の資格試験は、学歴や年齢、職歴を問わず誰でも受験できます。ただし、第一種電気工事士は、技能試験の合格に加えて3年以上の実務経験がないと免状が交付されません。
電気工事士の資格があれば、ほとんどの電気工事に携われるため、幅広い活躍の場があります。建設業界でも電気工事士は多くの現場で必要とされており、転職でも有利です。
電気主任技術者
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 第一種・第二種 ・第三種 |
| 主な業務内容 | 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督 |
| 受験資格 | 誰でも受験可能 |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:電気主任技術者の資格概要|一般財団法人 電気技術者試験センター
電気主任技術者は電気工作物の工事や維持、運用に関する保安の監督ができる資格です。電気工作物の設置者は事業場毎に電気主任技術者を設置しなければなりません。
電気主任技術者は第一種から第三種まで3種類あり、取り扱える電圧に違いがあります。受験資格はなく、誰でも受験可能な資格です。
ただし、電気主任技術者の試験は合格率が低く、難易度は高いとされています。 電気設備のあるビルや工場、発電所などに設置を義務づけられているため、需要の高い技術者です。
電気工事施工管理技士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 電気工事の施工管理 |
| 受験資格 | 1級:試験実施年度に満19歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) 2級:試験実施年度に満17歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:1級 電気工事施工管理技術検定のご案内|一般財団法人 建設業振興基金
出典:2級 電気工事施工管理技術検定のご案内|一般財団法人
建設業振興基金 電気工事施工管理技士は、電気工事の施工管理を専門的に行える国家資格です。施工計画の作成や品質管理など電気工事の監督としての役割を求められます。
電気工事施工管理技士を取得すれば、特定建設業・一般建設業で設置が義務づけられる専任技術者や主任技術者などになることが可能です。
電気工事施工管理技士の受験資格は1級が満19歳以上の者、2級が満17歳以上の者となっています。ただし、第二次試験の受験には所定の業務経験が必要です。 建設業の許可基準に含まれているため、電気工事施工管理技士は需要があります。
また、経営事項審査において、電気工事施工管理技士は加点対象です。企業からの評価が高いため、電気工事の分野でキャリアアップを図りたい場合に、電気工事施工管理技士の取得は役立ちます。
電気通信工事施工管理技士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 電気通信工事の施工管理 |
| 受験資格 | 1級:試験実施年度に満19歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) 2級:試験実施年度に満17歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:1級電気通信工事施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:2級電気通信工事施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
電気通信工事施工管理技士は、電気通信工事の施工管理を行える国家資格です。1級と2級の2種類あり、担当できる工事の規模が異なります。
1級は満19歳以上の者、2級は満17歳以上の者が受験可能です。第二次検定の受験には所定の実務経験が求められます。試験内容は学科試験で、実地試験はありません。
電気通信工事業の営業所に設置が義務づけられている各種技術者になれるのが電気通信工事施工管理技士です。
また、経営事項審査制度において、電気通信工事施工管理技士の資格者は加点対象になります。 企業から高く評価される資格のため、昇給や昇進、転職で有利です。取得すれば、電気通信工事の現場で責任者として活躍できます。
消防設備士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 甲種・乙種 |
| 主な業務内容 | 消防用設備などの工事や整備、点検 |
| 受験資格 | 乙種:誰でも受験可能 甲種:特定の学科の卒業、所定の国家資格の所持、実務経験など |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:消防設備士試験|一般財団法人 消防試験研究センター
出典:受験資格|一般財団法人 消防試験研究センター
消防設備士は消防用設備の工事や整備、点検ができる国家資格です。甲種は工事・点検・整備を行えますが、乙種は点検・整備のみ可能です。乙種は誰でも受験可能な一方、甲種は学歴や実務経験などの要件を満たさないと受験できません。
消防設備士の仕事は独占業務で、有資格者のみが消防用設備の工事や点検などを行えます。消防法により消防用設備の設置が義務づけられているため、消防設備士の活躍の幅は広範囲にわたります。
消防設備士は、建設業界において幅広い企業から評価されており、取得していると転職で有利になる資格です。
【空調衛生系】建設業界で役立つ資格
空調衛生分野では、実務に直結する資格があります。ここでは、空調衛生の分野で、仕事に役立つ資格について紹介します。
管工事施工管理技士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 1級・2級 |
| 主な業務内容 | 管工事の施工管理 |
| 受験資格 | 1級:試験実施年度に満19歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) 2級:試験実施年度に満17歳以上の者(第二次検定は所定の実務経験が必要) |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:1級管工事施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:2級管工事施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
管工事施工管理技士は管工事の施工管理ができる国家資格です。1級と2級が設置されており、それぞれ対応できる工事規模が異なります。
第一次検定は受験資格が年齢制限のみで、所定の実務経験を積めば第二次検定の受験が可能です。 管工事施工管理技士は、建設業許可の取得に必要な専任技術者になれる資格です。
公共工事の入札時には、経営事項審査で管工事施工管理技士の資格者が在籍していると加点対象となります。 企業からの評価が高い資格であるため、取得していると転職の際に役立つでしょう。
【不動産系】建設業界で役立つ資格
建設業界で役立つ不動産系の資格は多数存在します。特に取得をおすすめする資格について詳しくみていきましょう。
宅地建物取引士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | 不動産取引時の重要事項の説明など |
| 受験資格 | 学歴や年齢に関係なく誰でも受験できる |
| 試験内容 | 学科試験(四肢択一式) |
宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営むために設置が義務づけられている国家資格です。日本国内に居住する方であれば誰でも受験できます。
学科試験のみで、50問の四肢択一式で出題されます。 宅地建物取引士を取得すると、不動産取引時に重要事項の説明や35条書面(重要事項書面)への記名などの業務を担えます。
宅地建物取引士にしかできない独占業務があり、不動産の売買や賃貸借の仲介などをするのに設置が義務づけられているため、需要が高い資格です。
宅地建物取引士は不動産業界だけではなく建設業界や金融業界など幅広い業界に活躍の場があります。企業によっては資格手当を支給する場合もあり、資格取得によるメリットは大きいです。
マンション管理士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | 管理組合の管理者やマンションの区分所有者などへの助言・指導 |
| 受験資格 | 年齢や学歴などの制限なし |
| 試験内容 | 学科試験 |
マンション管理士は、マンションの管理者や区分所有者などに助言や指導を行うときに必要な国家資格です。年齢や学歴などの制限なく受験できて、試験内容はマンション管理に関する学科試験です。
マンションの管理業務は、資格がなくても行えます。しかし、マンションの維持管理はトラブルが起きやすく、難しい判断が求められる場面が多いです。
マンション管理士がマンションの管理についてのコンサルティングを行い、管理組合の運営をサポートします。 マンションの維持管理に関連した仕事であれば、マンション管理士の資格は有利になるでしょう。
土地家屋調査士
| 資格の種類 | 国家資格 |
|---|---|
| 等級 | 等級なし |
| 主な業務内容 | 不動産の表示に関する登記申請の代理、土地や家屋の調査測量など |
| 受験資格 | 学歴や実務経験などの制限なく誰でも受験できる |
| 試験内容 | 学科試験 |
出典:土地家屋調査士を目指す方へ|日本土地家屋調査士会連合会
出典:土地家屋調査士とは|東京土地家屋調査士会
土地家屋調査士は不動産の登記に必要な土地・家屋の調査測量を行い、不動産の表示に関する登記申請手続きの代理を行える国家資格です。年齢や学歴、実務経験などの制限はなく、誰でも受験できます。
不動産の表示に関する土地・家屋の調査測量や、登記申請手続きの代理などは土地家屋調査士の独占業務です。
土地家屋調査士にしかできない業務があるため、需要の高い資格です。建物を扱う多くの企業で土地家屋調査士は評価されており、転職でも有利に働きます。
建設業界の資格を取得するメリット
建設業界では、資格を取得することで知識やスキルを証明でき、仕事の幅が広がります。昇進や転職に有利になるほか、責任あるポジションを任される機会も増えるでしょう。
業務の幅が広がる
独占業務のある国家資格を取得すると業務の幅が広がります。建築士や測量士などの資格は、その資格を持つ者しかできない「業務独占資格」です。
また、特定の工事の要件として資格保有者の配置が求められているケースがあります。建設現場では、施工管理技士の資格保有者を、現場の責任者として必ず配置しなければなりません。
資格を取得することで、有資格者にしか任されない業務を担当できるようになり、仕事の幅を広げられます。建築士や測量士、施工管理技士といった資格を取得すれば、現場に欠かせない人材になれるでしょう。
キャリアアップにつながる
建設業界では、資格の取得がキャリアアップに直結します。たとえば施工管理技士や建築士などの国家資格を取得すると、現場管理や設計監理などの責任ある業務を任されるようになり、昇進や年収アップも期待できます。
また、資格を持つことで業務の幅が広がり、実務経験の蓄積にもつながります。今後どのようなポジションを目指すのかを見据え、必要な資格を戦略的に選ぶことが重要です。
プロジェクト全体を統括するリーダーを目指すなら、まずは2級施工管理技士から取得し、実務経験を積みながら1級を目指すと良いでしょう。資格と経験を重ねることが、将来の選択肢を広げる鍵となります。
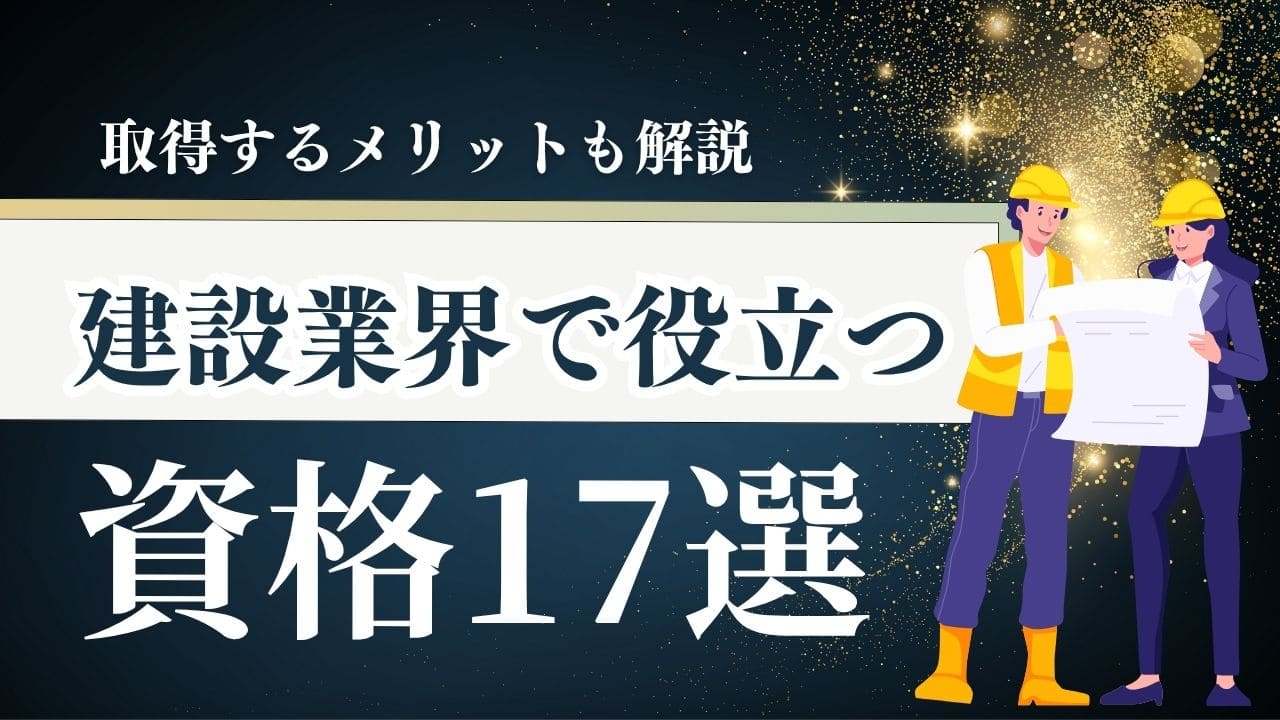

_180x98.png)
_180x98.png)
_180x98.png)
 (1)_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


