建設業界では、工事の請負金額や工事の規模に応じて、「監理技術者」または「主任技術者」の配置が義務付けられています。資格の有無や実務経験年数、工事現場の規模や内容に応じて、適切な技術者が選任され、施工管理を担当します。
建設業界で働く中で、「監理技術者と主任技術者の違いがわからない」「監理技術者や主任技術者になるには、どのような資格や経験が必要なのか知りたい」と考えている方も多いでしょう。
そこで本記事では、監理技術者と主任技術者の違いや、それぞれの役割、資格取得の要件について詳しく解説します。また、関連する資格やよくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてください。 監理技術者や主任技術者の役割を理解し、自身のステップアップに生かしましょう。
監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者は、どちらも建設工事の現場に配置される技術者ですが、担当する役割や求められる条件に違いがあります。
主任技術者は、すべての建設現場に配置が必要とされる技術者であり、発注者との契約形態や請負金額にかかわらず必要となります。建築、土木、電気など工種を問わず、一定の技術的知見と実務経験が求められます。
一方の監理技術者は、発注者から直接工事を受注した現場のうち、請負金額が5,000万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)の大規模な工事に限り配置が義務づけられています。主任技術者としての実務経験を積んだうえで、指定の国家資格や講習の修了が求められます。
それぞれの技術者の配置要件を以下に整理します。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 主任技術者の要件 | ・該当する工種の1級または2級の国家資格を取得していること ・一定期間以上の実務経験を有していること |
| 監理技術者の要件 | ・該当する工種の1級国家資格を取得していること ・一定期間以上の実務経験を有していること |
また、監理技術者が配置される場合、その現場には主任技術者を配置する必要はありません。このように、監理技術者は主任技術者よりも大規模な現場を担当し、必要な資格や経験の要件も厳しく、より責任の重い役割を担います。
出典:【通知】建設業法改正等による各種制度の改正について | 会津若松市
監理技術者と主任技術者の担当できる工事規模の違い
監理技術者と主任技術者では、担当できる工事規模に違いがあり、その規模は工事の請負金額によって判断されます。
請負金額が5,000万円以上の場合は監理技術者、5,000万円未満の場合は主任技術者を配置するのが基本です。この区分が、監理技術者と主任技術者の大きな違いの一つです。
ここでは、監理技術者と主任技術者の担当できる工事規模について詳しく解説します。
監理技術者は請負金額5,000万円以上
監理技術者は、発注者から直接請け負った工事(いわゆる元請契約)において、特定の要件を満たす場合に配置が義務づけられます。
-
建設工事全般:発注者から直接請け負った工事で、協力会社など他社に発注する金額の合計が5,000万円以上(税込)の場合
-
建築一式工事:同様の条件で、金額の基準は8,000万円以上(税込)
建築一式工事とは、複数の専門工事を総合的に管理しながら進める工事であり、一般的に大規模な元請工事として実施されます。また、工事期間中に変更が生じて請負金額が5,000万円を超えた場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者は工事規模5,000万円未満
主任技術者は、比較的小規模から中規模の工事現場を対象として配置が義務づけられる技術者です。監理技術者が不要な現場であっても、主任技術者は必ず配置されます。
-
発注者から直接請け負った工事において、他社への発注金額が5,000万円未満(税込)の場合
-
建築一式工事では、8,000万円未満(税込)の場合
-
他社から請け負った工事では、金額にかかわらず主任技術者の配置が必要
-
さらに、請負金額が500万円未満の工事であっても、建設業許可を受けている事業者であれば、主任技術者の配置が義務づけられる
つまり、工事規模や契約形態にかかわらず、建設業許可を持つ事業者が行う工事には、原則として主任技術者の配置が求められるのです。
キャリアアップを目指す方へ
プロのキャリアアドバイザーに相談してみませんか?
サイトに公開されていない非公開求人のご相談も行っています。
監理技術者と主任技術者の役割の違い
監理技術者と主任技術者は、いずれも工事現場に配置される重要な技術者ですが、その担う役割には明確な違いがあります。
主任技術者は、現場に常駐し、自社が担当する工事範囲の施工管理を直接行う技術者です。一方、監理技術者は、主任技術者の業務に加え、関係各社との連携・統括を含む工事全体のマネジメントを担います。
ここでは、それぞれの職務内容を比較し、違いを明確に解説します。
監理技術者の役割(工事全体の統括・マネジメント)
監理技術者は、施工計画の立案から工程・品質・安全の全体管理まで、現場全体を統括する役割を担います。複数の関係者と連携しながら、技術的な調整やマネジメント業務を広く担当します。
| 業務項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工計画の作成・実行・修正 | ・工事全体の施工計画書を作成 ・関係各社から提出された施工要領書を確認 ・変更時には計画を修正 |
| 工程管理 | ・現場全体の進捗を把握し、関係業者間のスケジュールを調整 |
| 品質管理 | ・必要に応じて施工の立ち会い確認を実施し、品質を確保 |
| 安全管理 | ・安全計画を立て、関係者への教育・指導を実施 |
| 技術的指導 | ・各社の主任技術者と連携し、技術的な統括・調整を行う |
主任技術者の役割(自社担当範囲の直接管理)
主任技術者は、自社が担当する工事範囲において、現場での施工管理を直接実施します。施工計画の実行や安全・品質管理、作業員への技術指導など、実務に即した管理を行う役割です。
| 業務項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工計画の作成・実行・修正 | ・全体の施工計画に基づき、自社の工事範囲について施工要領書を作成 ・指示に応じて修正対応 |
| 工程管理 | ・自社の工事範囲の進捗を管理 ・工程会議などへの参加 |
| 品質管理 | ・自社の施工範囲を確認し、必要に応じて報告 |
| 安全管理 | ・自社の作業エリアにおける安全対策を計画・実行し、報告 |
| 技術的指導 | ・自社作業員への技術的指導を実施 |
【資格一覧表】監理技術者と主任技術者の資格要件の違い
監理技術者や主任技術者として現場に配置されるためには、それぞれ特定の要件を満たす必要があります。主任技術者になるには、一定期間以上の実務経験または国家資格の取得が求められます。
一方、監理技術者になるためには、より高度な国家資格と実務経験が必要です。
ここでは、監理技術者と主任技術者に求められる資格要件の違いを詳しく解説します。
監理技術者は1級施工管理技士などの国家資格
監理技術者には、「1級施工管理技士」「1級建築士」「技術士」など、上位の国家資格を取得しておかなければなりません。
ただし、監理技術者の資格要件は、建設業全29業種のうち「指定建設業」に該当する7業種と、それ以外の22業種で異なります。
指定建設業に該当する7業種では、以下のいずれかの国家資格を取得していることが要件とされています。
- 1級施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士
また、指定建設業以外の22業種では、以下のいずれかの実務経験があれば要件を満たすことができます。
- 大学の指定学科を修了し、3年以上の実務経験がある
- 高等専門学校の指定学科を修了し、5年以上の実務経験がある
- 指定学科を修了していないが、10年以上の実務経験がある
なお、「指定学科」は建設業の業種ごとに定められています。
出典:監理技術者の資格要件|一般財団法人 建設業技術者センター
出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
主任技術者は2級施工管理技士などの国家資格
主任技術者には、1級もしくは2級施工管理技士などの国家資格や一定の実務経験が必要です。以下のいずれかの条件を満たすことが、主任技術者としての要件となります。
① 国家資格を有する場合
主任技術者としての要件を満たす資格の例は以下の通りです。
- 1・2級施工管理技士
- 1・2級建築士
- 技術士
たとえば、2級電気工事施工管理技士の資格があれば、電気工事業で請け負った工事の主任技術者になれます。
② 学歴・実務経験による場合
主任技術者になるためには、以下のいずれかの学歴と実務経験を満たす必要があります。
- 大学の指定学科を修了し、3年以上の実務経験がある
- 高等専門学校の指定学科を修了し、5年以上の実務経験がある
- 指定学科を修了していないが、10年以上の実務経験がある
- 複数の業種を経験し特定の業種で一定の実務経験がある
監理技術者と主任技術者の専任・兼任の違い
請負金額が一定以上の場合、監理技術者および主任技術者は、原則として担当する工事現場に専任で配置しなければなりません。
ただし、特定の条件を満たす場合に限り、複数現場を兼任することが認められています。
ここでは、監理技術者と主任技術者それぞれについて、専任が義務付けられるケースと兼任が認められるケースを整理して解説します。
監理技術者
監理技術者は、請負金額が1億円以上(建築一式工事では2億円以上)の工事において、原則として現場に専任で配置されます。
ただし、一定の条件を満たし、監理技術者補佐を専任で配置できる場合には、監理技術者自身が最大2件まで現場を兼任することが認められています。
監理技術者補佐となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
監理技術者の要件を満たしていること主任技術者の要件を満たし、1級の技術検定に合格していること
この特例が適用され、兼任が認められた監理技術者は、「特例監理技術者」と呼ばれます。
さらに、請負金額が1億円未満(建築一式工事では2億円未満)の工事であれば、以下の条件をすべて満たすことで、監理技術者の兼任が認められます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 工期の重複 | 複数の請負契約の契約工期が重複していること |
| ② 工事の一体性 | 工事対象(工作物等)に一体性または連続性があること ※または施工にあたり相互に調整を要する工事であること |
| ③ 契約形態 | 当初契約外の工事が随意契約により締結されていること |
| ④ 発注者の判断 | 安全・品質確保の観点から、発注者が兼任を適切と判断していること |
| ⑤ 現場の近接性 | 現場間の距離がおおむね10km以内であること(目安) |
※請負金額1億円未満の場合
出典:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例|佐賀県
出典:二以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合|国土交通省
主任技術者
主任技術者は、小規模な工事において、一定の条件を満たせば複数現場の兼任が認められます。主な条件は次のとおりです。
-
10km程度以内の近接した工事現場であること
-
施工に際して、相互に調整が必要な関係性があること
(例:複数現場で資材を一括調達して調整しながら進行するケース)
また、請負金額が一定規模以下の工事では、より詳細な要件を満たすことで兼任が可能です。
-
請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること
-
兼任する現場数が2件以下であること
-
1日で巡回可能で、移動時間が概ね2時間以内であること
-
関係する協力会社の施工体制が複雑化していないこと(例:工事に関与する会社階層が限定的であること)
-
現場ごとに連絡員を配置していること
-
情報通信技術(ICT)を活用した連絡体制が整備されていること
-
人員配置に関する報告書を作成・保存していること
-
現場に情報通信機器を設置していること
| 項目 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 役割 | 工事全体の管理、関係者への指導・調整 | 自社の工事全体を直接管理 |
| 資格 | 1級施工管理技士、建築士など | 一定の実務経験、複数業種での実務経験、または国家資格 |
| 工事規模 | 5,000万円以上(建築一式工事:8,000万円以上) | 5,000万円未満(建築一式工事:8,000万円未満) |
| 専任/兼任 | 原則専任、特例で最大2件まで兼任可 | 原則専任、小規模工事で条件付き兼任可 |
出典:建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和7年2月 改訂)|国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課
監理技術者は主任技術者になれる?
監理技術者は、主任技術者よりも上位の立場にあたるため、監理技術者の要件を満たしていれば、主任技術者としても従事することができます。
監理技術者の資格要件には、主任技術者に求められる条件も含まれており、資格面で主任技術者を兼ねることが可能です。
-
✓ 監理技術者には1級施工管理技士などの国家資格が必須
-
✓ 主任技術者は、1級または2級の国家資格、または一定の学歴・実務経験で要件を満たせる
また、指定建設業以外の22業種では、国家資格がなくても、所定の学歴や実務経験を満たせば監理技術者として従事することが可能です。この場合、必要な要件は主任技術者と同様です。
以上のように、監理技術者の資格要件は主任技術者よりも広範かつ高度であるため、監理技術者は主任技術者としても従事できることになります。
監理技術者と主任技術者のキャリアパス
ここでは、監理技術者や主任技術者になるための具体的なステップと、キャリアアップの道筋について解説します。
目標に応じて必要な資格や経験を積み重ね、着実に昇格を目指していきましょう。
監理技術者になるには
監理技術者になるためには、以下の要件を満たし、「監理技術者資格者証」の申請を行う必要があります。
| 対象業種 | 要件 |
|---|---|
| 指定建設業7業種の場合 | 1級の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士など)を取得していること |
| 指定建設業以外の22業種の場合 | 一定以上の実務経験を有していること |
申請に問題がなければ、監理技術者資格者証が交付されます。ただし、資格者証を持っているだけでは、現場に配置されることはできません。
監理技術者として業務を行うためには、「監理技術者講習」を受講し、修了証を取得することが必要です。現場に配置されるためには、講習の受講と修了証の取得を完了し、正式な配置要件を満たしておく必要があります。
主任技術者になるには?
主任技術者になるには、主に以下の2つの方法があります。
- 実務経験を積む方法
- 国家資格を取得する方法
どちらのルートを選んでも、主任技術者として働くことができるため、自身に合った取得方法を事前に確認しておきましょう。
なお、主任技術者には「資格者証の交付」や「講習制度」がないため、実務経験証明書または国家資格の資格証によって、要件を証明する必要があります。
実務経験を積む
主任技術者を目指す方法として、該当する業種で必要な実務経験を積むことが挙げられます。この場合、必要な実務経験年数は、最終学歴によって異なります。
- 大学(短大含む)の指定学科を卒業:3年以上
- 高等専門学校の指定学科を卒業:3年以上
- 高等学校の指定学科を卒業:5年以上
- そのほかの学歴:10年以上
各建設業種ごとに「指定学科」が定められているため、自身の学歴が該当するかを確認しましょう。
国家資格を取得する
主任技術者として認められるためには、国家資格の取得が有効な手段のひとつです。 主任技術者の要件を満たす国家資格には、以下のようなものがあります。
- 各業種における2級以上の施工管理技士
- 各業種における技術士
- 各業種における技能検定
- 2級以上の建築士
ただし、一部の国家資格には受験資格として年齢や実務経験が求められるものもあるため、事前に確認しておきましょう。
キャリアアップするには?
監理技術者や主任技術者などの現場配置技術者としてキャリアアップするには、以下のステップが考えられます。
- より大規模な工事を担当する
- 複数の現場を統括する立場になる
- 技術士やRCCM(シビルコンサルティングマネージャー)などの資格を取得し、専門性をより高める
主任技術者は、さらなる資格取得によって監理技術者へのステップアップを目指すことができます。
また、専門分野を深く掘り下げ、特定の技術に精通することで、プロジェクトの中核を担う技術者として活躍の幅を広げられるでしょう。
監理技術者と主任技術者の関連資格
ここでは、監理技術者や主任技術者に関連する代表的な資格を6つ紹介します。これらの資格は、現場への配置要件を満たすだけでなく、各分野の知識を深め、技術力の向上にも役立ちます。
さらに、資格取得により、社内評価や業界内でのキャリアアップにもつながるでしょう。
施工管理技士
現場管理において重要な国家資格が、施工管理技士です。
施工管理技士は、以下の7分野に区分され、それぞれ1級と2級の2段階に分かれています。
- 土木
- 建築
- 管工事
- 電気工事
- 造園
- 建設機械施工
- 電気通信工事
7つの分野の中でも、建築施工管理技士は特に取得が難しい資格の一つです。建築工事では、管工事や電気工事など他分野の知識も必要となるため、試験範囲が広く、総合的な知識が求められます。
また、どの分野でも1級の方が2級より難易度が高く、その分、任される業務範囲も広い点が大きな特徴です。1級を取得すれば、より高度で大規模な工事に携わることが可能になります。
施工管理技士の資格には、実務経験や年齢に関する要件が設けられていますが、学歴や保有資格によっては、一部の要件が免除される場合もあります。
RCCM(シビルコンサルタント)
RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)とは、土木分野における高度な技術力とマネジメント能力を有することを認定する資格です。一般社団法人「建設コンサルタンツ協会」が実施している民間資格です。 RCCMには22の分野があり、代表的なものとして以下が挙げられます。
- 港湾及び空港
- 電力土木
- 上水道及び工業用水道
- 都市計画及び地方計画
- 建設情報
RCCMを取得すれば、公共工事の設計や施工管理をはじめ、幅広い分野で活躍することができます。
特に、監理技術者として専門性を高めたい方や、建設業界でコンサルタント業務に携わりたい方にとって、大きな強みとなるでしょう。
また、建設・土木業界内で新たな分野へキャリアチェンジを目指す場合にも、RCCM資格は有利に働きます。
出典:RCCM資格ホームページ|一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 RCCM資格制度事務局
その他関連資格
施工管理技士やRCCM以外にも、建設業界でキャリアアップを目指す際に取得を検討したい資格は多数あります。
これらの資格は、監理技術者や主任技術者を目指す方はもちろん、建設業界で専門性を高めたい方にもおすすめです。
| 資格名 | 概要 |
|---|---|
| 技術士 | 科学技術に関する高度な専門応用能力を有することを国が認定する国家資格 |
| コンクリート診断士 | コンクリート構造物の劣化状況の調査、診断および補修方法選定等の業務を行うための資格 |
| 建築設備士 | 建築物の設備について、設計、工事監理、維持管理等の業務を行うための国家資格 |
| 土木施工管理技術検定 | 土木施工の技術に関する知識・技能について、一定水準以上の能力を有する者を認定する検定 |
主任技術者・監理技術者以外にも覚えておきたい職種
監理技術者や主任技術者は、「現場配置技術者」として施工現場に欠かせない存在です。しかし、建設業界にはこれらに似た名称を持ちながら、役割や配置場所が異なる職種も存在します。
ここでは、建設業界で必要とされる代表的な4つの職種を紹介します。それぞれの役割や要件を理解しておきましょう。
専任技術者
専任技術者は、建設業許可を取得・維持するため、営業所ごとに設置が義務付けられている職種です。工事現場ではなく、営業所や本支店などに常勤し、請負契約の締結や技術面でのサポートを担当します。
専任技術者となるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 該当する業種の国家資格を持っていること
- 指定学科を修了し、一定以上の実務経験があること
- 10年以上の実務経験があること
出典:許可の要件|国土交通省
現場代理人
現場代理人は、請負工事において、営業所の代表者に代わり、現場での責任を担う技術者です。作業員の指揮や発注者との連絡調整を行い、現場管理の中心的な役割を果たします。
現場代理人の配置は法的義務ではなく、資格要件も設けられていません。なお、主任技術者や監理技術者が現場代理人を兼任するケースも一般的です。
現場所長
現場所長は、施工現場の最高責任者を務める職種です。通常は現場代理人や主任技術者、監理技術者が兼務することが多いですが、大規模工事ではそれぞれの役割を分担して配置する場合もあります。
明確な資格要件はありませんが、高度な現場管理能力と豊富な経験が求められます。
工事主任
工事主任は、現場管理を担うメンバーのリーダー的存在です。資格要件は特にありませんが、一般的に現場経験が豊富な人材が選任されます。
ただし、現場代理人や現場所長のような法的な責任者ではなく、指揮命令権も持ちません。
監理技術者や主任技術者のように配置が義務付けられているわけではなく、他職種と兼務しながら工事主任の業務を担当するケースが多いです。
主任技術者と監理技術者に関連するよくある質問
監理技術者および主任技術者は、建設業における現場配置技術者であり、建設工事の適正な施工を確保するために重要な役割を担います。
これらの職種については、名称や役割が類似していることから、違いを理解しにくい場合があります。
ここでは、主任技術者と監理技術者に関連するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。気になる項目があればぜひチェックして疑問や不安を解消しましょう。
主任技術者と監理技術者の違いは何ですか?
両者とも建設工事現場に配置される技術者ですが、配置される工事の規模や資格要件に違いがあります。主任技術者は、工事の請負金額や契約形態を問わず、建設業許可を有する事業者が現場に配置すべき技術者です。
一方、監理技術者は、直接工事を請け負った契約において、一定金額を超える場合に配置が求められます。監理技術者は主任技術者よりも上位の資格(例:1級施工管理技士など)を有することが条件となります。
監理技術者と主任技術者を兼ねることはできますか?
資格要件を満たしていれば、同一人物が主任技術者の役割を担うことは可能です。
ただし、両者とも原則として専任配置が義務づけられており、通常は同時に複数の役割を兼ねることはできません(一部例外を除く)。
また、1つの現場には1名の技術者(監理技術者または主任技術者)が配置されることとされています。
出典:主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関する取扱いについて|藤枝市
主任技術者および監理技術者の専任配置が必要とされる要件が4,500万円になるのはいつから?
2025年2月1日から、主任技術者もしくは監理技術者の専任配置要件が、請負金額4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)に変更されました。
公共・民間の区別元請・下請けの違いに関係なく適用されます。ただし、対象となるのは、公共性のある建物や、多数の人が利用する施設などに限定されます。 そのため、個人の住宅に関する工事などは対象外です。
出典:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します|国土交通省
出典:建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和7.2版)|国土交通省
主任技術者の配置が不要になる工事とは?
一部の特定専門工事に限り、特定の条件を満たす場合に限り主任技術者の配置が不要となることがあります。
例としては、鉄筋工事・型枠工事などが該当しますが、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
✓ 技術者の配置が免除されることについて、上位契約者と書面で合意している
-
✓ 合意された技術者が工事全体を適切に管理できる体制が確保されている
-
✓ さらに下位の企業に再発注を行わない(多重構造にならない)こと
監理技術者や主任技術者の違いを把握し資格を取得してキャリアアップを目指そう
監理技術者と主任技術者は、建設業界における重要なポジションです。監理技術者あるいは、主任技術者になることで、各分野の責任ある役割を担い、自身のキャリアアップや年収アップにもつながるでしょう。これらの職種を目指すには、専門分野の資格取得と十分な実務経験が不可欠です。着実にスキルを磨き、将来的には建設現場において希少価値の高い人材となることを目指しましょう。
建設業界に特化した転職支援サービスを提供する「ベスキャリ建設」では、施工管理技士をはじめとする現場技術者を目指す方に向けた求人を多数ご紹介いたします。
未経験から建設業界に挑戦する方や、転職やキャリアに関する不安を抱えている方は、ぜひ「ベスキャリ建設」のキャリアアドバイザーにご相談ください。
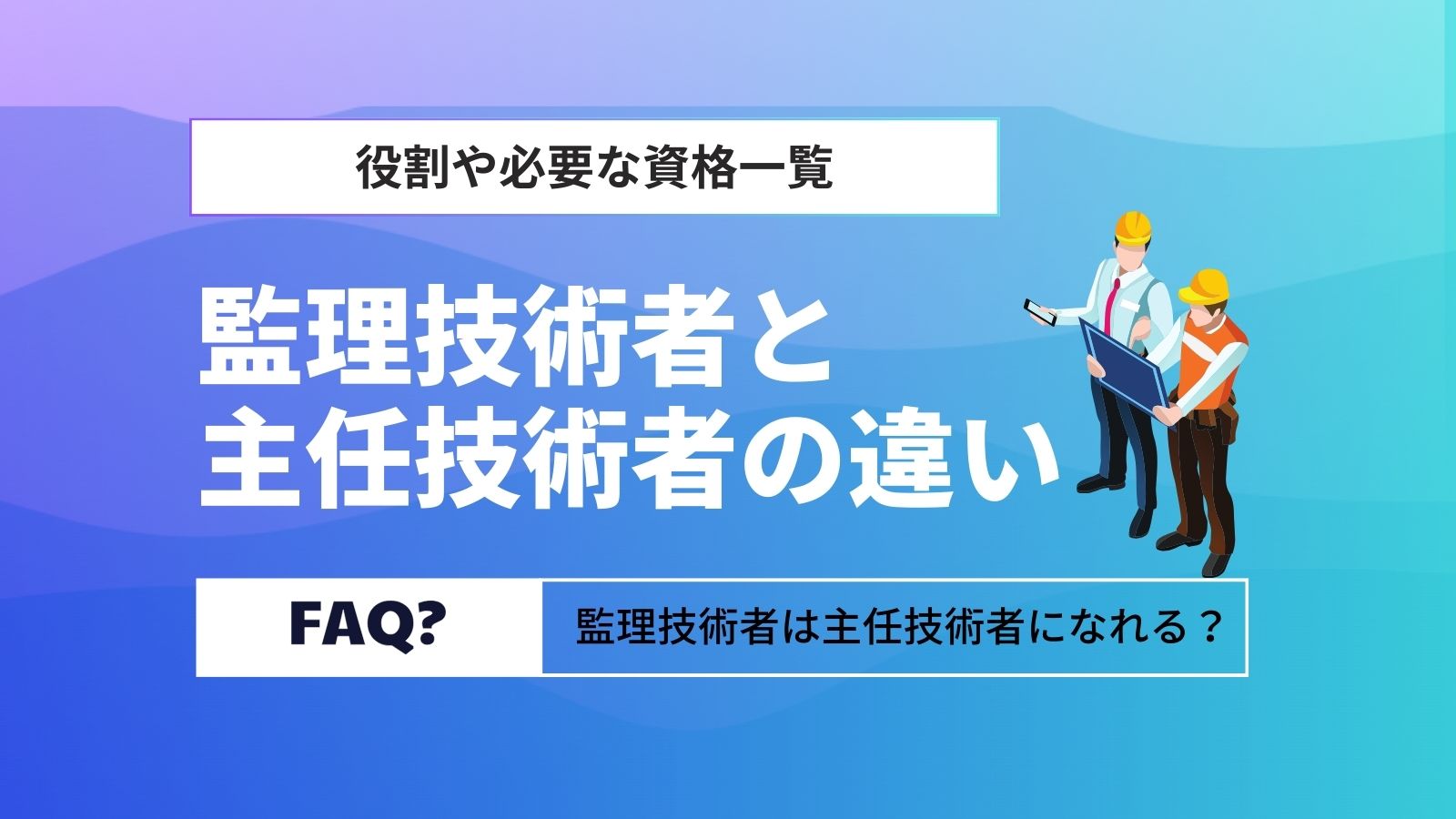


_180x98.png)
_180x98.png)
_180x98.png)
 (1)_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


