建設業界で働く中で、「この先も需要はあるのだろうか」「将来が不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
人手不足や資材価格の高騰など、建設業界が抱える課題を目の当たりにすると、今後の見通しが気になるのも無理はありません。
転職やキャリアの方向性を考えるうえでは、建設業界の需要動向や将来性を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、国の統計データや業界情報をもとに、2024年から2025年にかけての需要の見通しや、今後10年で予想される変化について詳しく解説します。これからのキャリアを見据える材料として、ぜひ最後までご覧ください。
あなたに合った職場や働き方を建設業界に詳しいアドバイザーがご提案します。
\ 無料で相談してみる /
【2026年】建設業界の需要は?現状を把握する
建設業界の現状を知るためには、直近の状況を振り返ることが重要です。
ここでは、建設投資の具体的な動き、人材市場の状況、そして建設資材の価格が業界に与える影響について詳しく解説します。
出典:建設経済モデルによる建設投資の見通し(2025年4月)
建設投資額の推移
建設業界への投資額は、長期的な視点で見ると着実に回復傾向にあります。1992年度に約84兆円でピークを迎えた後、一時は減少しましたが、2010年度の約41兆円で底を打ち、以降は増加に転じています。
回復の主な要因は、東日本大震災からの継続的な復興需要に加え、高度経済成長期に整備された社会インフラの老朽化が進み、大規模な改修や更新が必要な時期に差し掛かっていることです。
建設経済研究所が2024年1月に発表した予測によると、2024年度の建設投資額は73兆円で、前年度比2.7%の増加が見込まれています。
政府投資・民間投資の両方で増加が続いており、特に民間企業の設備投資意欲の高まりを背景に、工場や倉庫の建設が堅調に推移すると予測されています。
また、2015年度以降は建設投資が緩やかに増加し続けており、コロナ禍による影響も限定的でした。こうした背景から、建設業界全体としては安定した需要が続いているといえるでしょう。
2026年の人材需要
2026年の建設業界では、建設投資額が引き続き高水準で推移する一方で、深刻な人手不足が大きな課題となっています。なかでも、専門的な技術を持つ技能労働者の不足は顕著で、早急な対策が求められています。
建設業に従事する就業者数は、1997年の約685万人をピークに減少傾向が続き、2022年には約479万人まで落ち込みました。
特に就業者の高齢化が進行しており、建設技能者のうち約25.7%が60歳以上を占める一方で、29歳以下の若年層は11.7%にとどまっています。
今後10年間で多くのベテラン技能者が退職を迎える中で、若年層の入職数は十分とはいえず、人材の構造的なギャップが広がる懸念があります。
若手人材の不足は、熟練技術の継承を困難にし、業界全体の生産性低下や工事品質への影響を及ぼす可能性もあるのです。
したがって、若年層の入職促進と定着支援、多様な人材の確保・育成、技術継承の仕組みづくりが急務となっています。
出典:建設業における人材確保に向けた取り組みについて|国土交通省 北陸地方整備局
建設資材の価格高騰の影響
建設業界は現在、建設資材の価格高騰という深刻な課題に直面しています。その背景には、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や、継続的な円安の進行に伴う原材料費・エネルギーコストの世界的な上昇があります。
特に、セメント・生コンクリート・鋼材といった主要資材の価格上昇が顕著です。 2021年後半以降、多くの資材で価格上昇の傾向が見られ、企業の収益を圧迫しています。
こうした動向は、国土交通省が公表している「建設資材価格指数」からも明らかです。
この状況を受けて、国土交通省は公共工事における契約金額の変更について、「スライド条項(公共工事標準請負契約約款第26条)」の適切な運用を各発注機関に要請しています。
建設業者には、人件費や資材費の上昇分を適正に反映させた工事費見積もりの提出が求められていますが、実際にはコスト増加を価格に十分転嫁できていない事例も多く見られます。
そのため、今後は適正な価格転嫁を進めることが一層重要な経営課題となるでしょう。
【2026年】建設業界の需要はどうなる?
2024年の状況を踏まえ、2025年、2026年の建設業界の需要動向を予測します。
公共工事の安定性、新築住宅市場の今後の動き、そして成長が期待されるリフォーム市場の具体的な見通しについて、最新のデータを基にわかりやすく解説します。
公共工事は堅調に推移
2025年度の建設業界において、公共工事は引き続き堅調な需要が見込まれ、建設投資全体を下支えする重要な役割を担っています。
建設経済研究所の2024年1月時点の予測によれば、2025年度の建設投資額全体は74兆9,300億円で、そのうち政府投資は26兆3,900億円となる見通しです。
特に、国土強靭化計画に基づく防災・減災対策や、老朽化した社会インフラの維持更新事業が継続的に実施されることが予想されます。
具体的に大きな予算が割り当てられる分野には、以下のようなものが挙げられます。
-
✔ 2024年に発生した能登半島地震のような大規模災害からの復旧・復興事業
-
✔ 全国各地での河川改修、道路・橋梁の耐震化
-
✔ 上下水道施設の更新
国民の安全・安心な生活を守るためのインフラ整備は喫緊の課題で、必要な予算が確保されていることから、2025年の公共工事は高い水準を維持するでしょう。
出典:建設経済モデルによる建設投資の見通し|一般財団法人 建設経済研究所
出典:令和7年度予算概要|国土交通省
出典:公共事業費6兆円維持し防災新事業、25年度政府予算案を読み解く|日経XTECH
新築住宅は微増
2025年の新築住宅市場は、実際に建てられる住宅の数ベースでは横ばいから微減との見込みです。しかし、資材価格の上昇などの影響により、投資額ベースでは微増すると予測されています。
2025年度の民間住宅投資額は17兆6,800億円となり、前年度と比較して0.2%の微増、というのが、建設経済研究所の予測です。
一方で、住宅着工戸数については、資材価格の高騰や人件費の上昇による住宅価格の高止まり、金利上昇への懸念などから、自己資金で購入する持ち家を中心に慎重な動きが続くと考えられています。
政府は「子育てグリーン住宅支援事業」のような補助金制度を通じて住宅取得を後押ししています。しかし、建築コストの上昇が消費者の購買意欲に一定の影響を与えている状況です。
出典:建設経済モデルによる建設投資の見通し|一般財団法人 建設経済研究所
建築補修・改装工事の増加
建築補修や改装工事の市場、いわゆるリフォーム・リニューアル市場は、2025年にかけても増加傾向が続くと予測されています。
建設業界にとって、安定した収益源として大きな期待が寄せられています。 主な理由としては、既存の建物を有効に活用し長持ちさせようという意識の高まりや、地球環境への配慮から省エネルギー化を進める動き、そして高齢化社会に対応するためのバリアフリー化といった社会的なニーズがますます大きくなっているためです。
2025年度の民間非住宅建設投資のうち「建築補修投資」は、12兆5,600億円とわずかな減少が見込まれるものの、住宅リフォーム市場自体は堅調に推移すると見られています。
具体例として、住宅分野では「住宅省エネ2025キャンペーン」のような国の政策的後押しもあり、断熱改修や高効率給湯器への交換といった省エネリフォームの需要が大きく伸びています。
また、オフィスビルや商業施設、工場などでは、老朽化した設備の更新などのニーズも増加中です。また、改修工事には、働き方の変化に対応したレイアウト変更や、BCP対策として不可欠な耐震改修なども含まれているため、増加傾向にあります。
出典:建築物リフォーム・リニューアル調査報告|国土交通省
出典:建設経済モデルによる建設投資の見通し|一般財団法人 建設経済研究所
建設業界の今後の見通し
建設業界は、今後どのように変化し、働き方はどうなっていくのでしょうか。
ここでは、深刻な人手不足の解消に向けた生産性向上の具体的な取り組みや、国を挙げて進められている働き方改革が、建設業界にどのような変革をもたらすのかを詳しく解説します。
人手不足解消に向けた生産性の向上の動向
建設業界が抱える深刻な人手不足問題を解消するため、ICTの積極的な活用による生産性向上が進められています。
国土交通省が中心となって推進するi-Constructionは、測量から設計、施工、検査、そして完成後の維持管理に至る全ての事業プロセスにおいてICTを全面的に導入しています。
-
✔ ドローンを用いた高精度な3次元測量
-
✔ BIM/CIMの導入による設計・施工プロセスの全体最適化と効率化
-
✔ コンピューター制御された建設機械
-
✔ 現場に行かなくてもリアルタイムで施工状況を確認できる遠隔臨場システム
ICT技術の導入により、作業時間の大幅な短縮、施工精度の向上、作業員の安全確保といった効果が期待されています。 また、現場を支える技術者の配置に関する制度の柔軟化も進んでいます。
2023年1月から国の制度が見直され、これまで原則として1つの工事現場に専任で配置されなければならなかった主任技術者および監理技術者が、一定の条件を満たせば複数の現場を兼任できるようになりました。
働き方改革による変容
建設業界においても、長時間労働の是正や多様な働き方の実現を目指す「働き方改革」が本格的に進展し、労働環境は大きく変わろうとしています。
その中でも特に象徴的な変化が、2024年4月から建設業にも罰則付きで適用が開始された時間外労働の上限規制です。
原則として建設業界の時間外労働は月45時間・年360時間が上限となり、災害時等の復旧・復興事業といった特別な事情がある場合でも、以下のような上限が設けられました。
-
✔ 時間外労働は年720時間以内
-
✔ 単月では100時間未満
-
✔ 2ヶ月〜6ヶ月のいずれの期間でも月平均80時間以内
時間外労働の上限規制は、長年にわたり建設業界の課題とされてきた長時間労働の慣行を是正し、働く人々の健康を確保するとともに、仕事と私生活の調和の実現を目指すものです。
また、週休2日の確保も働き方改革の重要な柱の1つです。 国土交通省は、国が直接発注する公共工事において週休2日を前提とした工期設定や積算を行う「週休2日モデル工事」を積極的に推進しており、実施率は着実に向上しています。
民間工事でも、公共工事に倣って働き方改革を進める企業が増えています。 そして、建設業は現場作業が中心のためテレワークが難しいと思われがちですが、オフィス業務ではデジタル化が進み、リモート作業が増加しました。
感染症対策が大きな動機となったケースも多かったものの、柔軟な働き方の実現や従業員の満足度向上、さらには離職防止といった効果にも注目が集まっているのでしょう。
建設業界の需要についてよくある質問
建設業界の需要や将来性について、多くの方がさまざまな疑問や不安を持つこともあるかもしれません。
ここでは、国の統計データや業界団体の情報を基に、Q&A形式で分かりやすく解説します。
建設業に若手がいないのはなぜですか?
「建設業に若手がいない」という声をよく耳にしますが、新卒で建設業界に入職する人が全くいないわけではありません。
問題の本質は、他の産業と比較して若年層の就業者の割合が低く、一方で高齢化が進行していること、そして建設投資の増加に伴う需要の拡大に人材供給が追いついていない点にあります。
国土交通省のデータによると、建設技能労働者のうち29歳以下の割合は約11.7%で、これは全産業の平均よりも低い水準です。
新卒の入職者数は2017年以降、年間4万人台を維持していますが、残念ながら早期離職も課題の1つとなっています。
建設投資額が増加傾向にあるため、業界全体の仕事量が増え、現場では若手が不足している状況が続いています。若年層の入職を促進するとともに、魅力ある職場環境を整備し定着率を高めることが対策となるでしょう。
建設業で一番儲かる仕事は何ですか?
建設業において高い収入が期待できる職種としては、一般的に高度な専門知識や技術、そして豊富な経験が求められる建築士や施工管理技士が挙げられます。
厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、建築士の平均年収は約703万円、建築施工管理技術者は約599万円です。
ただし、この年収はあくまで平均値で、実際の年収は、勤務する企業の規模、これまでの実務経験年数、担当するプロジェクトの規模や難易度、保有している資格の種類や数など、個々の条件によって大きく変動します。
建築士や施工管理技士は、建築基準法や建設業法といった関連法規の深い理解に加え、複雑な設計能力や大規模な建設プロジェクト全体を統括する高度な工事監理と施工管理能力が欠かせません。重い責任と高い専門性に見合う形で、報酬が設定される傾向にあります。
出典:土木施工管理技術者|厚生労働省
出典:建築設計技術者|厚生労働省
建設業界が不人気な理由は何ですか?
建設業界がこれまで「不人気」というイメージを持たれていた主な理由には、いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)」があります。ネガティブな言葉で代表される労働環境への先入観が、強く影響していました。
しかし、国土交通省は従来のイメージを払拭し、業界の魅力を高めるために「新3K(給与・休暇・希望)」を提唱し、実現に向けて具体的な取り組みを推進しています。
例えば、適正な賃金水準の確保や週休2日制の着実な導入、そしてICT技術を積極的に活用して生産性を向上させる「i-Construction」の推進などです。 i-Constructionでは、ドローンやICT建機などを活用し、危険な場所での作業を減らし、より効率的で安全な働き方の実現を目指しています。
出典:新3Kを実現するための直轄工事における取組|国土交通省
まとめ
建設業界は、公共工事・インフラ更新、住宅リフォーム需要の拡大により、2025年以降も投資額が堅調に伸びると予測されます。
また、i-Constructionやドローン測量などデジタル施工で安全性も高まっています。
建設業界での需要の変化は、若手にもベテランにも好機をもたらし、施工管理技士・建築士などの有資格者のニーズは一段と高まるでしょう。
「ベスキャリ建設」では、業界に精通した専門のキャリアアドバイザーが、これまでの経験やスキル、理想の働き方や希望の年収、条件を丁寧にヒアリングし、最適な求人をご紹介いたします。
市場の追い風を受け、キャリア形成を図りたい方は、ぜひ建設業界に特化したキャリアアドバイザーが伴走するベスキャリ建設をご活用ください。
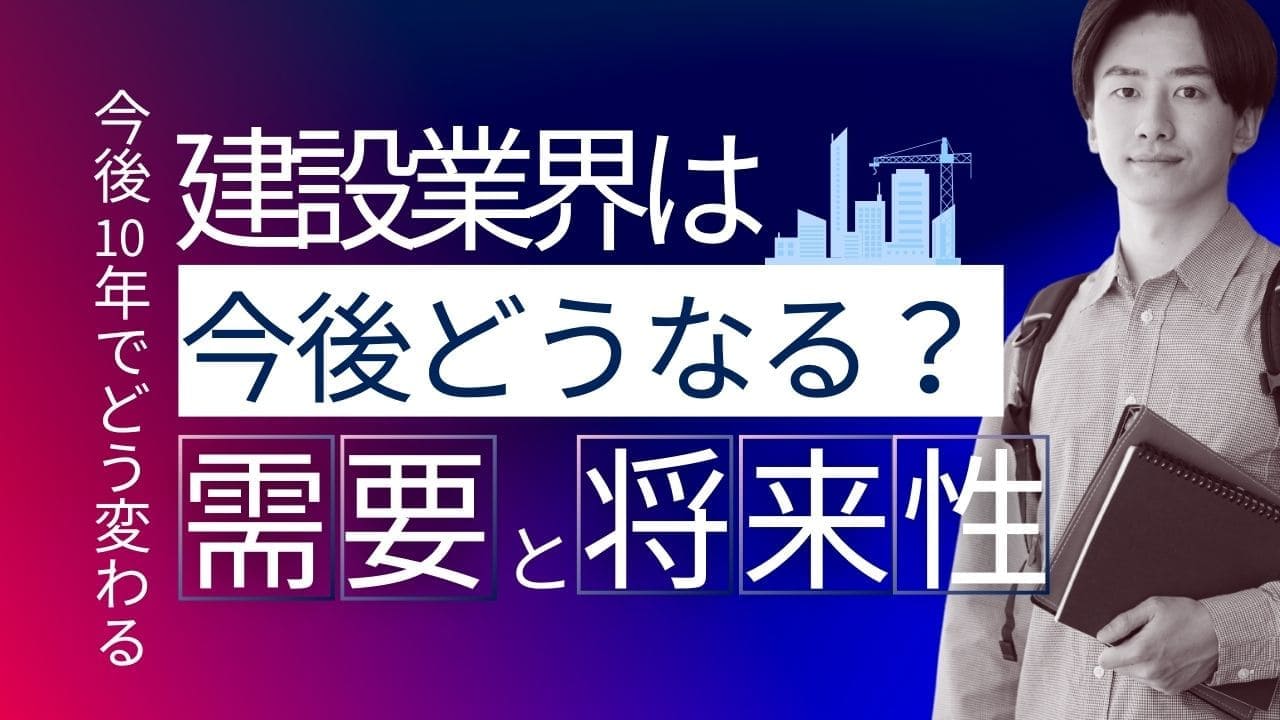



_180x98.png)

















.jpeg)


