電気工事分野でキャリアアップを目指すうえで重要な国家資格が「1級電気工事施工管理技士」です。令和6年度から制度が改正され、受検資格の緩和や試験制度の変更が行われたことで、より多くの技術者が挑戦できるようになりました。
しかし、「受検資格が複雑」「1級と2級の違いがわからない」「合格率や難易度はどの程度?」といった不安を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、試験制度の最新情報、受検資格、合格率、勉強方法、取得メリットまでを網羅的に解説します。
資格取得を目指す方に向けて、信頼できる最新情報をお届けするのでぜひチェックしてみてください。
- ✓ 2026年(令和8年度)の試験日程・申請期間・会場まとめ
- ✓ 新制度の受検資格区分と第一次/第二次検定の出題内容
- ✓ 合格率・難易度、手数料、取得メリットと学習法の要点
1級電気工事施工管理技術検定の内容
1級電気工事施工管理技士の資格取得には、「第一次検定(学科)」と「第二次検定(実地)」の両方に合格する必要があります。
第一次検定では施工管理に関する法規や技術的知識が問われ、第二次検定では実務経験をもとにした判断力・応用力が評価されます。
令和6年度から制度改正が進み、受検資格や申請方法も変更されました。なお、試験は年1回実施され、合格すれば国土交通省所管の国家資格として、公共工事の監理技術者などに従事するための重要なステップとなります。
ここでは、第一次検定と第二次検定それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
第一次検定
第一次検定では、電気工事の施工管理に必要な法規、施工計画、安全管理、品質管理などについて幅広く問われます。
選択式のマークシート方式で実施され、出題範囲は建設業法や電気事業法、労働安全衛生法など多岐にわたります。受検資格は「試験年度に満19歳以上」であることとされており、比較的多くの方が受検可能です。
試験は全国10か所以上の会場で行われ、合格すると「1級電気工事施工管理技士補」として認定されます。合格率は例年35~40%程度で、しっかりとした対策が求められる試験です。
第二次検定
第二次検定は、現場での実務経験をもとに、施工管理における応用力や判断力が問われる記述式の試験です。
2024年度からは受検資格制度が刷新され、新旧どちらの区分でも受検が可能ですが、経過措置期間を過ぎると新制度のみとなります。
試験内容は、施工体制・工程管理・安全対策・品質管理などの実務的な設問で構成されており、過去問を活用した実践的な学習が重要です。
合格後は「1級電気工事施工管理技士」として正式に認定され、監理技術者としての配置要件を満たすことができます。
出典:令和7年度 1級 電気工事施工管理技術検定のご案内 一般財団法人建設業振興基金
【令和7年度】1級電気工事施工管理技術検定の日程と会場
令和7年度の1級電気工事施工管理技術検定は、例年通り第一次検定(筆記)と第二次検定(実地)の2段階で実施されます。
各検定には異なる申請期間・試験日・合格発表日が設けられており、会場も全国主要都市で開催予定です。以下に最新スケジュールをまとめました。
| 第一次検定 | 第二次検定 | |
|---|---|---|
| 申請受付期間 | 2025年2月14日(金)〜2月28日(金) ネット申請のみ4月7日(月)まで(※1) |
同左 (※2,3) |
| 試験日 | 2025年7月13日(日) | 2025年10月19日(日) |
| 合格発表 | 2025年8月22日(金) | 2026年1月9日(金) |
| 試験地 | 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄 | |
出典:令和7年度 1級 電気工事施工管理技術検定のご案内 一般財団法人建設業振興基金
※1 ネット申請のみ。インターネット環境がない方は、必ず2月28日までにご相談ください。
※2 願書販売は1月31日(金)からです。本財団WEBサイトからの注文は2月21日正午までとなっていますので、早めのご対応をお願いします。
※3 第一次検定の合格を確認してから、同年の第二次検定へ受検申請をすることはできません。
第一次検定と第二次検定を同時に申請する場合は書面申請が必要で、再受検者はネット申請が可能です。
また、会場は都道府県ごとに異なる可能性があるため、事前に受検票や案内通知をよく確認しましょう。
1級電気工事施工管理技術検定の受検資格
令和7年度からの制度改正により、1級電気工事施工管理技士の受検資格は、2級合格後の実務年数や学歴・職歴に応じた「区分制」に変更されました。
以下の表で、自分がどの区分に該当するかを確認し、必要な実務経験年数を把握しておきましょう。
| 受検資格区分 | 必要な実務経験 | 対象となる合格年度 |
|---|---|---|
| 【区分1】2級第二次検定の合格者 | 合格後5年以上 | 令和元年度までの合格者 |
| 【区分2】2級第二次検定合格後、特定実務経験あり | 特定実務経験1年以上を含む3年以上 | 令和3年度までの合格者 |
| 【区分3】旧制度(学歴+実務経験) |
学歴・職歴に応じた年数 (例:高卒9年以上など) |
令和3年度以前の受検資格者 |
出典:建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 受検の手引」
新制度では、実務経験を積んだ2級合格者が対象の中心となりますが、旧制度による学歴・職歴経由の受検も一部可能です。
自分の合格年度や経験年数がどの区分に該当するかを公式手引で必ず確認しましょう。受検要件を満たさないと申請は無効になります。
1級電気工事施工管理技術検定試験の申請方法
1級電気工事施工管理技術検定の申請方法は、受検区分や申請種別(新規/再受検)により異なります。第一次検定のみの申請はネットから行えますが、一次・二次同時申請や第二次検定のみの申請には原則書面での手続きが必要です。
ただし、平成15年度以降に同種目を受検している場合、再受検として一部書類の省略が可能です。ネット申請では受検資格の自動判定が行われ、ミスを防げるため推奨されています。願書は1月末より販売され、受付は2月中旬から2週間程度と短いため、早めの準備が重要です。
1級電気工事施工管理技術検定試験の受検手数料
令和7年度の1級電気工事施工管理技術検定の受検手数料は、第一次検定・第二次検定ともに15,800円(非課税)です。
一次・二次同時に申請する場合、第一次検定合格後に第二次検定分の支払いを行います(支払期限は9月上旬予定)。受検手数料は申請方法により支払いタイミングが異なるため、受検の手引や通知書を必ず確認しましょう。なお、手数料納入後の返金は原則できないため、受検の可否やスケジュールに問題がないか事前に確認しておくことが大切です。
1級電気工事施工管理技術検定試験の試験地
令和7年度の1級電気工事施工管理技術検定は、全国10会場で実施されます。
主な試験地は、札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄です。ただし、会場確保の都合により、近隣の府県などに変更される場合もあります。
試験地の詳細は受検票に記載され、受検者の希望による変更は基本的にできません。早期に申し込むことで、希望する地域での受検がしやすくなるため、日程に余裕をもって申請を行うことが推奨されます。
1級電気工事施工管理技術検定試験の難易度と合格率
1級電気工事施工管理技士は、施工管理の中でも専門性が高く、電気工事現場の責任者として必要とされる国家資格です。
合格率は年によって変動しますが、近年は第一次検定で約36〜40%、第二次検定で約50%前後となっており、中〜やや難関レベルと評価されています。
| 年度 | 検定種別 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 第一次検定 | 23,927人 | 8,784人 | 36.7% |
| 令和5年度 | 第一次検定 | 16,265人 | 6,606人 | 40.6% |
| 令和5年度 | 第二次検定 | 8,250人 | 4,093人 | 49.6% |
出典:建設業振興基金「令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 結果表」
令和6年度は制度改正により受検者数が大幅に増加したものの、第一次検定の合格率は36.7%と大きくは下がっていません。
これは過去問や基礎知識中心の対策でも対応できる難易度であることを示唆しています。第二次検定は記述式で対策が難しい一方、合格率は約50%と比較的高めです。
1級電気工事施工管理技術検定とほかの電気系資格の違い
電気に関する資格は数多く存在しますが、それぞれの目的や活躍できる場が異なります。
なかでも「1級電気工事施工管理技士」は、工事現場のマネジメントに特化した国家資格です。以下に、電気主任技術者や電気工事士など主要な電気系資格と比較した違いをまとめました。
| 資格名 | 資格区分 | 主な業務範囲 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 国家資格(技術検定) | 電気工事の施工計画・安全管理・品質管理 | 工事全体のマネジメントを担う |
| 第一種電気工事士 | 国家資格 | 600V超の電気設備工事 | 実際の電気工事作業を行う技術者向け |
| 電験三種(第三種電気主任技術者) | 国家資格 | 電気設備の保安監督(出力5,000kW未満) | 保守・点検・法令管理に特化 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 国家資格(技術検定) | 通信インフラ工事の管理 | 通信ケーブルや設備の施工管理に従事 |
「施工管理技士」は電気工事そのものではなく、工程・品質・安全などの管理業務を担当する立場です。
一方、電気工事士は配線・接続など実作業、電験三種は設備全体の保安責任者となる役割を担います。目的や活躍の場が異なるため、自身のキャリアに合った資格選びが重要です。
1級電気工事施工管理技術検定試験に合格するメリットとは?
1級電気工事施工管理技士に合格すると、国家資格としての信頼性が高く、公共工事での主任技術者や監理技術者としての選任が可能になります。
特に建設業法に基づく重要ポジションに就けるため、キャリアアップや転職時のアピールにも有利です。企業によっては資格手当や昇進条件に含まれていることもあり、年収アップにつながるケースも少なくありません。
また、現場の統括管理や安全対策における責任範囲が広がるため、技術者としての信頼とやりがいも得られます。電気工事分野で長期的に活躍したい方にとって、取得する価値の高い資格だといえるでしょう。
1級電気工事施工管理技術検定に合格するための勉強方法
1級電気工事施工管理技士の試験は専門性が高く、計画的な学習が合否を左右します。仕事と両立しながら効率よく学ぶには、自分に合った方法の選定が重要です。
ここでは、勉強スケジュールの立て方から過去問の活用、講座やアプリの使い方まで、合格に向けた具体的な対策を紹介します。
勉強方法1. 検定までの勉強スケジュールを立てる
試験対策を始めるにあたり、まず大切なのが全体のスケジュール設計です。一次検定は択一式、二次検定は記述式であり、必要な勉強内容や時間が異なるため、それぞれ逆算して準備期間を設定しましょう。
平均的な学習時間の目安は、一次検定で100〜150時間、二次検定で150〜200時間です。平日は1〜2時間、休日はまとまった時間を確保するよう計画を立て、無理のないペースを心がけることが継続のコツです。
勉強方法2. 過去問を活用して出題傾向をつかむ
過去問は合格への最重要教材です。一次検定は出題形式が安定しているため、5年分ほどを繰り返し解くことで傾向や頻出テーマを把握できます。
間違えた問題は解説を読み、なぜ間違えたのかを理解することが重要です。二次検定では、記述力と構成力が問われるため、答案例を参考にしながら自分でも記述練習を積みましょう。可能であれば添削サービスの利用もおすすめです。
勉強方法3. 資格学校の講習や通信講座を活用する
独学が難しいと感じたら、資格学校や通信講座の受講もおすすめです。専門講師の解説を通じて、難解な法規や施工管理法も理解しやすくなります。
また、模擬試験や添削サポートがある講座では、自分の実力を客観的に把握し、苦手分野を重点的に対策できるでしょう。最近ではオンライン形式の講座も増えており、働きながらでも柔軟に学べる環境が整っている点も魅力の一つです。
勉強方法4. スマホアプリを活用する
通勤時間やスキマ時間に学習を進めたい方には、スマホアプリの活用が便利です。択一式問題に特化した問題集アプリなら、いつでもどこでも学習が可能で、復習や間違えた問題の管理もしやすい点がメリットです。
「施工管理技士 一級」などで検索すると、無料アプリも多数見つかります。メイン教材との併用により、学習の定着率を高めることができるでしょう。
まとめ
1級電気工事施工管理技士は、公共工事の主任技術者・監理技術者に選任されるための重要な資格であり、取得によって年収アップや昇進、専門性の証明につながります。
令和6年度以降の制度改正により、受検資格の幅が広がった一方で、出題傾向や合格基準の理解も求められるようになりました。
合格のためには、過去問や講習などを活用した計画的な対策が不可欠です。将来を見据えたキャリア設計の第一歩として、ぜひ本記事を参考にして資格取得を目指してみてください。
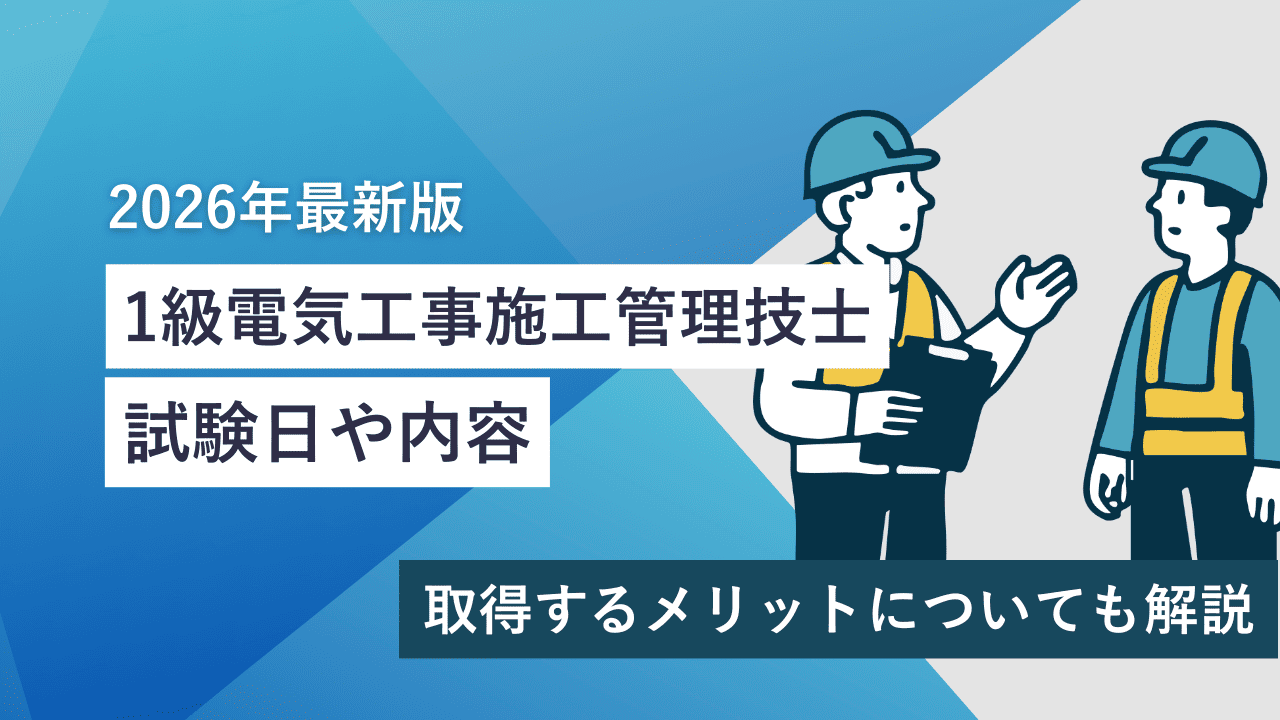


_180x98.png)
_180x98.png)
_180x98.png)
 (1)_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


