土木施工管理技士とは、河川や道路などの土木工事において、施工計画の立案や工程・品質・安全管理などを担う技術者に必要な国家資格です。主任技術者や監理技術者として、工事全体を統括する役割を担います。
「土木施工管理技士の受検資格や難易度が気になる」「1級と2級の違いがよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、土木施工管理技士の仕事内容や年収、1級・2級の違い、取得のメリットについて解説します。
土木業界でキャリアアップを目指す方や、土木施工管理技士の資格取得に興味がある方はぜひ参考にしてください。
土木施工管理技士とは
土木施工管理技士とは、建設業法に基づいて定められた「施工管理技士」の7区分のうちの1つで、国土交通省が認定する国家資格です。
ここでは、土木施工管理技士の仕事内容や主な勤務先、平均年収について解説します。
併せて、資格取得後にどのような働き方ができるのかもまとめたので「土木施工管理技士は何ができるの?」という疑問を持っている方はぜひチェックしてみてください。
土木施工管理の仕事内容
土木施工管理とは、土木工事の現場において、施工計画を立案し、工事全体の監督・指導を行う仕事です。
対象となる工事には、橋梁や道路、鉄道、ダム、河川、港湾などのインフラ整備が含まれます。 施工計画の立案では、設計図や仕様書、関係法規、施工手順、工期、予算などを総合的に考慮しながら計画を策定します。
実際の施工段階では、工程管理・安全管理・品質管理・原価管理といった「施工管理の4大管理」を実施し、工事の円滑な進行を図ります。
また、現場全体の進捗を把握した上で、作業責任者や協力業者への適切な指示・調整を行うことも重要な役割です。
特に大規模プロジェクトでは、「土木施工管理技士」が現場マネジメントを担い、「土木設計技術者」が調査・設計・計画を担当するなど、業務の分業化が行われるケースもあります。
出典:土木施工管理技術者 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
土木施工管理技士の勤務先
土木施工管理技士の主な勤務先は、ゼネコン(総合建設会社)や土木専門業者、建設コンサルタント、官公庁、研究機関などの土木部門です。
加えて、インフラ関連企業である電力・鉄道・ガス・不動産会社などに所属するケースもあります。
土木施工管理技士が実際に働く現場は、全国各地の土木工事現場が中心です。代表的な現場として、道路、河川、上下水道、港湾、造成地、鉄道などが挙げられます。
労働条件は、工事の種類や規模、施工場所の環境、天候や工期などに大きく左右されるのが特徴です。
たとえば、交通量の多い道路工事では夜間作業が一般的となり、屋外工事では天候による作業の変更も多く発生します。現場の状況に左右されやすいため、労働条件の安定性に課題を抱える企業も見受けられます。
土木施工管理技士の平均年収
厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「job tag」によると、令和5年における土木施工管理技術者の平均年収は約604万円です。
一方、国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、全職種の平均年収は約460万円でした。 これらを比較すると、土木施工管理技士の平均年収は全体平均より約140万円高く、比較的高水準であることが分かります。
ただし、実際の年収は勤務する地域や経験年数、企業規模、資格の有無、担当する現場の規模などによって大きく異なります。
特に、大規模工事の現場責任者や管理職に就いている場合は、平均を上回る年収を得るケースも少なくありません。
出典:土木施工管理技術者|職業情報提供サイト job tag|厚生労働省
土木施工管理技士の1級と2級の違いとは
土木施工管理技士の資格には、1級と2級の2つの区分があります。それぞれ対応できる工事の規模や業務範囲に違いがあるため、違いを押さえておくことが重要です。
ここからは、1級と2級の資格で担当できる業務の違いを中心に、実務上の役割や配置可能な技術者区分について詳しく解説します。
監理技術者資格の違い
1級土木施工管理技士と2級土木施工管理技士では、「監理技術者」になれるかどうかに明確な違いがあります。1級土木施工管理技士を取得すると、監理技術者として現場に配置される資格が与えられます。
監理技術者とは、特定建設業者(元請)が発注者と総額5,000万円以上(建築一式では8,000万円以上)の下請契約を結ぶ場合に、設置が義務付けられている技術者のことです。
監理技術者は、複数の下請業者を統括・指導し、品質や安全の確保を担います。
一方で、2級土木施工管理技士は監理技術者の資格要件を満たさないため、監理技術者としての配置はできません。
ただし、主任技術者として現場に配置されることは可能です。主任技術者は、すべての建設工事(軽微な工事を除く)において設置が義務付けられており、施工の管理や技術的指導を担う責任ある立場です。
つまり、2級土木施工管理技士でも、中小規模の土木工事であれば、現場の責任者として十分に活躍することが可能です。
出典:土木施工管理技士(1級・2級) | CIC日本建設情報センター
業務領域の違い
1級土木施工管理技士は、監理技術者として大規模な公共工事の現場責任者を務めることができます。国や地方自治体などが発注する工事を含め、複数の下請業者を統括・指導しながら、工事全体を総合的に管理する役割を担います。
一方で、2級土木施工管理技士が担当するのは、比較的規模の小さい民間工事や住宅開発などが中心です。
主任技術者として現場に配置されることが多く、主に単体工事や限られた範囲の施工管理を担当します。1級に比べて対応できる工事の規模や業務範囲に制限があるため、仕事の内容が限定される傾向があります。
経営事項審査の加点の違い
1級土木施工管理技士と2級土木施工管理技士では、経営事項審査(経審)における加点にも違いがあります。
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負う建設業者に対して国や地方自治体が実施する審査で、競争入札の参加資格を判断するための重要な評価基準です。 経審で評価対象となる項目のひとつに「技術職員数(Z点)」があります。この項目では、1級土木施工管理技士が1人在籍していると5点が加算されます。
さらに、監理技術者講習を修了し、「監理技術者資格者証」が交付されている場合には、追加で1点が加算され、最大6点となるのです。 一方で、2級土木施工管理技士が1人在籍している場合の加算は2点にとどまります。 そのため、1級土木施工管理技士と2級土木施工管理技士では、最大で4点の差が生じることになります。
このように、経営事項審査において1級土木施工管理技士の在籍は、企業の評価点を大きく左右する要素となり、公共工事を受注する上での重要な競争力となるのです。
第一次検定合格後の資格の違い
1級土木施工管理技士の第一次検定に合格すると、「施工管理技士補」という資格が付与されます。
施工管理技士補とは、令和3年4月の試験制度改正により新設された国家資格で、監理技術者の補佐として現場に従事することができます。 この制度が設けられた背景には、監理技術者の人手不足の解消があります。
施工管理技士補が補佐に入ることで、監理技術者が複数現場を兼任できるようになり、技術者の効率的な配置が可能となるでしょう。 なお、第一次検定の合格には有効期限が設けられていないため、施工管理技士補として現場経験を積みながら、適切なタイミングで第二次検定を受験することができます。
【令和7年度】土木施工管理技士試験の基本情報
ここでは、令和7年度に実施予定の土木施工管理技士試験について、1級および2級の試験科目や受検資格、合格基準、合格率などの基本情報を詳しく解説します。
試験内容を正確に把握し、計画的に学習を進めることが合格への第一歩です。受検を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1級土木施工管理技士の試験科目
1級土木施工管理技士の試験は、「第一次検定」と「第二次検定」に分かれています。
合格を目指すにあたっては、それぞれの検定科目や出題範囲、評価基準を理解しておくことが重要です。以下では、各検定における出題内容の概要と学習時の注意点について解説します。
| 検定区分 | 検定科目 | 検定基準(求められる知識・能力) |
|---|---|---|
| 第一次検定 | 土木工学等 | ・土木一式工事の施工管理に必要な一般的な知識(以下を含む): └ 土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学、建築学 ・設計図書に関する一般的な知識 |
| 第一次検定 | 施工管理法 | ・監理技術者補佐として、施工管理に必要な知識(施工計画・工程管理・品質管理・安全管理) ・施工管理に関する応用能力 |
| 第一次検定 | 法規 | ・施工管理に必要な法令(建設業法など)に関する一般的な知識 |
| 第二次検定 | 施工管理法 | ・監理技術者として、施工管理に必要な実務知識 ・土質試験や材料強度試験を正確に行い、適切な対応をする応用能力 ・設計図書に基づいた施工計画の立案および実施に必要な応用能力 |
出典:令和7年度1級土木施工管理技術検定 第一次検定・第二次検定 新受検資格 受検の手引|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:土木施工管理技士】KGKC 建設技術教育センター
1級土木施工管理技士の受検資格
1級土木施工管理技士試験には、第一次検定と第二次検定それぞれに受検資格が定められています。
受検資格の条件には、年齢や実務経験の有無などがあり、受検前に自分が該当するか確認しなければなりません。
ここでは、令和7年度における1級土木施工管理技士試験の受検資格の詳細を分かりやすく解説します。
第一次検定の受検資格
1級土木施工管理技士試験の「第一次検定」は、学歴に関係なく満19歳以上であれば誰でも受検可能です。
たとえば、令和7年度の試験では平成19年4月1日以前に生まれた方(同日含む)が対象となります。
| 対象者 | 平成19年4月1日以前に生まれた者(平成19年4月1日生まれも含む) |
|---|---|
| 実務経験 | 不要(経験の有無に関わらず受検可能) |
出典:令和7年度1級土木施工管理技術検定《検定区分》第一次検定受検の手引
第二次検定の受検資格【経過措置:令和6年度〜令和10年度】
1級土木施工管理技士試験の「第二次検定」は、所定の実務経験を有する方のみが対象です。
令和6年度から制度が改正されたため、令和10年度までは旧制度と新制度のいずれかを選択できる「経過措置」が設けられています。
実務経験年数の要件は、3区分に分類されます。詳しい要件は、下表をご覧ください。
| 受検資格要件 | 実務経験年数の要件 |
|---|---|
| 令和3年度以降の1級第一次検定合格者 | 合格後に5年以上の実務経験 |
| 令和3年度以降の1級第一次検定合格者 | 合格後に特定実務経験1年以上を含んだ3年以上の実務経験 |
| 令和3年度以降の1級第一次検定合格者 | 合格後に監理技術者補佐として1年以上の実務経験 |
| 2級第二次検定合格後に1級第一次検定に合格した者 | 2級合格後に5年以上の実務経験 |
| 2級第二次検定合格後に1級第一次検定に合格した者 | 2級合格後に特定実務経験1年以上を含んだ3年以上の実務経験 |
| 技術士第二次試験(土木部門)合格者 | 合格後に5年以上の実務経験 |
| 技術士第二次試験(土木部門)合格者 | 合格後に特定実務経験1年以上を含んだ3年以上の実務経験 |
出典:令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります|一般財団法人
全国建設研修センター 令和6年度から土木施工管理技士試験の受検資格が変更されたことに伴い、経過措置が令和10年度までの5年間にわたり設けられています。
この期間中は、「新受検資格」または「旧受検資格」のいずれかを選んで受検することが可能です。
※なお、申込締切後の資格区分(新・旧)の変更はできませんので、申込時に慎重に選択してください。
詳しくは、一般財団法人 全国建設研修センター 1級土木施工管理技術検定をご確認ください。
1級土木施工管理技士の合格基準点
1級土木施工管理技士の試験は、「第一次検定」と「第二次検定」に分かれており、それぞれに合格基準が定められています。
「全国建設研修センター」が公表する資料をもとに、第一次検定・第二次検定の合格基準を下表にまとめました。
| 区分 | 合格基準 |
|---|---|
| 第一次検定 | 総得点の60%以上、かつ施工管理法(応用能力)の得点が60%以上 |
| 第二次検定 | 総得点の60%以上 |
特に第一次検定では、「施工管理法(応用能力)」の科目にも個別の合格基準が設けられているため、他の科目で得点が高くても、この科目で基準に達しない場合は不合格となります。
1級土木施工管理技士の合格率
過去3年間に実施された1級土木施工管理技士試験の第一次検定、第二次検定の合格率は、下表のとおりです。
難易度や受検傾向を把握する上での参考情報として活用しましょう。
| 実施年 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 44.4% | 41.2% |
| 令和5年度 | 49.5% | 33.2% |
| 令和4年度 | 54.6% | 28.7% |
出典:1級土木施工管理技士受検者数・合格率動向|KGKC建設技術教育センター
令和6年度は、制度改正により受検要件が緩和された影響で第一次検定の受検者数が大幅に増加しました。
その結果、受検者の母数の拡大が合格率に影響を及ぼし、例年と比べて合格率が低下したと考えられています。
なお、合格率は年によって変動するため、あくまでも目安のひとつとして捉え、自身の状況に応じた学習計画や対策を講じることが重要です。
2級土木施工管理技士の試験科目
2級土木施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定に分かれており、それぞれで試験科目や出題形式が異なります。
どのような分野の勉強が必要なのかを把握し、効率よく学習を進めるためにも、試験科目の構成と出題傾向を確認しておきましょう。
第一次検定
2級土木施工管理技士の第一次検定は、マークシート方式で実施され、全66問中45問以上の正答で合格となります。
出題形式は選択問題が中心で、以下の6つの試験科目から出題されます。 第一次検定の試験科目
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 工学基礎 | 土質工学・構造力学・水理学(※令和6年度から新設) |
| 土木一般 | 土工・コンクリート工・基礎工 |
| 専門土木 | 構造物・河川・砂防・道路・舗装・ダム・トンネル・海岸・港湾・鉄道・地下構造物・上下水道 |
| 法規 | 労働基準法・労働安全衛生法・建設業法など |
| 共通工学 | 測量・契約・設計・機械・電気 |
| 施工管理 | 施工計画・安全管理・品質管理・環境保全・建設副産物・基礎的な能力 |
出典:2級土木施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
- 工学基礎:令和6年度から新設された科目で、学術的要素が強く難易度はやや高め
- 土木一般:基礎的な内容の出題が多く、比較的取り組みやすい
- 専門土木・施工管理:専門性が高く、第二次検定でも問われる重要科目
- 法規:頻出の法令が限られており、過去問の活用が効果的
- 共通工学:出題範囲が広く、効率的な学習が必要
第二次検定
2級土木施工管理技士の第二次検定は、4つの試験科目から構成され、すべて記述式で実施されます。出題数は全9問で、そのうち7問に解答します。
記述問題はすべての科目からバランスよく出題されるため、特定の科目に偏らず、全科目に対する対策が不可欠です。
出題傾向や記述パターンを分析し、実務的な視点での記述力を身につけておくことが合格のポイントとなります。
第二次検定の試験科目
| 試験科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 施工経験記述 | 受検者が過去に経験した工事について論文記述する形式 工事概要や技術的な課題、課題に対する検討内容などを記述 |
| 土工 | 土量の計算・盛土の締め固め・排水工法・のり面保護工・軟弱地盤対策・建設機械など |
| コンクリート工 | コンクリートの品質・打ち込み・養生・鉄筋の加工・組立など |
| 施工管理 | 施工計画・安全管理・品質管理・環境保全 |
出典:2級土木施工管理技士出題傾向|KGKC建設技術教育センター
施工経験記述は、過去に経験した工事について論文として記述する問題です。
記述テーマに即した内容で論文にまとめる形で回答します。技術的な課題や現場で実施した対策など、記述した内容の整合性が取れていることが重視されます。事前にしっかりと記述の練習を積む必要があるでしょう。
土工やコンクリート工、施工管理は出題範囲が幅広いため、過去問対策と知識の整理が欠かせません。用語の理解や記述練習を通じて、実務に即した表現で解答できる力を身につけましょう。
2級土木施工管理技士の受検資格
2級土木施工管理技士の受検資格は、1級とは異なります。申込時に適切な受検区分を選ぶためにも、受検要件を正しく把握しておくことが重要です。
第一次検定の受検資格
2級土木施工管理技士の第一次検定は、試験実施年度において満17歳以上であれば受検可能です。
たとえば令和7年度の場合、平成21年4月1日以前に生まれた方が対象となります。 学歴や実務経験は不問であり、誰でも受検することが可能です。
ただし、第二次検定には実務経験が必要なため、第一次検定合格直後にすぐ第二次検定を受けることはできない場合があります。
第二次検定の受検資格
2級土木施工管理技士の第二次検定は、受検資格区分が3つに分けられています。
「2級の一次検定合格者」「1級の一次検定合格者」「技術士第二次試験合格者」など、区分によって必要な実務経験が異なるため注意しましょう。
| 受検区分 | 対象者 | 必要な実務経験 |
|---|---|---|
| 区分1 | 2級土木施工管理技士 第一次検定合格者 | 合格後3年以上 |
| 区分2 | 1級土木施工管理技士 第一次検定合格者 | 合格後1年以上 |
| 区分3 | 技術士第二次試験合格者(該当部門) | 合格後1年以上 |
ただし、年度ごとの試験実施状況や難易度に応じて、合格基準が調整される場合があるため注意が必要です。
第一次検定はマークシート方式で実施され、出題数に対し60%以上の正答で合格となります。
第二次検定は記述式で実施され、配点や採点基準は公開されていませんが、総得点率60%が合格ラインの目安とされています。
| 検定区分 | 合格基準 |
|---|---|
| 第一次検定 | 得点率60%以上(マークシート方式) |
| 第二次検定 | 得点率60%以上(記述式) |
出典:令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)受検の手引|一般財団法人 全国建設研修センター
出典:令和6年度2級土木施工管理技術検定 第二次検定 新受検資格 受検の手引|一般財団法人 全国建設研修センター
2級土木施工管理技士の合格率
過去3年間に実施された2級土木施工管理技士の合格率は、以下のとおりです。
- 区分1:2級の一次試験合格者は、合格後に3年以上の実務経験が必要
- 区分2:1級の一次試験合格者であれば、1年以上の実務経験を積むことで2級の第二次検定に進める
- 区分3:技術士第二次試験の合格者も、1年以上の実務経験があれば受検可能
出典:2級土木施工管理技士 第二次検定 新受検資格 受検の手引|一般財団法人 全国建設研修センター
2級土木施工管理技士の合格基準
2級土木施工管理技士の合格基準は、下記のとおりです。
| 実施年 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 44.6% | 35.3% |
| 令和5年度 | 52.1% | 62.9% |
| 令和4年度 | 64.0% | 37.9% |
出典:2級土木施工管理技士受検者数・合格率動向|KGKC建設技術教育センター
第一次検定・第二次検定ともに、年度ごとに合格率に大きな差があることが分かります。
これは、受検者数の変動や試験の難易度、制度変更の影響などによるものだと考えられるでしょう。
特に、合格率が50%を下回る年もあることから、容易に合格できる試験ではないと言えます。合格するためには、出題傾向を踏まえた十分な準備と対策が必要です。
土木施工管理技士を取得するメリット
ここでは、土木施工管理技士の資格を取得することによって得られる代表的な3つのメリットを紹介します。
- 監理技術者になれる
- 昇給や昇進しやすい
- 転職で有利になる
土木施工管理技士の資格を取得することで、キャリアの選択肢が広がり、現場での責任ある立場を担えるようになるなど、さまざまなメリットがあります。
監理技術者を務められる
1級土木施工管理技士の資格を取得すれば、監理技術者として現場を統括する立場に就くことができます。監理技術者とは、施工計画の作成や現場の施工管理、下請業者への技術的指導などを担う重要なポジションであり、総額5,000万円以上の工事(建築一式は8,000万円以上)を請け負う場合には設置が義務付けられています。
特に公共工事では、発注者との折衝や現場全体の統括を行う責任者として活躍する機会も多く、社会的な信頼性が高く、専門スキルを客観的に証明できる資格です。
また、監理技術者の人材は建設・土木業界において慢性的に不足しており、需要が非常に高いのが現状です。
そのため、主任技術者よりも高収入が見込まれるほか、プロジェクトの中心として重要な役割を担うことで、大きなやりがいも感じられるでしょう。
昇給や昇進しやすい
土木施工管理技士の資格を取得すると、昇給や昇進に有利になるケースが多く見られます。 その理由のひとつが、資格手当の支給制度です。多くの企業では、資格保有者に対して毎月の給与に上乗せする形で資格手当を支給しています。
また、土木施工管理技士の資格保持者が在籍していると、企業は経営事項審査(経審)における技術評価点(Z点)で加点を得られます。
この評価点は、公共工事の入札時に用いられるため、企業の競争力に直結する重要な指標です。 そのため、多くの企業が土木施工管理技士の資格取得を昇進要件の一つとして明文化しており、評価対象として重視する傾向にあります。
特に、大規模工事を担当できる1級土木施工管理技士は、社内外での評価が高く、人材確保や流出防止の観点から昇給・昇進で優遇されるケースも少なくありません。
転職で有利になる
土木施工管理技士の資格は、転職市場においても高い評価を受けます。 すべての建設現場には、主任技術者の配置が義務付けられており、加えて大規模な工事では監理技術者の配置も必須とされています。
そのため、施工管理技士の資格を持つ人材は、建設・土木業界において必要不可欠な存在だといえるでしょう。
資格を保有していることで、即戦力として現場に配属しやすくなるため、採用担当者からも高く評価されやすくなります。
また、近年では施工管理職の人材不足が深刻化しており、経験+資格を有する人材のニーズは全国的に高まっています。
土木施工管理技士の資格を持っていることで、より条件の良い企業やポジションへの転職を実現しやすくなるでしょう。
土木施工管理技士の試験に関してよくある質問
ここでは、土木施工管理技士の試験に関するよくある質問とその回答をまとめました。
受検資格・難易度・資格取得後の活用方法など、受検前に押さえておきたい重要なポイントを網羅しているので、ぜひ参考にしてください。
土木施工管理技士の難易度は?
2級土木施工管理技士は、年度によって合格率が35〜60%前後と幅があり、試験の難易度にもバラつきがあります。合格率が50%未満となる年もあるため、決して簡単な試験ではありません。
ただし、出題傾向を押さえたうえで計画的に対策を進めれば、十分に合格を狙えるレベルといえるでしょう。
一方で、1級土木施工管理技士の合格率は例年30%前後と低く、2級よりも難易度が高めです。科目数が多く、記述式の対策も必要になるため、長期的な学習計画が重要になります。
土木施工管理技士は誰でも受けられる?いきなりなれるもの?
制度改正により、第一次検定の受検資格が大きく緩和され、学歴や実務経験がなくても受検できるようになりました。年齢要件を満たせば、誰でも挑戦できます。
- 2級土木施工管理技士(第一次検定):満17歳以上
- 1級土木施工管理技士(第一次検定):満19歳以上
ただし、第二次検定の受検には所定の実務経験が必須です。 そのため、将来的に土木施工管理技士の資格取得を目指す場合は、実務経験の積み方やタイミングを含めた中長期的な計画を立てておくことが重要です。
2級土木施工管理技士の資格を取得すると何ができるの?
2級土木施工管理技士を取得すると、以下のような現場や企業内での役割を担うことができます。
- 一般建設業の営業所で「専任技術者」として配置される
- 工事現場で「主任技術者」として配置される
また、2級土木施工管理技士の資格者が在籍していると、企業は経営事項審査(経審)の「技術職員数」の評価項目で1人あたり2点の加点を受けられます。
この加点は、企業が公共工事を受注するうえでの競争力に直結する重要な指標です。 そのため、資格を取得していることで企業内での評価が高まり、昇給・昇進にもつながる可能性が高くなります。
まとめ
土木施工管理技士は、土木工事の現場で施工管理や監督・指示を行う責任ある重要なポジションです。資格は1級と2級に分かれており、監理技術者の資格要件や対応できる工事の規模などに違いがあります。
また、多くの企業で資格手当制度が導入されており、資格取得により昇給・昇進が期待できる点も大きなメリットです。
土木業界でキャリアアップを目指すなら、土木施工管理技士の資格取得を目標にすると良いでしょう。
これから実務経験を積んで土木施工管理技士を目指したい方や、転職を通じてキャリアアップを目指したい方は、建設業界に特化したキャリア支援サービスである「ベスキャリ建設」をご活用ください。
「ベスキャリ建設」では、あなたのご希望やスキルに合った職場探しをサポートします。転職のお悩みやキャリアに関する不安がある方も、お気軽にキャリアアドバイザーにご相談ください。
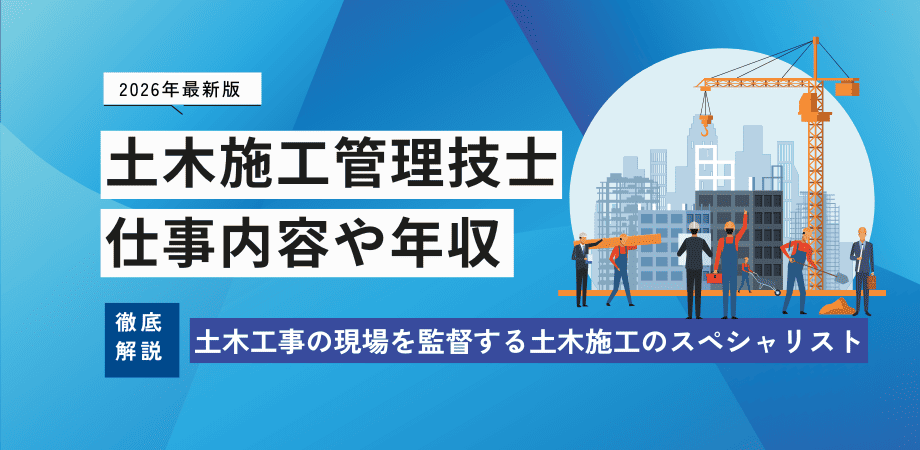





_180x98.png)
_180x98.png)
_180x98.png)
 (1)_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


