「現場監督はやめとけ」「激務できつい」という声を聞いて、不安になっていませんか。
現場監督は、建設現場をまとめる重要な役割を担う一方で、長時間労働や人手不足、責任の重さから「大変な仕事」と語られることも少なくありません。
しかし、現場監督のキャリアには他の職種では得られないやりがいや、国家資格を活かした将来の安定性といった魅力も存在します。
この記事では、なぜ「現場監督はやめとけ」と言われるのか、その理由を客観的なデータや実際の声とともに整理します。
現場監督として働き続けるべきか迷っている方に向けて、キャリアの選択肢や転職に関する情報もまとめました。
「現場監督はやめとけ」と言われる4つの理由

「現場監督はやめとけ」と言われる背景には、建設業界特有の労働環境や、責任負担の大きさがあります。
代表的な要因としては、長時間労働や休日取得の難しさ、トラブル対応を含む精神的プレッシャー、慢性的な人手不足による業務過多、そして給与と業務負荷のギャップが挙げられます。
これらが複合的に重なり、現場監督という職種に対して「厳しい」「割に合わない」といった印象を持たれることが多いようです。
ここでは、現場監督はやめとけと言われる理由について、4つに分けて解説します。
1. 労働時間が長く休みにくい
現場監督は工事の進行管理や安全確認、職人の段取り、朝礼準備などを担うため、始業前の準備から終業後の書類整理・会議対応まで、1日の拘束時間が10〜12時間に及ぶこともあります。
加えて、工程が遅れていたりトラブルが発生した場合は、休日返上の対応も求められます。
特に若手や経験の浅い監督は、慣れない業務への対応に時間がかかり、心身ともに疲弊しやすい傾向があります。
こうした実態が、「休めない」「続けにくい」というイメージにつながっています。
2. 責任が重く精神的プレッシャーが大きい
現場監督は、安全・品質・工程・コストのすべてを管理する立場にあり、現場での最終的な責任を負います。
万が一、事故や施工ミス、納期遅延が発生すれば、顧客や会社から厳しく責任を問われることも珍しくありません。
また、現場では年上の職人や協力会社のスタッフと信頼関係を築き、指示を出さなければならず、人間関係のストレスもつきまといます。
これらの精神的負荷により、「やめたい」と感じる人が一定数存在するのが実情です。
3. 人手不足による過重労働
建設業界は少子高齢化の影響で技術者・職人の減少が進み、現場監督への負担が増大しています。
特に中小企業や地方の現場では、監督が現場対応だけでなく、写真整理・工程表作成・発注業務・行政対応など、幅広い業務を一手に担うケースも少なくありません。
その結果、長時間労働や休日出勤が常態化し、心身の負荷から離職に至る人も多くいます。
人手不足が解消されない限り、構造的な負担軽減は難しいのが現状です。
4. 給与が見合わないと感じる声もある
現場監督の平均年収は、国土交通省や各種求人情報によると約450万〜600万円前後とされており、日本の給与所得者の平均年収よりも高く設定されています。
しかし、業務の負担や労働時間を考慮すると「割に合わない」と感じる声もあります。
特に20代〜30代前半の若手や、施工管理技士の資格を持たない人は年収が400万円を下回ることもあり、生活費や家庭との両立に不安を抱く人も多いです。
業務内容と報酬のバランスが不公平に感じられることが、「やめとけ」と言われる理由の一つとなっているようです。
出典:建設業における賃金等の状況について|国土交通省、
出典:建築施工管理技術者 - 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)
やめとけと言われる現場監督!働くメリットや大きなやりがいがある

一部では「やめとけ」と言われている現場監督ですが、実際にはキャリアの成長や社会的なやりがいを感じられる、魅力的な職種でもあります。
たとえば、「若いうちから責任ある立場を経験できる」「国家資格の取得によってキャリアの安定性が高まる」「大規模な社会インフラに関われる達成感」といった点は、他職種では得難いメリットだと言えるでしょう。
ここでは、現場監督だからこそ得られる代表的な利点を具体的に紹介します。
若いうちからマネジメント経験が積める
現場監督は、入社後数年で職人や協力会社をまとめる「現場の司令塔」としての役割を担います。
現場の規模にもよりますが、数人〜数十人規模の人員を動かす経験を20代のうちから積むことができ、コミュニケーション能力・調整力・リーダーシップが実践を通じて身につきます。
このマネジメント経験は、建設業界にとどまらず、不動産管理、施設運営、PM(プロジェクトマネジメント)職など、他業種への転職においても高く評価される重要なスキルだといえます。
国家資格取得でキャリアの安定につながる
現場監督の実務経験を積むことで、国土交通省認定の「1級・2級施工管理技士」などの国家資格の受験資格を得られます。
とくに1級施工管理技士は、公共工事や大規模案件における監理技術者としての登録が可能で、業界内での評価が非常に高い資格です。
資格取得により、資格手当の支給や昇進の条件を満たすケースも多く、転職市場でも貴重な存在として評価されやすくなります。
人材不足が続く建設業界において、資格保有者のニーズは今後も継続すると見込まれています。
大規模プロジェクトに関われるやりがい
現場監督の仕事の醍醐味のひとつは、道路・橋・病院・高層ビル・ショッピングモールなど、地域のランドマークとなる建物やインフラの建設に携われることです。
設計段階から施工完了まで、一貫してプロジェクトに関与することで、竣工時の達成感や社会への貢献意識を強く感じられます。
「この建物は自分が現場を仕切って完成させた」という誇りは、一生のキャリアのなかでも大きな支えになるでしょう。
実際に現場監督として働く人の声

現場監督の仕事には、実際に経験してみないとわからないリアルな一面があります。
社員や元社員の口コミサイトや建設業界の掲示板、SNSなどでは、ポジティブな意見とネガティブな意見がはっきりと分かれており、仕事の魅力と厳しさが同時に存在していることが伝わってきます。
ここでは、現場で働く人のリアルな声を参考に、現場監督としてのやりがいや悩みについて紹介します。
また、大手ゼネコンと中堅・中小ゼネコンの違いにも触れ、キャリア選択の参考になる情報をまとめました。
【ポジティブな意見】やりがい・スキルを得られる
前向きな意見として多く見られるのは、「やりがいの大きさ」と「スキルの幅広さ」です。
自分が携わった建物やインフラが完成し、地図に残る成果となったときには、言葉にできない達成感と誇りを感じるという声が多数あります。
また、現場監督は工程・品質・安全・コストといった多岐にわたる管理を行うため、若いうちから総合的な現場マネジメント力が身につきます。
こうした経験は、施工管理技士資格の取得や将来的なキャリアアップにも直結するため、「厳しい環境の中で確実に成長できる職種」と捉える人も多いようです。
【ネガティブな意見】長時間労働・人間関係のストレス
働く上での悩みとして頻繁に挙げられるのが「長時間労働」と「人間関係のストレス」です。
特に工期が迫ると、早朝から夜遅くまでの勤務や休日出勤が常態化し、プライベートの時間がほとんど取れないという声が目立ちます。
また、現場では年上の職人や協力会社のスタッフと連携しながら作業を進める必要があり、若手の現場監督にとっては「年上への指示の出し方」「板挟みでの調整」が大きなプレッシャーになることもあります。こうした環境に疲弊し、転職や異業種への移行を考える人も少なくありません。
大手ゼネコンと中堅ゼネコンの違い
実際の口コミを見てみると、大手ゼネコンと中堅・中小の建設会社とでは、働き方や待遇に明確な違いがあることがわかります。
大手ゼネコンでは、給与や福利厚生、研修制度が充実しており、大規模プロジェクトに携われる魅力があります。
一方で、役割分担の細かさから「十分なスキルが身についていないのでは」と不安を抱く人もいるようです。
中堅・中小ゼネコンでは、地域密着型で転勤が少なく、現場の裁量が大きいケースが多い反面、人的リソースが不足しやすく、1人当たりの業務負担が重くなる傾向にあります。
どちらの環境が自分に合っているかを見極めることが、長く働き続けるうえで非常に重要です。
入社前には、企業の業務体制や配属地域、キャリアパスの実例などをしっかり確認しておくと良いでしょう。
現場監督と2024年問題|残業規制がもたらす働き方の変化
2024年4月から、建設業にも罰則付きの時間外労働の上限規制が適用され、いわゆる「2024年問題」として現場監督の働き方にダイレクトに影響しています。
これにより、企業は休日の確保や長時間労働の是正を本格的に進めざるを得なくなり、現場監督の負担軽減や労働環境の改善が期待されています。
しかし、工期や人手不足が解消されないままでは、サービス残業や持ち帰り仕事につながるリスクも指摘されています。
そのため、転職や就職を考える際には、企業がICT施工や人員体制の強化など、具体的にどのような改革を進めているかを見極めることが重要です。
現場監督はやめとけばよかったと感じたときの選択肢

現場監督として働く中で、「自分には合わない」「このまま続けてよいのか」と迷う瞬間は珍しくありません。
重要なのは、無理に我慢を重ねるのではなく、キャリアの選択肢を冷静に見つめ直すことです。
たとえば、部署異動による環境改善や、資格を活かした職種転換、さらには異業界への挑戦など現場監督者として培った経験は多彩な道へつながっています。以下では、代表的な3つの選択肢を紹介します。
部署異動や転職でのキャリアチェンジ
同じ会社の中でも、建築施工から土木、設備、リニューアル部門などへ部署異動できるケースがあります。
仕事内容や担当フェーズが変わることで、業務負荷や働き方が大きく改善される可能性があります。
また、転職によって、大手ゼネコンから中堅・地域密着型企業に移ることで、勤務エリアの固定や業務量の軽減を実現できるケースもあります。
まずは社内外の選択肢を比較し、自分に合ったポジションへのシフトを検討することが、現実的かつ前向きな選択だと言えるでしょう。
資格を活かして建設コンサル・設備管理へ
施工管理技士などの国家資格や現場経験は、建設コンサルタントや設備管理といった職種でも高く評価されます。
たとえば、建設コンサルでは設計補助や施工計画の立案が主な業務となり、体力的な負担を抑えながら働ける環境が整っている場合もあります。
また、病院・商業施設などの設備管理では、施工経験が設備更新・保全の現場で即戦力として活かせます。
「現場から離れても建設業界でキャリアを活かしたい」という方には、有力な選択肢の一つです。
施工管理経験を強みにできる他業界
現場監督として培った「工程管理」「予算管理」「リスク対応」などのスキルは、異業界でも高い汎用性があります。
たとえば製造業の生産管理、不動産開発のPM職、物流やIT業界のプロジェクトマネージャーなど、施工管理の経験は“現場を動かす力”として評価されやすい傾向にあります。
転職=マイナスではなく、施工管理という専門性をベースに、新たな領域でキャリアを再構築するチャンスと捉えることが重要です。
現場監督に向いている人・向いていない人
現場監督は、誰にでも適しているわけではありません。適性によって仕事の捉え方や続けやすさに大きな差が出る職種です。
向いている人は現場でスムーズに能力を発揮でき、やりがいを感じながらキャリアを築いていけますが、向いていない人は心身ともに早期に疲弊してしまうリスクがあります。
ここでは、その違いを明らかにしながら、自分の性格や強みがどちらに近いかを見極めるコツについて解説します。
【向いている人】リーダーシップ・体力・調整力がある
現場監督は、数十人規模の職人や協力会社を取りまとめ、工程・安全・品質のすべてを管理する立場です。
そのため、リーダーシップを発揮できる人や、周囲との信頼関係を築きながら調整役を担える人が向いています。
また、炎天下や冬季の現場作業、長時間の立ち仕事などもあるため、一定の体力や気力も求められます。
「人と関わりながら現場を動かすのが得意」「段取りや進行管理が好き」という人は、現場監督として活躍できる素養を持っていると言えるでしょう。
【向いていない人】長時間労働が苦手・精神的に追い込まれやすい
一方で、長時間労働に強いストレスを感じる人や、突発的なトラブルで精神的に追い込まれやすい人は、現場監督の業務に適応しづらい可能性があります。
建設現場では「図面通りにいかない」「予定が崩れる」「予期せぬ事態が起きる」といった事態が日常的に起こります。
そのたびに臨機応変な対応が求められ、職人・発注者・上司の板挟みになることも少なくありません。
自分のストレス耐性や状況対応力を客観的に見つめ、「続けられるか」「向いているか」を冷静に判断することが重要です。
現場監督からのキャリアパス・転職先の選択肢
現場監督として培った経験は、建設業界内外でさまざまなキャリアに活かせます。
施工管理技士や建築士などの資格を取得すれば、大手ゼネコンやハウスメーカーでの昇進や大型案件への抜擢も可能です。
また、建設コンサルタントや不動産ディベロッパー、施設管理なども実務経験が評価される分野です。
さらに、工程管理やマネジメント力を武器に、製造業やIT業界のプロジェクトマネージャーへ転職する人もいます。
現場監督の仕事で身につく調整力や問題解決力は、業界を超えて通用する普遍的なスキルです。転職はキャリアの後退ではなく、強みを活かす新たな挑戦の場とも言えるでしょう。
現場監督として働くならホワイト企業を選ぼう
同じ現場監督でも、企業によって働きやすさは大きく異なります。
長時間労働や休日出勤が常態化している企業もあれば、働き方改革を進め、週休2日制や残業削減に取り組む「ホワイト企業」も増えています。
なかでも、国土交通省の「建設業働き方改革加速化プログラム」に参加している企業は、ICT施工や休日確保に積極的で、比較的良好な労働環境が整っています。
転職活動では、求人票だけでなく平均残業時間や離職率、有給取得率などを確認し、可能であれば口コミサイトやOB訪問も活用しましょう。
現場監督としてキャリアを長く続けるには、「どこで働くか」が重要な判断軸になります。
現場監督の働き方に関するよくある質問
現場監督を目指している方のなかには、「年収が低いって本当?」「施工管理技士の資格は必要?」「女性や未経験でも現場監督になれる?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、現場監督の働き方に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。以下の中に気になる項目があればぜひチェックして、疑問や不安を解消しましょう。
Q1:現場監督の年収は本当に低いの?
現場監督(施工管理職)の平均年収は約596万円と、日本の全体平均(約460万円)を大きく上回っています。
ただし、労働時間の長さや業務負荷の高さから、「年収の割に見合わない」と感じる人が多いのも事実です。
出典:建設業における賃金等の状況について|国土交通省、
出典:建築施工管理技術者 - 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)
Q2:現場監督をやめて転職する人は多い?
建設業における新卒入職者の3年以内の離職率は、大卒で約3割、高卒では約4割〜5割と高めで、ここ10年以上横ばい傾向にあります。
これは全産業平均と比べてもやや高水準です。特に高卒者の離職率は製造業よりも約15%、大卒者では約10%ほど高く、他業種に比べて若手の定着が難しいのが特徴です。
背景には長時間労働や休日の少なさ、人間関係の負担といった要因があり、現場監督を含む施工管理職に強く表れています。
そのため「やめとけ」と言われる理由の一つに、若手が長続きしにくい実態があるといえるでしょう。
Q3:施工管理技士の資格を持っていると有利?
1級・2級施工管理技士は、給与に反映される資格手当や、転職・昇進時の評価を得やすい国家資格です。
将来のキャリア形成を見据えるうえで、取得しておいて損はありません。
Q4:女性や未経験でも現場監督になれる?
女性や未経験でも現場監督になれます。近年は女性の現場監督も増加傾向にあり、建設業界全体でも多様性が進んでいます。
また、未経験者でも研修制度やOJT(現場教育)を通じて、少しずつスキルを習得できる環境が整いつつあります。
Q5:現場監督に将来性はあるの?
現場監督に将来性はあります。建設業界では深刻な人手不足が続いており、施工管理職の需要は今後も高まると見込まれています。
さらに、ICT施工や働き方改革の浸透によって、働き方の改善も進みつつあるため、今後の展望は明るいと言えます。
Q6:現場監督が辞める理由は何ですか?
現場監督が辞める主な理由は「長時間労働」「人手不足による過重負担」「責任の重さ」「給与が見合わないこと」などです。
特に若手は、年上職人との人間関係や休日の取りにくさから疲弊しやすく、心身の不調や将来への不安から転職に至るケースが多く見られます。
Q7:建設業で一番きつい仕事は何ですか?
「施工管理(現場監督)」が最もきつい職種の一つとされます。
早朝の準備や日中の現場対応、終業後の書類業務などで拘束時間が長く、職人よりも労働時間が長くなりがちです。責任の重さや休みの取りづらさも負担の一因です。
Q8:35歳の現場監督の年収はいくらですか?
会社規模や資格によって異なりますが、35歳の施工管理職の平均年収は約550万〜650万円が目安です。
大手ゼネコンで1級施工管理技士を保有していれば700万円超も可能ですが、中小企業では500万円台にとどまる場合もあります。
出典:建築施工管理技術者 - 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)
まとめ
現場監督という仕事は、責任の重さや長時間労働、人手不足などの課題から「やめとけ」と言われることもあります。
しかしながら、その一方で高い専門性や社会的意義を持ち、やりがいや成長機会も多い仕事です。近年は働き方改革やICT導入による改善の動きも見られ、少しずつ環境が変わりつつあります。
大切なのは、「合わない」と感じたときに無理をせず、部署異動・転職・異業界チャレンジなどの道を含めて、自分に合ったキャリアを見極めることです。
現場監督としての経験は、建設業界内外で通用する確かなスキルであり、決して無駄にはなりません。
未来の選択肢を広げるためにも、今の経験をどう活かすかを前向きに考えていきましょう。
建設業界に特化した転職支援サービスを提供する『ベスキャリ建設』では、プロのキャリアアドバイザーによる無料相談を実施しています。
キャリアに関する不安やお悩みがあればぜひご相談ください。お悩みや理想の働き方を丁寧にヒアリングしたうえで、あなたにぴったりな職場をご提案いたします。
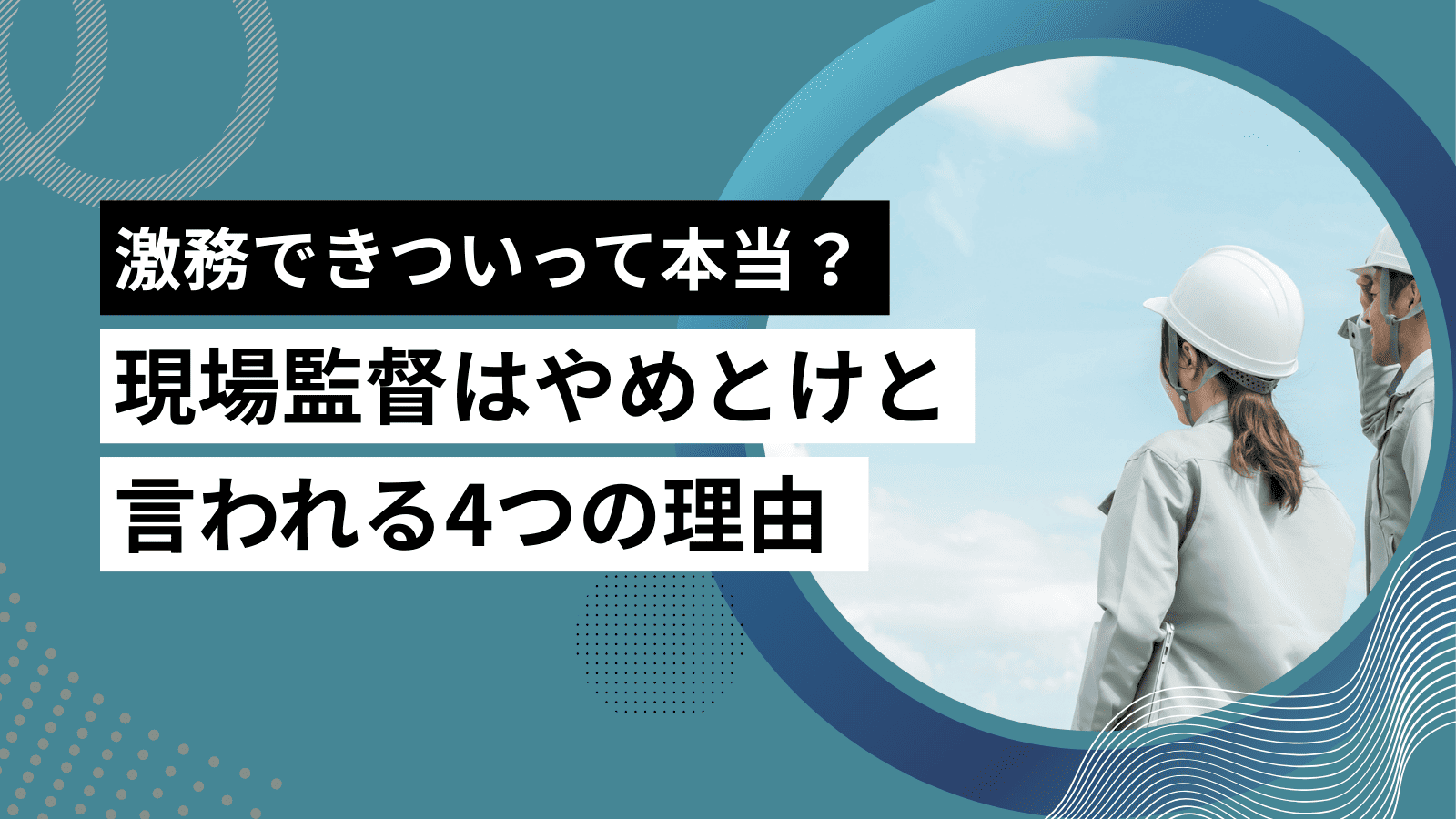


_180x98.png)

















.jpeg)


