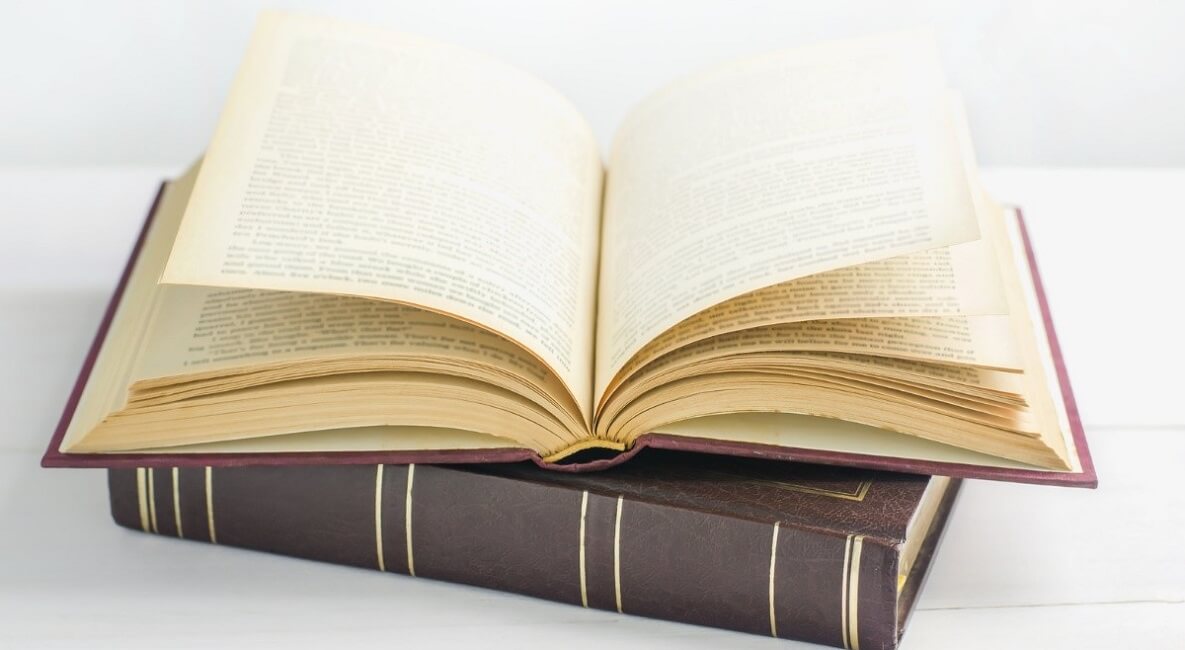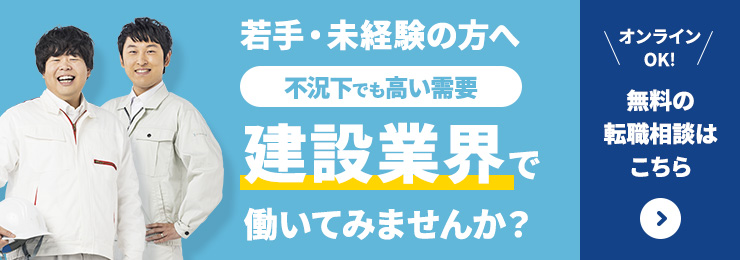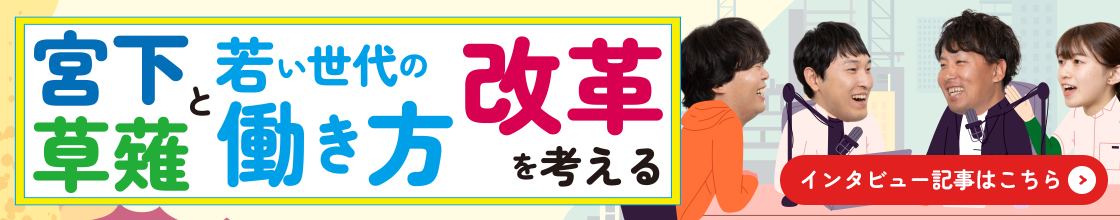■施行管理職に就くなら知っておきたい基礎用語集
業界未経験の人が建設業界へ飛び込むとき、専門用語が飛び交っていてついていけないということも考えられます。もちろん、工業高校や専修学校、大学で学んだ人でもいざ仕事に就くと学んだ知識を仕事に紐づけることができないと悩むこともあるでしょう。
専門用語を覚えておくことで、「この業務にはこの作業が必要だ」というように仕事自体のプロセスを覚えるきっかけにもなります。基本中の基本ともいえる基礎用語を11個解説いたします。
これだけ覚えれば万全ということではありませんが、頻出単語ですので少しずつ覚えていきましょう。
●施工管理の求人情報を探す
> 建築施工管理 > 土木施工管理 > 電気施工管理 > 空調衛生施工管理
◇知っておきたい施行管理の用語①『施工管理技士施工管理基準』
国交省や自治体が定めるものです。簡単に「管理基準」と呼ばれることもあります。工事の施工に欠かせない建設会社や下請け業者が守るべきマニュアルといった体裁で、発注した工事を滞りなく進めるとともに、受注業者と下請け業者はそれを遵守した施工を心掛けなければいけません。
一般的に、施工管理技士施工管理基準は土木や建築など様々な分野で詳細に定められており、自治体ごとにスタンダードが決められています。
公共工事を受注する場合は、その自治体が提示する管理基準を確認する必要があります。
◇知っておきたい施行管理の用語②『施工計画書』
施工計画書は、受注した公共工事や一般工事において、基本情報から使用機械、採用資材などの情報のほか、安全管理、緊急時の対応や周辺環境への配慮などを書面に記したものです。これによって、企業独自の工法などをわかりやすくクライアントへ提示できます。
一部の自治体では統一書式を準備し公共工事の施工を可視化しています。この公共工事の場合、施工請負業者が施工計画書を速やかに提出し、受理されなければ工事に着手できないので注意が必要です。不備があればその分だけ着工が遅れることになります。
◇知っておきたい施行管理の用語③『工事完成保証人』
工事を請け負った場合は、請負業者があらかじめ資材や機械などを調達し、それらにかかる費用を立て替えることが一般的です。会社の体質や工事の規模によって、会社の財政が破綻し、工事を続行できなくなる場合もあります。実際このようなことがないよう、発注者(主に公共工事)側も経営事項審査の結果などを把握したうえで発注業者を見極めます。
もし、その企業の財政事情から工事が続行できなくなった場合、別の建設会社が請負った企業に代わって工事を完成させなければいけません。その企業を「工事完成保証人」といいます。
工事完成保証人となった建設会社は共倒れのリスクも背負います。今では、建設業保証株式会社が新しい履行保証制度を提示し、公共工事をバトンタッチする工事完成保証人に対し金銭的補償を行います。請負企業は1工事ごとに契約保証等を締結しなければ、公共工事を受注できない流れになっています。
◇知っておきたい施行管理の用語④『現場代理人』
工事現場において、現場監督の役割を担う監理技術者や主任技術者を配置する義務があります。その有資格者は請負業者の正社員とし、1級ないし2級施工管理技士の資格が必要になります。請負金額に応じ主任技術者の配置も認められています。
時折出てくるのが「現場代理人」の存在です。現場監督の業務とほぼ同じ仕事を担いますが、一般的には現場監督の統括的な存在となり、現場監督の業務として課されていない工事現場の取り締まりや、請負代金の受領や請求に関する業務を担います。監理としては業務内容も難しいものとなるため、位置づけとしては現場監督の上司といった見方がなされています。
◇知っておきたい施行管理⑤『QCDSE』
・Quality(品質)
・Cost(原価)
・Delivery(工期)
・Safety(安全)
・Environment(環境)
これら、施工管理を行う上で重視される5つの要素の頭文字をとった造語です。ここまで読み進められた方はお気づきのことでしょう。施工計画書で網羅すべき要素でもあります。
一般的なビジネスシーンや製造業では「QCD」がよく言われていますが、建設業では安全性や環境の確保も課題として受け止めなければいけません。施工管理の基本としてまずはこの要素を覚えましょう。
◇知っておきたい施行管理の用語⑥『施工管理基準』
「施行管理の用語1.施工管理技士施工管理基準」を参照
「管理基準」「施工管理基準」または「基準」などと呼ばれることもあります。地域によって定められる施工管理基準は異なります。複数の自治体の公共工事を請け負う場合、施工管理者が施工計画書の作成などにおいてそれぞれの施工管理基準に沿った内容であることが基本となります。
◇知っておきたい施行管理の用語⑦『3K仕事』
用語、というよりもほぼスラングとなります。3Kというと「きつい・汚い・危険」といういわれがあります。建設業もこれが当てはまることでしょう。昨今では行き届いた施工管理によって、安全衛生の意識向上や、作業員にとって無理のないスケジュールが組まれるようになりました。
このところでは建設業で働く人は「カッコイイ・稼げる・結構モテる」という新3Kが常識になりつつあります。
このような意識改革も、施工管理職の努力のたまものといえるでしょう。
◇知っておきたい施行管理の用語⑧『施工管理技士』
施工管理の仕事は無資格でもできますが、工事現場の監督や、建設業の専任技術者として届け出る場合は「施工管理技士」という国家資格必要になります。施工管理技士には1級・2級の種別がありますが、特定建設業の監理技術者や専任技術者となる場合は建設業を届け出る業種の1級施工管理技士の資格が必要になります(2級は一般建設業のみ)。
勉強をしたから取得できる資格ではなく、受験には実務経験が必要です。キャリアパスの中で施工管理技士の取得を目指す場合は、学歴と実務経験年数に注意が必要です。
◇知っておきたい施行管理の用語⑨.施工管理でよく使われる道具の名前
一般的には「QC7つ道具」などといわれるようです。品質チェックや、改善検討の際に用いる書類やデータがあげられます。
・特性要因図
・チェックシート
・散布図
・パレート図
・ヒストグラム
・グラフ
・管理図
原因解析と実践や分析に役立つツールであり、QC7つ道具のデータとともに層別と呼ばれる5MET(人・設備/システム・手順・材料・測定方法・環境の頭文字の略)の項目を重ねて状況の整理を行っていきます。
◇知っておきたい施行管理の用語⑩『液状化現象』
砂地などの地盤の場合、地震などの振動により地下水の圧力が高まり、これまで結びつき支えあってきた砂の粒子が地下水に浮かび上がった状態になることを「液状化現象」といいます。液状化現象によって水よりも比重が重い建物が倒壊や傾倒するほか、マンホールが浮き上がるなどという事故も考えられます。
液状化現象が懸念される土地に対しては、造成時に液状化対策を検討する必要があります。液状化現象が引き起こされた場合、人的被害もさることながら、経済的な被害も大きいと考えられます。もちろん液状化現状自体は天災の一つですが、地盤の事前調査は重要だといえるでしょう。
◇知っておきたい施行管理の用語⑪『水循環基本法』
2014年に制定された法律です。水は循環されるものであることを意識づけるもので、水を大切に使うことはもちろん、適切な水処理を行い川や海へ戻すことで、生態系を守ることや産業や文化の発展・生活の安定を目指すものです
施工管理の立場では、プラント(工場)や商業施設を建設するほか、水循環システムを採用した施設を建築する際に意識する法律となるでしょう。勤務先においても雨水を水洗トイレの洗浄水に使う方法を構築するなど何らかの対策を講じてみることも一案です。
■まとめ
駆け出し施工管理者が覚えておくと便利な用語を紹介しました。施工管理の仕事は多岐にわたるため、なかなか自分自身の守備範囲がとらえきれていないという新人さんもいるかもしれません。先輩施工管理技士さんに教えてもらいながら、建設工事の要でもある施工管理の仕事を覚えていきましょう。