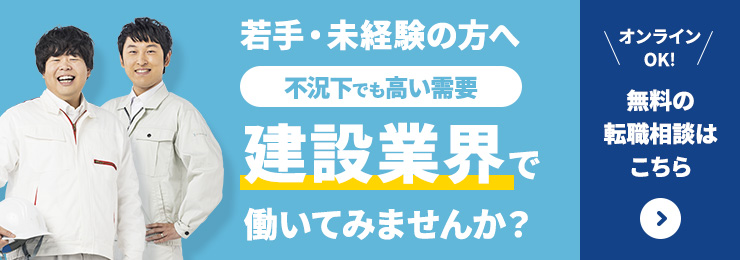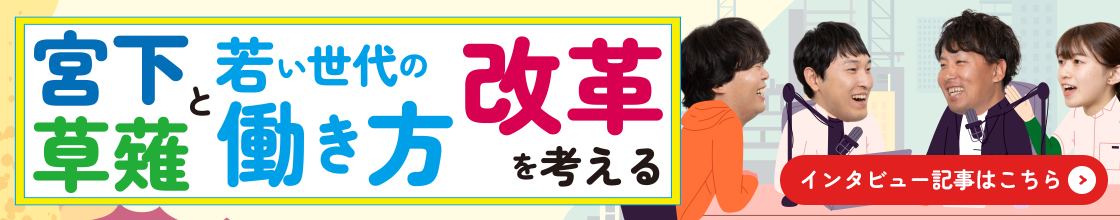建物やインフラ整備を手がける建設業界は、人々の暮らしに欠かせない基幹産業の一つです。建築を学ぶ学生はもちろん、異業種からの転職で建設業界を目指す方も多いでしょう。建設業界で働くのであれば、最低限の基本用語は押さえておく必要があります。今回は建設業界の基本用語を理解する重要性と、押さえておきたい基本用語について解説します。
■建設業界の基本用語を覚えておくメリット
どうして建設業界で働く前に基本用語を勉強する必要があるのか、疑問に思う方もいるでしょう。基本用語を覚えておくと、業界研究がしやすくなるメリットがあるのです。
業界研究の目的は、建設業界の基本的な仕組み、企業の特長や業績、建設業界の動向などを把握して、建設会社を選ぶ判断材料をより多く持つことです。入社前後のギャップを埋めることで、建設業界でより良い4ができるようになります。
基本用語は建設業界の業務に直結しているので、具体的な業務内容を把握することも可能です。
■建設業界で働くうえで押さえておきたい基本用語
建設業界について学ぶうえで、必ず押さえておきたい基本用語は以下のとおりです。業界研究と業務に役立つので、建設業界を目指す方は参考にしてください。
◇アスベスト
アスベスト(石綿)とは、天然の繊維状けい酸塩鉱物です。
保温断熱を目的とした建物内の吹き付けや、スレート材、防音材、断熱材など、建材製品に多く使用されていました。しかし、建物を解体する際に飛散したアスベストを長期間吸引すると、じん肺(肺線維症)や悪性中皮腫、肺がんなどの病気を発症するリスクが高くなります。
アスベストを使用した建物を解体する場合、飛散させない封じ込め・囲い込みの措置を取ることが建築基準法で定められています。
◇内法
内法(うちのり)は寸法の用語で、対面する2つの部材の「内側から内側」までの距離を指します。柱と柱の間、窓、出入り口の幅、床面積を測る際によく用いられます。また、外側と外側の寸法を示す外法も、建設業界でよく使われる用語です。
◇液状化現象
液状化現象とは、地震により地盤が液体状する現象です。液状化が起きやすい地盤は、埋め立て地や河口付近などに多い、ゆるく堆積した砂地盤といわれています。
砂質土の地盤は砂の粒のすき間を地下水が満たして地盤を支えています。地震が起きると地下水の圧力が高くなり、砂の粒が地下水の中で浮き上がります。地震が収まると砂の粒は地下水と分離して沈下し、地盤の亀裂や沈下を起こします。
液状化現象が起きると地上の建物や電柱などが傾いたり、地下の水道管などが地上に浮き上がり断水したりするのが特徴です。東日本大震災でも見られた、マンホールが浮き上がる現象は液状化現象のメカニズムによるものです。
◇外構工事
外構工事とは、建築物以外の外回りの工事のことです。コンクリートやアスファルトの舗装、駐車場の整備、トイレや雨水などの排水工事、植栽工事など、業務内容はさまざまです。
トイレなどの排水計画は工事に着手する前に準備しますが、外構工事のほとんどは建築物の完成後に着手するのが一般的です。工期最後の業務になるので、スピードとパワーが要求されるのが特徴です。
◇基礎
基礎とは、建築物や土木構造物の土台になる部分です。建築物を安定させるため、建設地の地盤調査をおこなった後、基礎工事に移るのが基本的な流れです。日本は地震の発生数が多いので、基礎工事では地中深いところにある固い地盤に届くように杭を打つ工法が活用されています。
◇隣地境界線
接地境界線とは、隣接する2つの土地の境を示す線のことで、隣の土地の境界標(目印)と、他の境界標を結んだ線を指します。
境界標には杭や鋲などを用いますが、境界標がないケースも少なくありません。通常は境界線上に塀や垣根、擁壁などが設置されていますが、それらが必ずしも接地境界線と重なるとは限らないので注意が必要です。
◇採光
採光とは、外の自然光を窓などから室内に採り入れることです。建築基準法では、居室には一定の自然光を取り入れる設計が義務付けられてます。それを「有効採光面積」と言いますが、住宅の場合、居室の床面積の1/7以上の広さが必要になります。
採光が必要な居室はリビングや寝室など、常時生活する空間部分で、トイレやキッチン、洗面所、納戸などは除外されます。
◇在来工法
在来工法とは、柱と梁を組み合わせて建物を建てる、日本に古くからある工法です。木材を組み合わせることから、「木造軸組構法」と呼ばれることもあります。
在来工法には、日本の気候風土に適している、間取りを自由に変えられるなどの特長があり、リフォームにも適しています。