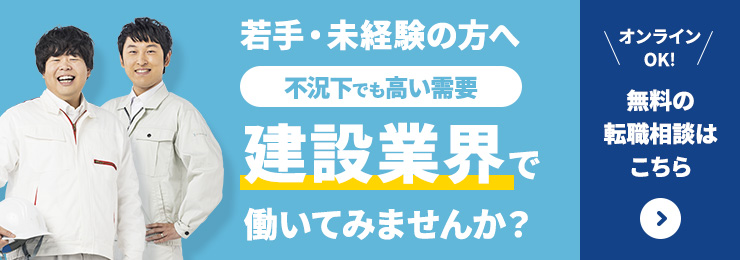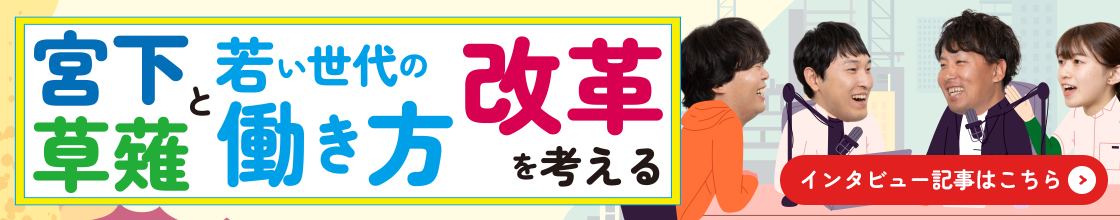橋や道路、ダムといった、人々の生活を支える設備を造るのが土木工事の仕事です。しかし、建設業界でよく耳にする「建築」と何が違うのか、よく知らない方が多いかもしれません。今回は、土木工事の仕事内容と将来性、土木工事で働く際に必要な専門用語について解説します。
■土木工事ってどんな仕事?
土木工事の仕事内容と将来性について紹介します。
◇土木工事の仕事範囲
土木工事で作る構造物は、道路をはじめ、ダムやトンネル、橋梁、鉄道、河川、空港建設、上下水道の配管工事、土地区画整理など多岐にわたります。土木工事は先進国の象徴といわれるほど、高度な技術とスキル、最先端技術が必要な工事です。
建設は土木や建築などの分野があり、住居やビル、学校、病院といった、人々が利用する空間をつくることを建築工事といいます。
◇土木工事の将来性
土木工事は街作りやインフラ整備に関わるため、社会生活を送るうえで欠かせません。景気や情勢に左右されることがなく、安定した仕事が長く見込まれるでしょう。
橋やダムなど、大がかりな構造物を造る土木工事は、国や都道府県が発注する公共工事が大半を占めます。令和2年度の国土交通省の予算における公共事業費は5兆円と膨大な額から見ても、土木工事は簡単に仕事がなくならない、将来性のある仕事といえるでしょう。
■土木工事の現場で知っておきたい専門用語
土木工事に携わる場合、次に挙げる専門用語を把握しておきましょう。
◇インフラ
産業や社会生活の基盤となる設備や施設のことです。道路や鉄道、上下水道など、土木工事の仕事と密接に関係しています。
◇アメニティ
本来は「快適さ」を意味していますが、土木工事においては「街並み」や「街の雰囲気や環境」という意味として、主に都市計画の分野で使われます。
◇ヒートアイランド現象
郊外に比べ、都市部の気温が高くなる現象のことです。
都市部に起こる理由は、緑地や河川の減少、熱を溜め込むアスファルトやコンクリートの影響、自動車やエアコンの室外機の熱気、密集したビルによる風通しの悪さなどです。ヒートアイランド現象が進行することにより、熱帯夜や熱中症の増加、集中豪雨など、さまざま影響が懸念されます。
◇疲労破壊
構造物の材料が、静的強度より小さな負荷を継続的に受けることによって破壊されていく現象のことです。コンクリートの構造物での疲労現象は、繰り返される負荷によって鋼材にひび割れや亀裂が生じ、結果的に鋼材の性能が低下することで起こります。疲労破壊が起きるのは、鉄筋コンクリート板、はり部材が挙げられます。
◇供用性能と供用性
供用性能は、路面や舗装の性能を表す概念のことです。一方、供用性は供用性能が時間が経つにつれて低下する概念を指します。この概念は、経年劣化と荷重でダメージを受ける、道路舗装で用いられます。
◇ライフサイクルコスト
建物や橋などの構造物の建設から、役目を終えるまでにかかるトータルの費用のことです。土木工事で言うと、企画と設計、工事、完成後の運用、修繕、解体までかかるすべての費用を指します。
建設においては、構造物の完成までにかかる費用(イニシャルコスト)よりも、運用や修繕など使い続けるための費用(ランニングコスト)のほうが3~4倍もかかるといわれています。
◇川表と川裏
堤防のある河川で、水が流れているほうを川表(堤防から見た河川側)、住居や農地があって水が流れていないほうを川裏といいます。堤防に関する専門用語の一つで、河川の土木工事で用いられます。
◇アーチダム
V字型の地形に適したアーチ状のダムのことです。アーチ状にすることで水圧を岸壁に分散します。丈夫な岩盤が必要ですが、ダムの厚さを薄くできるので、材料が少なく済むメリットがあります。