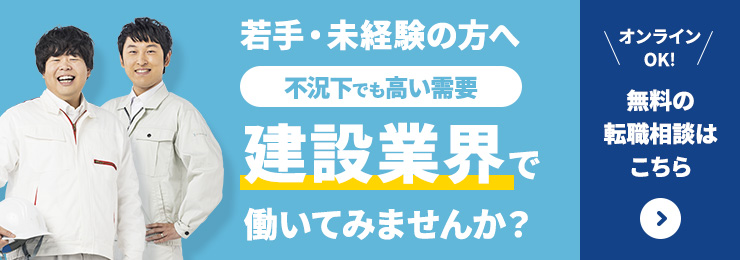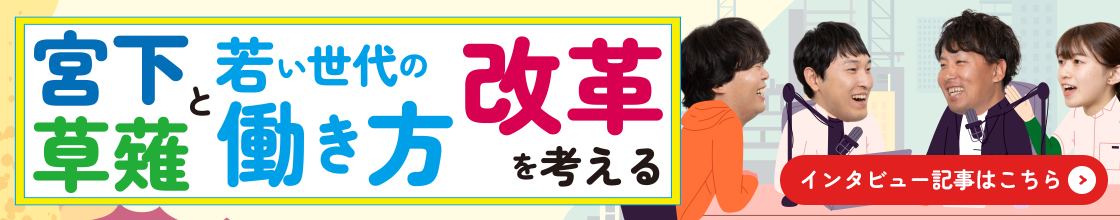電気工事の仕事は、生活に欠かせない電気を供給する重要な役割を持ちます。しかし、電気工事は具体的にどのような作業をするのか、ほとんど知らない方も多いはずです。
電気工事の仕事に携わる場合、電気工事の種類と作業内容、専門用語は知っておく必要があります。今回は、電気工事現場の概要と、電気工事の現場で使われる専門用語について解説していきます。
■電気工事現場ではどんな作業をするの?
電気工事の現場で行う作業は、鉄道電気工事と建設電気工事の2つに分けられます。
鉄道電気工事は、鉄道を安全に運行する陰の立役者です。鉄道に電気を送る架線や発電所、変電所に加え、安全を守る信号システムや踏切、駅の自動改札機や通信設備といった電気設備の工事や保守業務に携わります。
一方、建設電気工事は、公共施設や工場、病院、商業施設、住宅などの建物に電気を供給する仕事です。変電施設や電線施設のメンテナンス、建物内の電気配線や配電盤の設置、コンセントや照明器具の取り付けなど、業務内容は多岐に渡ります。
また、電気工事の仕事は、現場施工、施工管理、設計にも分けることができます。それぞれの仕事内容と役割は次の通りです。
・ 現場施工…電線やケーブルの配線、配管、ボックスや電気機器の設置など、工事現場で実際に施工する。電気工事の技術者として、施工図を正しく読むスキルが求められる。
・ 施工管理…規模が大きい電気工事の現場で、施工計画を立てる「工程管理」、作業の安全を守る「安全管理」、利益を残す「原価管理」、建物の完成度を高める「品質管理」を行なう。施工管理は作業に携わるのではなく、工事現場全体の監督をする。
・ 設計…電気設備の設置場所、配線のルートなどを、建物の設計図書を決めた後、CADを使って設計図を作成する仕事。必要な電気設備を見極めることに加え、法律や予算、発注者の意図などを考慮して設計する必要がある。
■電気工事の現場で知っておきたい専門用語②
さまざまな作業と仕事内容がある電気設備では、以下の専門用語を使用します。
◇電気工事法
電気工事法とは、電気工事による事故や災害、犯罪を防止のため、昭和35年に制定された法律です。電気工事は一見すると単純そうに見える反面、感電や漏電による火災につながる危険性があります。そのため、電気工事法では、軽微な作業に該当しない「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物(500kw未満)」の作業を制限しています。
◇絶縁体
絶縁体とは、ゴムやビニール、プラスチックといった、電気をほとんど通さない物質のことです。絶縁体で電線の金属部品を覆うことで、触っても感電しなくなります。しかし、絶縁体は完全なものではなく、高い電圧がかかると破壊される可能性があります。
◇接地端子
接地端子とは、コンセントのプラグに配置されている、設置のための端子です。
従来の2本のコンセントに、もう1つの端子や配線が出ている、いわゆる「アース線」を設置端子と呼びます。予期せぬ漏電が起きた際、別のルートに電気を流すことで感電を防ぐ役割があります。
設置端子があるコンセントは、洗濯機や冷蔵庫などの大型家電、漏電の可能性がある水回りの家電、パソコンなどが主流です。
◇電工ナイフ
電工ナイフとは、電線やケーブルを覆う絶縁体の皮むき、電線の割線に使う道具です。電工ナイフは刃が出たまま固定されたタイプと、刃が折りたためるタイプの2種類があります。
◇ピッチ
ピッチとは間隔の意味です。図面にある寸法を施工する際、実際に施工する場所に印をつける「墨出し」のシーンでよく使われます。間隔の距離をセンチやメートルではなく、ピッチという単位として使うイメージです。
◇レベル
レベルとは、高さを意味する言葉です。ピッチと同様に、高さをセンチやメートルから、レベルという単位に替えて使います。コンセントなどを設置する際、地面からの高さを示すのにレベルを使うことが一般的です。
◇配線器具
配線器具とは、電流の受け渡しとなるもので、コンセント、スイッチ、照明関連の器具を指します。複線図や記号はさまざまなものが存在するので、違いを確認しておくようにしましょう。