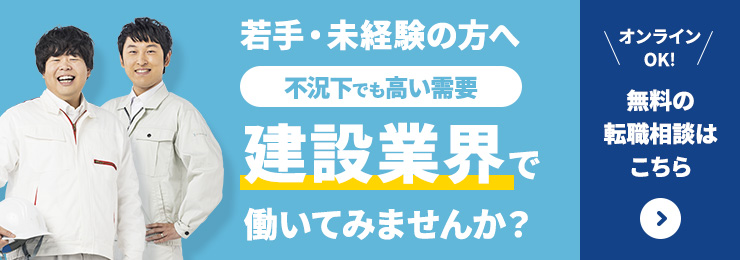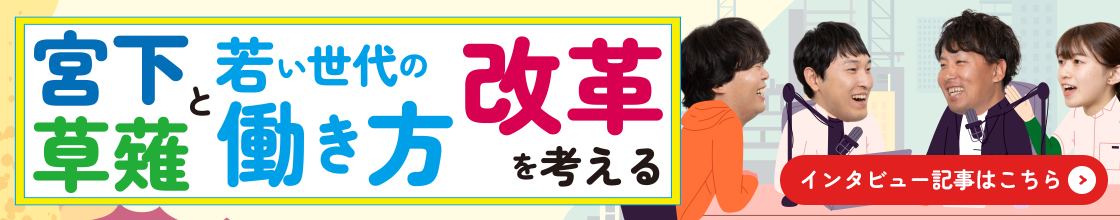電気工事は仕事内容によって3種類に分類され、仕事も役割分担で進めるのが特徴です。はじめて電気工事の仕事に就く場合、電気工事の仕事の進め方と、専門用語を覚えることが必要です。
今回は、電気工事の具体的な仕事内容と、知っておきたい専門用語について解説していきます。
■電気工事の仕事内容
電気工事と一口にいっても、仕事内容で以下の種類に分類されます。
・外線工事…発電所や変電所から電柱に電気を送る工事
・内線工事…コンセントなどを設置して、建物内で電気を供給する工事
・仮設工事…建築中の建物内で一時的に電気を供給する、仮設用の分電盤やコンセントを設置する工事
発電所で作られた電気が建物で使えるようになるまで、3種類の工事が必要になるのです。また、電気工事では「現場施工・施工管理・設計・積算」という役割分担があり、それぞれの役割で仕事内容が異なります。
「現場施工」とは、実際の工事現場において、電線やケーブルの配線、機器や設備、照明の設置などを施工図に従って工事する技能者のことです。現場施工は施工図を正しく読み、施工図どおりに設置するスキルが求められます。
「施工管理」は規模が大きい現場に必要な役割で、施工計画や施工図の作成、工事の工程管理、品質管理、安全管理などの仕事をおこないます。現場施工に携わる技能者の指導・監督、設計者や発注者との打ち合わせなど、工事現場の作業に携わらないのが施工管理の特徴です。
電気工事における「設計」とは、建物の設計図書に基づき、電気設備の設置場所や配線ルートを決める仕事です。
必要な電気設備、法律、予算、発注者の要望などを考慮して設計をおこないます。設計が決まり次第、現場施工に必要な設計図を作成する業務や、現場で設計図どおりに施工されているかを確認して発注者に報告する業務も含まれます。
「積算」とは、電気工事にかかる工事費を算出する作業のことです。設計図から必要な設備や材料の数量、配線や配管の長さを割り出し、施工に必要な労務費などを含めて工事費を算出します。発注者は積算の工事費を参考に発注を決めるため、適切な工事費を算出する経験や感覚が求められます。
■電気工事の現場で知っておきたい専門用語
電気工事の現場でよく使用する、覚えておくと役に立つ専門用語を紹介します。
◇一般用電気工作物
電気工作物は、電気を供給する発電所、住宅などの受電設備の総称です。一般用電気工作物は電気工作物の1種で、住宅や小規模な店舗などで、他の者から600ボルト以下の低圧の電圧で受電する場所の電気工作物のことです。
また、太陽光発電設備や風力発電所、水力発電所などの小出力発電設備も一般用電気工作物に分類されます。
◇三相交流回路
三相交流回路とは、3つの交流回線を組み合わせたものを指します。電気工事の資格である、電験三種の理論科目の基本となります。
三相交流回路の問題では、Yの形に結線するY結線、三角形に結線するΔ結線という方法を用いた電流の計算問題が出題されます。Y‐Y結線の計算、Δ-Δ結線の計算、 Y-Δ結線・Δ-Y結線の相互変換の3つが、三相交流回路の基本の計算です。
◇MIケーブル
MIケーブルは、高温や過酷な環境下でも使用できる、可燃性が低い特殊なケーブルです。電線に使われるケーブルの1種で、主に高温の場所の配線に用います。
◇オームの法則
オームの法則とは、回路の電流の大きさは電圧の大きさに比例し、抵抗に反比例するという関係のことです。式に表すと、「VまたはE(電圧)=R(抵抗)×I(電流)」となります。オームの法則を利用すると、電圧・電流・抵抗の計算が可能です。
◇キャノピースイッチ
キャノピースイッチとは、ひもを引くと電路が開閉するスイッチのことです。照明器具の本体に設置する引きひもスイッチで用いられます。壁に取り付けたひもを引くプルスイッチと異なり、キャノピースイッチは器具の本体に取り付けるのが基本です。
◇コンデンサ(低圧進相コンデンサ)
コンデンサ(低圧進相コンデンサ)とは、電動機の負荷の力率を改善する機器のことです。
電力には仕事をする有効電力と、仕事をしない無効電力が同時に流れています。力率は仕事をしている電力の割合を示すもので、コンデンサを取り付けると力率を100%に近付けることが可能です。力率が改善されると、消費電力が小さくなる、電力設備に余裕ができる、電力損失の低減、電圧の安定といった効果が得られます。
◇圧着端子
圧着端子とは、電線の端末に取り付ける端子のことで、電線を固定する必要がある電気設備や基盤で用います。圧着端子は、裸圧着端子、絶縁ひふく付圧着端子、閉端接続子という種類があり、用途によって使い分けます。