建設業界では、生産性向上や人手不足の解消策として「ICT施工」が注目されています。一方で、「ICT施工を導入することによるデメリットはないのか」「導入が難しいのでは」と不安を抱える方も少なくありません。
特に、建設業界の未経験者やキャリアアップを目指す方にとっては、「ICT施工でどのようなスキルが求められるのか」「仕事の進め方がどう変わるのか」といった実態が気になるところでしょう。
この記事では、ICT施工が現場にもたらす変化、メリット・デメリットに加え、具体的な活用事例、i-Constructionとの関連を最新情報も交えて解説していきます。
建設業界の未来と自身のキャリア形成のために、ICT施工について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
そもそもICT施工とは?
ICT施工は、測量から設計、施工、検査、維持管理に至るまで、建設プロジェクトのあらゆる場面で情報通信技術(ICT)をフル活用し、仕事の進め方そのものを大きく変えようという取り組みです。
ここでは、ICT施工の基本的な知識から、具体的な活用例、必要性まで解説します。
建設現場におけるICT施工とは
ICT施工とは、建設現場で情報通信技術(ICT)を使い、仕事の効率と精度を上げる方法です。ドローン測量や3D設計、GPS連動のICT建機などが活用され、作業時間短縮と品質向上が実現します。
このICT施工は、国土交通省が2016年度から進める「i-Construction」の中心的な取り組みです。
i-Constructionは建設現場の生産性を高め、魅力ある場所にするためのプロジェクトで、ICT技術はその重要な柱の一つです。
ICT施工の例
ICT施工は、測量から設計、施工、維持管理まで、建設の全工程に影響を与えます。技術を導入することで、精度の向上や効率化、コスト削減、安全性の確保が可能です。主な活用例を、工程ごとに表すと下表の通りです。
| ICT活用例 | |
|---|---|
| 測量 | ドローンや3Dレーザースキャナーによる3次元測量、RTK-GNSS測量での高精度な位置情報取得 |
| 設計 | BIM/CIMでの3Dモデル作成と共有、シミュレーションによる干渉チェックや施工ステップ検討 |
| 施工 | ICT建機による丁張りレス施工や施工履歴データの自動収集・管理 |
| 維持管理 | ドローンやロボットによる構造物点検、点検データのデジタル化・分析 |
ICT施工の必要性
ICT施工の導入は、建設業界にとって早急に取り組むべき課題です。最大の理由は、建設技能労働者の減少と高齢化です。国土交通省によれば、技能者の約3割が55歳以上で、若年入職者も不足しています。
ICT技術は少人数でも質の高い建設生産を可能にし、人手不足を補う有力な手段です。また、ICT活用で高精度な施工が実現するため、品質向上にも貢献します。
中でも、3次元データの活用による手戻りの削減は、工期短縮とコスト削減に直結するでしょう。そして、ICT建機やドローンの活用により、労働災害リスクの低減や、作業員の安全の確保が可能になります。
ICT施工のメリット5選
ここでは、ICT施工の代表的なメリットを5つに絞って解説します。
1. 測量や検査の作業時間を大幅に削減できる
ICT施工では、従来2~3人で2~3日かかっていた測量作業が、ドローンやレーザースキャナを活用することで、1人で数時間で完了することも可能です。これにより大幅な省人化・省力化が実現します。
また、UAV測量によって危険な場所への立ち入りを避けることができ、作業者の安全確保にも寄与します。さらに、取得した3次元地形データをもとに、検査工程も効率化され、精度の高い計測結果をスムーズに取得できることもメリットの1つです。
ICT施工による測量・検査の革新は、作業のスピードと安全性の両立を可能にします。ICT施工では、従来複数人で数日かけていた測量作業が、ドローンやレーザースキャナの活用により、1人・数時間で完了できるケースもあります。
UAV測量や3次元スキャニングにより、人が立ち入るには危険な場所の測量も安全に実施可能です。3次元測量データの活用によって、検査業務の精度とスピードも向上するでしょう。
2. 工期を短縮し、生産性を高められる
ICT施工により、マシンガイダンス(MG)やマシンコントロール(MC)を搭載した建機が設計データに基づいて動作するため、丁張りや仕上がり確認の作業を省略できます。これにより現場作業の手戻りが減少し、全体の工期が大きく短縮されます。
実際の事例では、施工日数を平均20%以上削減できたという結果も報告されています。
さらに、ICT建機は進捗のリアルタイム管理が可能で、工程管理も効率化されます。現場の生産性向上とリソース最適化の両立が図れる点は、経営的にも大きなメリットです。
マシンガイダンス(MG)やマシンコントロール(MC)を搭載したICT建機により、丁張り作業や出来形確認が不要となることで、施工全体の日数を大幅に短縮できるでしょう。
3. 高精度な施工が安定して実現できる
ICT施工では、MC(マシンコントロール)機能を搭載した建機を使用することで、設計データに基づいた自動制御が可能になります。これにより、オペレータは大まかな操作を行うだけで、勾配や法面といった高度な整形作業を精度高く仕上げることができます。
人為的な誤差やばらつきを抑えられるため、施工の品質が安定し、やり直しの回数も減少します。また、特に構造物周辺や狭小地といった熟練が必要な場面でも、安定した精度を保つことができる点は、大きな利点といえるでしょう。
MC建機は位置情報や設計データに基づいて自動制御されるため、法面形成や勾配調整などの精度が向上します。人為的な誤差が少なくなるだけでなく、過掘りや仕上がりのばらつきも減少します。
4. 経験の浅い作業員でも対応しやすくなる
ICT施工は、従来は熟練作業者に頼らざるを得なかった複雑な作業も、建機のアシスト機能や自動制御により、経験の浅い作業員でも対応可能となります。これにより、人材不足に悩む建設業界においても、現場の回転率や品質の維持がしやすくなるでしょう。
また、3次元設計データに沿って作業できるため、作業者のスキルによるばらつきが軽減され、教育や指導にかかる負担も削減されます。
ICTの活用は、技能継承の壁を越え、現場力を維持・向上させる手段の一つとして注目されています。ICT施工の導入により、これまで熟練作業者が必須だった工程も、機械によるアシストにより効率よく進められます。
5. 作業員の安全性が大きく向上する
ICT施工の導入により、作業工程の自動化・省力化が進み、危険な現場への立ち入りを最小限に抑えることができます。たとえば、測量や出来形確認をドローンや遠隔システムで行うことで、作業員が重機や危険箇所に近づく必要がなくなります。
また、施工スピードが上がることで、現場の滞在時間が短縮され、事故リスクの低減にもつながります。ICT建機の導入は、安全性を確保しつつ効率化を実現する重要な手段であり、建設現場の環境改善にもつながるでしょう。
作業効率が高まることで、工期に余裕が生まれ、安全対策が講じやすくなる点もメリットの1つです。
さらに、測量や確認作業を遠隔で行えることで、作業員が重機と近接するリスクを軽減できます。ICT施工の導入は、現場でのヒューマンエラーや災害発生率を抑える上でも有効な手段だといえるでしょう。
ICT施工のデメリット・問題点
ICT施工には多くのメリットがありますが、導入にはコスト、通信環境、人材育成といった課題も存在します。
これらのデメリットを正しく理解することで、導入を成功させるための準備や、人材に求められるスキルの方向性が明確になるでしょう。
1. 導入にコストがかかる
ICT施工における最大の課題の一つが、初期導入にかかるコストの高さです。
3次元測量機器、BIM/CIM対応の設計ソフト、ICT建機、ドローンなどの機材は、いずれも従来の施工機器より高額で、数百万円から数千万円、場合によっては億単位の投資が必要になります。
特にICT建機は非常に高価で、導入だけでなくソフトウェアのライセンス料や定期メンテナンス費用も継続的に発生します。こうした費用負担は中小企業にとって重く、導入のハードルとなりがちです。
現状では大手建設会社を中心に導入が進んでおり、中小規模の企業との間で技術格差が拡大することも懸念されています。
導入支援策や補助金の活用、リースや共同利用の仕組みなど、コストを抑える工夫が求められます。
2. 通信状況に左右される
ICT施工の多くは、リアルタイムでのデータ送受信やクラウド連携を前提としています。そのため、安定した通信インフラが現場に整備されていない場合、作業に支障が出ることがあります。
たとえば、GNSS(全地球測位システム)による測位が必要な場面で、山間部・トンネル・高層ビル周辺などでは衛星電波の受信が不安定となり、建機の動作や測量精度に影響が出る可能性があります。
通信が切断されると、ICT機器が本来の性能を発揮できなくなる点も見逃せません。
災害復旧やインフラ整備のような急を要する工事では、通信トラブルによる遅延が大きな問題になります。事前の電波調査や、ポータブルWi-Fi、ローカル5G、スタンドアロン型の測位補正装置などの導入も検討する必要があります。
3. 従業員への研修が必要になる
ICT施工を効果的に活用するには、ICT建機の操作やデータ処理、3次元設計ソフトの取り扱いに対応できる人材が不可欠です。しかし、従来の施工業務とは異なる知識やスキルが求められるため、現場の作業員がすぐに対応するのは難しい場合があります。
年齢層の高い従業員が多い企業では、ICT機器の操作に対する抵抗感もあり、技術習得までに時間がかかるケースも見られます。そのため、体系的な研修プログラムやOJTの充実が重要となります。
また、社内に十分な指導者がいない場合は、外部講師の招へいや新たな人材採用が必要になる可能性もあります。このような教育コストや育成の手間も、企業のICT施工導入における大きな課題の一つです。
4. 運用・保守管理に手間がかかる
ICT施工に用いる機材やソフトは、精密な調整や定期的なバージョン更新、キャリブレーション(校正)などの保守管理が求められます。GNSSアンテナの設置や通信機器の接続、点群データの整理など、ICT機器ならではの運用フローがあり、手間や時間がかかる場面もあります。
また、トラブル発生時に即座に対応できる社内の技術者がいなければ、作業が止まってしまうリスクもあるため、ICT施工を導入する企業には「ICT運用を自立して行える体制づくり」が求められます。
キャリアアップを目指す方へ
プロのキャリアアドバイザーに相談してみませんか?
サイトに公開されていない非公開求人のご相談も行っています。
ICT施工のデメリットへの対策法
ICT施工の導入デメリットは、補助金制度の活用やスモールスタート、人材の育成といった方法で解決が期待できます。
ここでは、ICT施工を導入するときの対策法についてわかりやすく解説します。
補助金や減税制度を活用する
ICT施工の導入にかかるコストを軽減するには、国や自治体の補助金や減税制度の活用が有効です。ICT機器やソフトの購入費、ICT建機を導入する際は、一部の補助や税制優遇を受けられる場合があります。
例えば「ものづくり補助金」は革新的設備投資を支援し、ICT機器導入も対象になる制度です。「IT導入補助金」はITツール導入経費を補助し、BIM/CIMソフト導入に活用できます。
税制面では「中小企業経営強化税制」による即時償却や税額控除、先端設備導入に対する固定資産税軽減措置などがあります。ただし、制度の利用には要件があるため、最新情報を確認しておきましょう。
スモールスタートで始める
ICT施工の全面導入コストや体制変更、人員確保に不安があるなら、段階的に進める「スモールスタート」が推奨されます。
まず導入しやすく効果を実感しやすい範囲から、ICT化に着手し、徐々に適用範囲を広げる方法です。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- ✓ ドローン測量や3Dレーザースキャナーによる現況測量
- ✓ 特定工程のみにICT技術を試験導入する
- ✓ BIM/CIMソフトで3Dモデル作成と情報共有から始める
- ✓ 小規模案件でICT建機をレンタルして試用する
無理なく始め、成功事例を積み重ねることがスムーズなICT化推進につながるでしょう。
人材の育成を進める
ICT施工を円滑に進め効果を最大限引き出すには、ICT技術を理解し活用できる人材育成が不可欠です。高性能機器も使いこなせる人がいなければ、効果は限定的です。
そのため、企業には、中長期的視点で計画的・継続的に従業員のスキルアップを図る投資と環境整備が求められています。具体策として、国交省や業界団体、メーカー主催の研修・講習に参加することが挙げられます。
国交省関東地方整備局HPでは、Webセミナーアーカイブが公開されており、個人でも閲覧できるため、積極的に利用してみましょう。
出典:関東DX・i-Construction 人材育成センター|国土交通省関東地方整備局
出典:人材開発支援助成金|厚生労働省
従来施工とICT施工の比較【実例データあり】
ICT施工がどれほどの効果を発揮するのか、実際の工事現場における従来施工との比較データから見ていきましょう。
以下は、同等条件の3つの工事を対象に、各工程ごとの作業日数を比較した結果です。
① 起工測量:作業日数を平均73.7%削減
従来施工では平均17.7日かかっていた起工測量が、ICT施工では平均2.7日で完了。ドローン測量や3Dレーザースキャナにより、人手・時間の大幅な削減を実現しています。
② 3次元データ作成:平均65.5%の省力化
従来の起工測量結果の整理や図化に平均5.3日かかっていたのに対し、ICT施工では1.5日で完了。点群処理や設計データとの連携により、準備工程が効率化されました。
③ 施工(重機作業+相番作業):平均20.7%の工期短縮
ICT建機の導入により、施工そのものも効率化。丁張り設置や出来形確認の手間が減少し、現場での待機や調整時間も短縮され、全体の作業日数が抑えられています。
④ 出来形計測・⑤ 実地検査・⑥ 電子納品も効率化
- ✓ 出来形計測:平均41.6%削減
- ✓ 実地検査:平均50.0%削減
- ✓ 電子納品:平均26.6%削減
UAVやソナーを活用した計測により、安全かつ短時間で高精度の成果物が得られます。検査も書面主体で済むため、現場対応の負担が軽減されました。
作業工程別の日数比較(平均)
| 工程 | 従来施工 | ICT施工 | 削減率 |
|---|---|---|---|
| 起工測量 | 17.7日 | 2.7日 | 73.7%削減 |
| 3次元データ作成 | 5.3日 | 1.5日 | 65.5%削減 |
| 施工(整地作業) | 44.0日 | 36.0日 | 18.2%削減 |
| 測量等の付帯作業 | 7.7日 | 1.6日 | 75.3%削減 |
| 出来形計測 | 2.7日 | 1.3日 | 51.9%削減 |
| 実地検査 | 1.6日 | 0.6日 | 62.5%削減 |
| 電子納品 | 2.2日 | 1.1日 | 50.0%削減 |
出典:京都府「ICT施工のメリット デメリット」
出典:ICT土工の取組みと効果について|国土交通省
今後建設現場においてICT施工導入は必須?
ICT施工は、国が推進する「i-Construction」政策の中核を担う技術であり、公共土工工事を中心に対象工種が拡大しています。補助金や技術講習などの支援制度も整備されており、導入へのハードルは年々低下しています。
一方、未導入企業は入札競争や品質・納期面で不利になる恐れがあり、将来的に公共工事を継続的に受注するにはICT対応が必須だといえます。
早期に導入体制を整えることで、コスト面の恩恵だけでなく、競争力の強化にもつながるでしょう。
ICT施工導入を成功させるポイント
ICT施工を導入するだけでなく、現場で成果を出すには社内体制の整備が欠かせません。操作研修やトラブル対応の教育、専任者の配置などが成功の鍵となります。
また、高額な建機・ソフト導入には費用対効果の精査が重要で、自社の規模に応じた導入範囲を見極める必要があります。
さらに、ICT建機や支援ソフトの性能・サポート体制はメーカーごとに異なるため、パートナー企業の選定も慎重に行うことが重要です。
まとめ:ICT施工のメリット・デメリットを理解して業務に活かそう
ICT施工は建設業界の生産性向上や働き方改革に有効ですが、導入にかかるコストや通信環境への依存、人材育成といったデメリットも存在します。しかし、補助金の活用や人材育成など、解決法もあります。
「ICT施工を学べる企業に転職するには?」「ICTスキルを身につけて、キャリアアップするには?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ「ベスキャリ建設」にご相談ください。
建設業界に精通したアドバイザーが、ご希望に合った求人をご提案し、転職活動をサポートいたします。
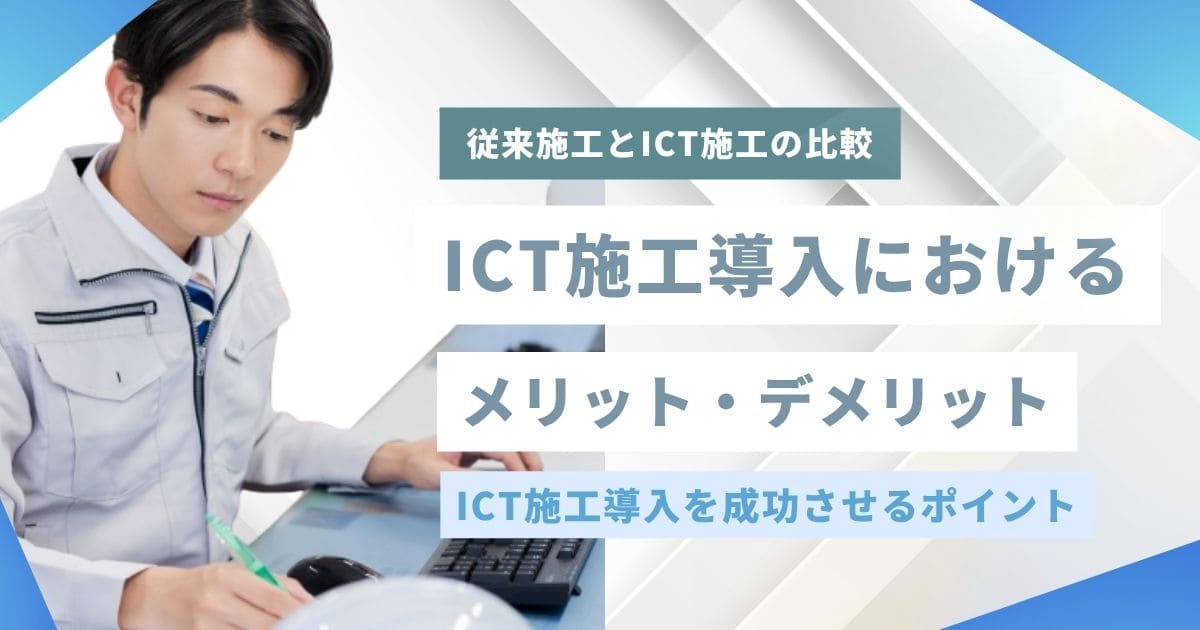




_180x98.jpg)
_180x98.png)
_180x98.png)













.jpeg)


